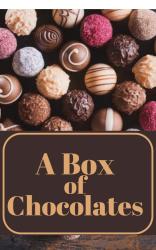――時々、夢に見ることがある。
あの夜のこと。
理性がどこかに消えてしまった、あの夜のこと。
別に、誰にも後ろめたいことはない。
あの時はもう誰とも付き合っていなかったし、誰かの許可が必要なわけでもなかったし。
私は一応大人で、何でも自分の意志で判断できる。
何が起こっても、自分がしたくてそうしたのなら、自己責任で後悔なんてしない。
後悔はしないけど……思うところは、いろいろとあるけど。
ワインを飲みながら話していた時のようには、部屋での私たちはほとんど言葉を交わさなかった。
お互いの名前もそのほかの何もかも知らなかったけれど、何の不安もなかった。
冷ややかで滑らかなサテン織のシーツの上で起こったことは、およそ現実とは思えなかった。
私の指を絡めとる長い指や、私の鎖骨のくぼみに落ちてきた汗のしずく。
生理的な涙を吸いとる唇、そこから覗く、私を翻弄する舌。
知らない感触、知らない香り、知らない吐息。
知らない肌、知らない背中、知らない体温、知らない重み。
何よりも、欲望がたゆたうあの瞳。
あの瞳に見つめられると、おなかの奥がうずいて切ない吐息が漏れた。
私の中にも「この男が欲しい」という渇望が生まれて、何もかも忘れてしがみついた。
あのひとは冗談交じりに「忘れられなくて後悔しても知らない」と言っていたけれど……
後悔はないけれど……忘れられなくなったのは、本当みたい。
私自身も知らなかった、大胆で自由で、わがままな私。
それが知れただけでも、あの夜のことは私の人生の中で、何か意味を成したと思う。
うん、そう。
もう二度とあんなことはない、そう確信していたんだけど……
金曜日、午後11時23分。
「さくー! さくいもー!」
ご機嫌な酔っ払いが電話をかけてくる。
「なんでしょうか、酔っぱらい暉ちゃん?」
「タクシー捕まんないー! 迎えに来てー!」
はいはい。そうなると思っていたよ。
「どこ?」
「緑ヶ丘駅の近くの、リヴ・ドワットゥっていうワインバー。すぐわかるよー」
「近くまで着いたら電話するから、それまでしっかりしておいてね」
「うん、おっけぇ~」
「お友達も一緒?」
「うんうん、あ、二人連れてくからー」
「えっ? ひとりって言ったじゃん……」
酔っぱらいには何を言っても通じない。電話を切って、あと一人分の布団の準備を急いで客間に出す。
父のハイブリット車のキーを手に、はーっとため息をつく。結婚も兄の面倒も見るのもあまり差はないかもしれない。
おばあちゃんになっても、振り回されるのかな?
金曜の繁華街へ車を乗り付けるなんて、あまり運転が得意ではない私にとっては神経が磨り減るストレスフルな行動だ。
念のためググって店の住所と外観を調べてきたので、店はすぐに見つけることができた。
「リヴ・ドワットゥ……右岸。ここだ」
店の前に停めて、急いで電話をかける。
「今前にいるから急いで出てきて」
1分後、2階の店の扉が開いて男が3人出てくる。
「お迎えありがとなー、いも。こいつらはぁ、高校ん時からの友達のヒロトとソウ。乗れ乗れー」
助手席に倒れこむように乗り込んで、暉はひらひらと手を振る。強烈に酒臭い。後部座席のドアを開けてカジュアルスーツの男性と、黒いバックパックを持ったTシャツ黒シャツにキャップを被った眼鏡男子が遠慮がちに乗り込んでくる。
「はじめましてなのに、すみません。お世話になります。ヒロトです。こっちがソウです」
カジュアルスーツ姿の男性が申し訳なさそうに頭を下げて苦笑する。私は座席越しに頭だけ振り返っていいえ、と答える。眼鏡のほうの男性はぺこりと頭を下げた。
ふたりとも、暉ほどは酔っていないようだ。
高校時代は暉は友達の家に入り浸っていたし、私は暉の学校とは逆方向の隣の市の女子高に通っていたから、暉の高校の友達とは面識がない。家に何度か遊びに来ていたことがあったみたいだけれど、人見知りの私のために暉はわざわざ友達を紹介するようなことはなかった。
「こいつらとは一通りやんちゃしたな。留学した時も一緒だったしー。なぁぁぁ?」
「お前、酔いすぎでしょ」
眼鏡のソウさんが呆れたように言う。
「久々で嬉しかったんだよな?」
カジュアルスーツのヒロトさんが苦笑する。
「帰ったらぁ、あれ、開けるぞぉ。ボルドーの変わったワイン!」
「はいはい……」
ふたりは棒読みで返事をする。やはり、暉の扱いには慣れているようだ。
家に着くと、二人が両側から酔っぱらいを支えてくれる。よかった。私一人では部屋まではおろか家の玄関まで運ぶのも難しかった。先回りして玄関のドアを開け、1階の暉の部屋まで誘導する。
「隣の部屋にお布団用意してあります。あとトイレとお風呂は……」
私が言いかけると、ヒロトさんが言った。
「あ、昔来たことあるんで大丈夫です。ご迷惑かけてすみません。ありがとうございました」
私はそれじゃあ、ごゆっくりと言って暉の部屋を出る。やれやれ。
老舗旅館にありそうな古い階段をひとつ上がり2階の自室に行こうとしたところで、後ろから呼び止められる。
「あの、ちょっと。グラスをもらいたくて」
振り返ると、キャップを脱いだ眼鏡のソウさんが立っていた。廊下の電灯が暗めなので、表情はよく見えない。
「ああ、はい。こちらです」
私は段を降りてキッチンへ向かう。ソウさんはついてくる。
「ええと、ボルドーって言ってましたよね」
私はキャビネットからボルドーグラスを取ろうと手を伸ばす。
「兄も妹も、酒にはあんまり強くないんだな」
グラスに触れかけた私の指が止まる。
「えっ?」
振り返る。首をかしげる。
ソウさんは私の背後から棚に手を伸ばしてグラスを三つ取り、テーブルの上に置く。後ろから小突かれる感じで、私の体はキャビネットに張り付く。ふいにウエストを後ろから摑まれて支えられる。うん? なに? なんか、デジャヴ?
黒ぶちメガネがグラスの傍らに置かれる。
「クラウド・ナイン」
後ろから耳元で低い声がおかしそうに囁いた。唇が耳珠に触れる。
その声が尾てい骨を直撃して、落雷したかのような衝撃が走る。
かく、と足に力が入らなくなると、くすりと微かな笑いがまた耳をかすめる。
「やり逃げするとはひどい女だな」
「‼」
振り返る。おそるおそる。
どうして……
それは、あの夜の、あの人だった。