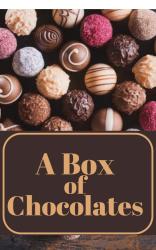「さっき、私の愚痴を聞いていて、ところどころ鼻で笑ったよね? 私のこと、気が小さくてまじめすぎるつまらない奴って、ディスったよね?」
エレベーターが到着する。
ほら、と促されるのを首を横に振って拒否する。
エレベーターが締まり、下に行ってしまう。
「いや、べつにばかにしたわけじゃない。俺とは真逆だと思っただけ!」
「私、今の自分が嫌になってきた。もしもこのまま年を取って死んだら悲しすぎる」
「それが俺を責めるのとどんな関係があるんだよ?」
私は背伸びをして、彼の顔を両手でとらえた。その時、初めてまともに……数時間一緒に飲んで愚痴を聞いてくれた相手の顔を見た。
いや、本当は、今までは意図的に見ないようにしていた。一瞬、動揺する。
はじめから、声は低くて素敵だと思った。指も長くてきれいだと思った。やはり……造作も超絶整っていた。
おかげで11万円のワインの余韻がすべて吹っ飛んで一瞬で素に戻ったけれど、そこで怯んだら負ける気がした。
何に?
勝ち負けなんて、まったく気にしない人生なのに?
それが俗にいう、「魔が差す」ということに当たるのかもしれない。
「——明日、日本を発つんでしょう?」
「そうだけど」
「それでもう、帰ってこないんでしょう?」
「いや、一時的に出てるだけ。この国の人間だからそのうち戻ってくるけど」
「いい加減なのは気楽だから、決まった相手はいらない、あんたもやってみればいいって、言ったよね?」
「い、いや、それは」
「おしえて。真逆の側を」
「……」
彼は不思議なものを見るように私を見下ろして、やがてふと困ったような笑みを浮かべた。
私の両手をすり抜けて、私の目線の高さにまでぐぐっとかがんできた。
「なかなか衝撃的な誘い方だな。俺を利用する気か」
距離が狭まる。
「人聞きが悪……い」
後ろは壁。逃げ場はない。鼻先が掠れ合う。
私は目を伏せる。じっと見つめられて、見つめ返せなくなる。アルコールの力を借りても、強がっても、しょせんはミジンコ、究極のビビりだ。
彼は私のウエストを自分のほうへ引き寄せながら、エレベーターのパネル”⇧”に触れて鼻で笑う。私がパネルの前で邪魔だったらしい。
「まぁ、いいか。後悔して泣いても、知らないからな」
脚が震える。ウエストを支えてもらっていなかったら、多分その場にへなへなと崩れ落ちてそう。それでも再び視線を上げて、彼の目をまっすぐに見すえた。
「また、ばかにしてるの?」
唇が、話すたびにかすかに触れ合う。
「ちがう。俺のことが忘れられなくなるっていう、そういう意味で」
エレベーターの扉が開く。無人。
言い返そうとしたときに下唇を甘噛みされる。
そしてそのまま手首をつかんでガラスの空間に引き込まれる。ガラスの扉からは夜景が見下ろせるけど、もうそれどころじゃなかった。
エレベーターは振動も音もなく静かに上昇していく。
息をするのもままならなくて、頭の中は真っ白になった。
な、なんと……私が、誘ったんだ……‼
「おはようございます」
淹れたてのコーヒーを差し出して昨夜のお礼を述べる。
「昨日は夕飯をごちそうさまでした。早速ですが、あれからワインをいただきまして……その、夢のように、おいしかったです」
――今では、すべて夢だったということにしてしまいたい。
「おはようございます。喜んでいただけたようで、何よりでした」
専務の笑顔には、少し同情が混じっている。「結婚はナシになりました」と言ったから、私が傷心していると思っているのかもしれない。
それよりも私は昨夜、自分の認識限界値をはるかに超えてしまったのです、とはお伝え出来ませんが。
「あのあと、無事に帰宅されましたか? 私は副社長に朝方まで付き合わされて散々でした」
はは、と専務は苦笑する。私も、はい、とだけ答えてにっこりと笑み返す。
――言えるわけがない。
本日の午前中、専務は営業部の部長と全課課長との会議に出席する。その間、私はニコイチ片割れの翔ちゃんとふたりで、途中休憩のお茶の準備をする。
「いいなぁ、朔。昨夜は専務にA5ランク連れて行ってもらったんだよね。あそこのシャトーブリアン、口の中でとろけるんだよね。僕も食べたかったー」
のんびりと話してはいるが、翔ちゃんの手元は高速でお茶菓子を一人分ずつに仕分けている。
「ついに伝えたんだよ。結婚は、ナシになりましたって。こっちが申し訳なくなるくらいに、さりげなく励まされたわ……」
「そっか。結婚するって報告して数日でやっぱりしなくなったって、ちょっと言いづらかったよね、朔。それで、あの人どうすることにしたって?」
駿也が私の恋人ではなくなったので、翔ちゃんは「奴」とか「あいつ」と呼ぶのをやめたらしい。
「まだはっきりとは決めてないけど、ミラノで就職する予定みたい。彼女はもう帰国したらしいけど、お正月休みには向こうに行ってくるって」
「そうか。元カノと浮気だと思ったら、意外な結末だったよね。朔が思ったよりダメージ激しくなくてよかったけど……なんか、今日きみ、めっちゃ疲れてない? ん? あれ? ちょっと、んん⁈」
お茶菓子を袋から開けて差し出した時、翔ちゃんは目ざとく私の手首の小さなあざを見つけ、両手ではっしと捕まえて私のスーツの袖をめくった。
「いやちょっと、朔、なにこれ? 指のあとじゃん! あっ、こっちはもしや! えっ? ちょっと、きみまさか専務と……?」
「かっ、翔ちゃん! 違うから‼ し――っ!」
私は使われていないほうの手で翔ちゃんの口をふさいだ。彼は大きな目で探るように、好奇の色を浮かべながら私をじっと見つめた。こくりと頷くと翔ちゃんも同様にうなずいた。私が口元から手を外すと、翔ちゃんは私の手首をつかんだまま口元を吊り上げた。
「朔、話して。誰が付けたの、これ?」