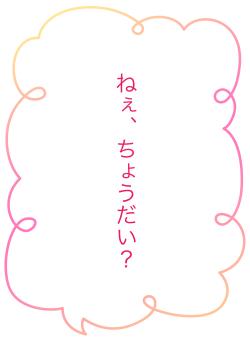「凰牙くんのことが、好きだから」
私がそう言うと、凰牙くんは少しうつむいたまま、徐々に私との距離を詰めてきた。
「ーーえ、え!?ちょ、お、凰牙くん!?」
気づいたら私は屋上の入り口の壁にまで追い詰められており、私の背にはその硬い壁があたっていた。
私より約20センチほど背の高い凰牙くんが、私のことを真上から見下ろす形になった。
この1年間、こんなに近くにいたことがなかったから、私の心臓はとてもうるさい。
心臓の音が、凰牙くんに聞こえてしまいそうだ。
「…美姫」
「は、はい」
「覚悟、できてるんだよな?」
そう言う凰牙くんの目は、少しも笑っていなかった。