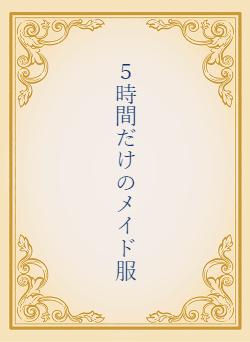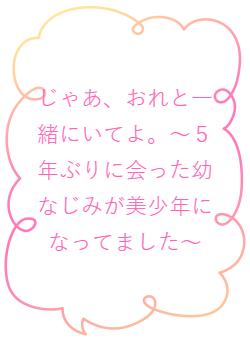画材を入れた鞄をひっくり返すようにして、そこに入れたままの自分の絵を審美した。
悪くないといえば悪くなく、ひどいものだといえばひどいものでもあるそれが実際にどんなものなのかという答えは、少なくとも、陽が沈みあたりが暗くなってきたことで家の中に戻ってからもでなかった。
わたしは昔から、自分のものを客観的に判断するというのがどうしようもなく苦手だった。小学生の頃、よく、テストを解き終わってからは見直しをするようにといわれたけれど、何度見直しても答えは変わらなかった。わたしはいつだって漢字を間違えてはいなかったし、式も答えも正しかった。
当然だ、ほんの数分前の自分が、それが正しいと思って書いたものなのだから。ほんの数分で答えが変わるほど、わたしは気まぐれではない。わたしはいつだって満点の答えを書いていた。
しかし、数日後に返ってきたテストには、赤いインクで『88』とか『92』とか書かれていた。ひどいときには『74』とか『62』とかいうときもあった。
そういうときだって、もちろん、わたしは満点の答えを書いていた。人物とできごとを正しく結びつけ、漢字や顕微鏡の部品の名前を正しく書き、文章から正しい情報を読みとり、正しい式を組み立てて正しい答えを導きだした。解き終えて残った時間で、その正しさを何度も確認した。
わたしはいつでも正しかった。それ自体が間違っていた。
わたしは自分がどんな人間なのかがわからない。容姿がものすごく醜いかもしれないし、反対に美しいかもしれない。とても聞きやすい声や言葉で話すかもしれないし、反対になにをいっているかまるでわからないかもしれない。
そういうあいまいなものを、テストの赤いインクは、公平に、本当に正しく評価した。わたしは正しい答えを書き、ときに間違えた。
しかし、絵というのはどうだろう。こうだから美しい、そうだからこうじゃないという基準は、ないか、あったとしてもとてもあいまいなものだと思う。
わたしはテスト用紙の上での自分の間違いにも気づかない。
自分の絵が美しいかそうでないかなど、まるでわからない。
「どうした?」と声が聞こえて、はっとした。顔をあげれば、お父さんがこちらを見ていた。
「難しい顔して」
「わたしって……絵、うまいのかな」
「うまいんじゃない?」
「違う、そうじゃなくて。趣味じゃなくて」
「ええ」と、お父さんは驚いたようでもあったけれど、それと同じくらいに笑っているようでもあった。「画家にでもなるのか?」といった声にはその笑いがより濃く感じられた。
こめかみのあたりに血管が浮くのを、妙に冷静に感じた。
あ、むかつく。すごいむかつく。
黙らせる。こいつ絶対黙らせる。
なにを弱気になってるのよ。わたしって絵うまいのかなじゃないでしょ。へたならうまくなればいいでしょ。なんだって誰かに評価させようとしてるのよ。
それに、わたしは時本はなでしょう。努力さえ怠らなければ、驕らなければ、時がくれば咲くのよ。わたしは花じゃない。わたしを咲かすのは、ほかならない時なのよ。
時の本に咲うのが、わたしでしょう。
直前までの弱気さにまで腹が立ってくる。
感情的になっているのもばからしくて、わたしはそっと深呼吸した。テーブルの上の絵を集めて立ちあがる。
離れたリビングから、「なんであんないい方するの?」とお母さんの声が聞こえた。
悩むことなんてない。わたしはただ、美しいものを描けばいい。きっと、誰かがそれを認めてくれる。笑わずに受け入れてくれる人が、どこかに必ずいる。
悩む必要なんて、ない。
悪くないといえば悪くなく、ひどいものだといえばひどいものでもあるそれが実際にどんなものなのかという答えは、少なくとも、陽が沈みあたりが暗くなってきたことで家の中に戻ってからもでなかった。
わたしは昔から、自分のものを客観的に判断するというのがどうしようもなく苦手だった。小学生の頃、よく、テストを解き終わってからは見直しをするようにといわれたけれど、何度見直しても答えは変わらなかった。わたしはいつだって漢字を間違えてはいなかったし、式も答えも正しかった。
当然だ、ほんの数分前の自分が、それが正しいと思って書いたものなのだから。ほんの数分で答えが変わるほど、わたしは気まぐれではない。わたしはいつだって満点の答えを書いていた。
しかし、数日後に返ってきたテストには、赤いインクで『88』とか『92』とか書かれていた。ひどいときには『74』とか『62』とかいうときもあった。
そういうときだって、もちろん、わたしは満点の答えを書いていた。人物とできごとを正しく結びつけ、漢字や顕微鏡の部品の名前を正しく書き、文章から正しい情報を読みとり、正しい式を組み立てて正しい答えを導きだした。解き終えて残った時間で、その正しさを何度も確認した。
わたしはいつでも正しかった。それ自体が間違っていた。
わたしは自分がどんな人間なのかがわからない。容姿がものすごく醜いかもしれないし、反対に美しいかもしれない。とても聞きやすい声や言葉で話すかもしれないし、反対になにをいっているかまるでわからないかもしれない。
そういうあいまいなものを、テストの赤いインクは、公平に、本当に正しく評価した。わたしは正しい答えを書き、ときに間違えた。
しかし、絵というのはどうだろう。こうだから美しい、そうだからこうじゃないという基準は、ないか、あったとしてもとてもあいまいなものだと思う。
わたしはテスト用紙の上での自分の間違いにも気づかない。
自分の絵が美しいかそうでないかなど、まるでわからない。
「どうした?」と声が聞こえて、はっとした。顔をあげれば、お父さんがこちらを見ていた。
「難しい顔して」
「わたしって……絵、うまいのかな」
「うまいんじゃない?」
「違う、そうじゃなくて。趣味じゃなくて」
「ええ」と、お父さんは驚いたようでもあったけれど、それと同じくらいに笑っているようでもあった。「画家にでもなるのか?」といった声にはその笑いがより濃く感じられた。
こめかみのあたりに血管が浮くのを、妙に冷静に感じた。
あ、むかつく。すごいむかつく。
黙らせる。こいつ絶対黙らせる。
なにを弱気になってるのよ。わたしって絵うまいのかなじゃないでしょ。へたならうまくなればいいでしょ。なんだって誰かに評価させようとしてるのよ。
それに、わたしは時本はなでしょう。努力さえ怠らなければ、驕らなければ、時がくれば咲くのよ。わたしは花じゃない。わたしを咲かすのは、ほかならない時なのよ。
時の本に咲うのが、わたしでしょう。
直前までの弱気さにまで腹が立ってくる。
感情的になっているのもばからしくて、わたしはそっと深呼吸した。テーブルの上の絵を集めて立ちあがる。
離れたリビングから、「なんであんないい方するの?」とお母さんの声が聞こえた。
悩むことなんてない。わたしはただ、美しいものを描けばいい。きっと、誰かがそれを認めてくれる。笑わずに受け入れてくれる人が、どこかに必ずいる。
悩む必要なんて、ない。