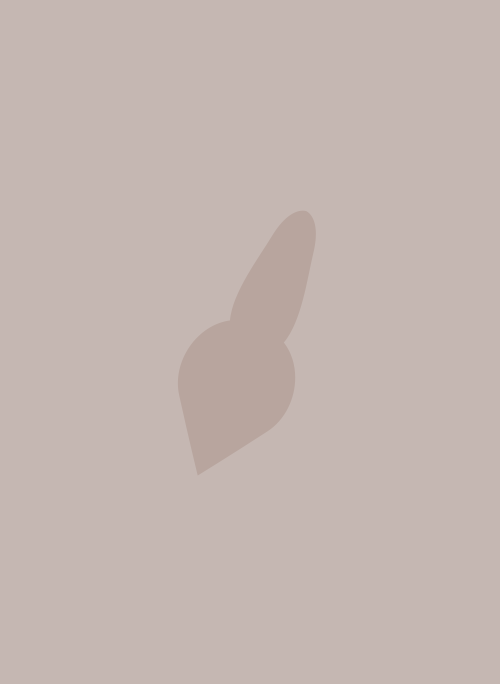「それね、アカンサスっていうの」
ジッと絵を観察していると、彼女が声を掛けてくれた。物静かな声色だったが、玄関を通じて音は廊下に反響し、増幅されて聞こえた。美術館みたいだと思った。
「花言葉は芸術、芸術への愛、美を好む。私が生まれた日に、美しさの象徴としてお父さんが描いたの。これは人生で最初の誕生日プレゼントなんだ」
絵の下のボタンを彼女が押すと、濃いオレンジ色の光が下部から差し込みアカンサスを照らした。
粋な計らいだ。ついでにもう一つ、靴箱の上にあったミニプラネタリウムにも電気が通っていたらしく、天井には星空を見立てた光の点々が広がった。
「すげぇ、夜に見たら綺麗なんだろうね」
「夜まで親は帰ってこないから、それまで居る?」
思いのほか彼女は積極的なんだなぁと思って僕は驚いた。こうまで言われると逆に不安になってきて仕方がない。けど、僕がここに来た目的はただ一つだった。
彼女が作った垢玉を、一目だけでもいいから見てみたい。