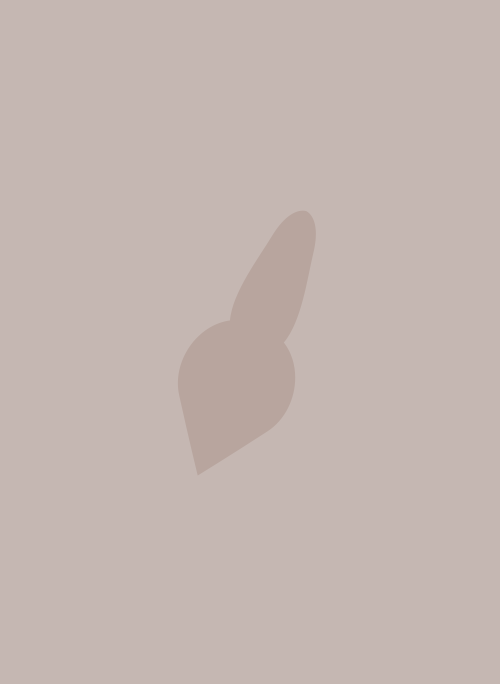彼女の目の奥の輝きは、まるで職人が自分の作品と真剣に向き合い、納得のいくものを、仕上げていこうと意気込んでいるような深みがあった。
食事をしている最中もずっと、彼女はどこか遠くに意識を向けているようだった。彼女は間違いなく僕の目の前で食事をしているのだが、魂は肉体からいったん離れ、故郷へと帰ろうと、身支度を整えているように思えた。
しかし、それは決して死を連想させる表情ではなく、むしろ命の輝きで生き生きとした表情がそこにあった。
たいての人々は、意識が肉体からいったん離れて別の場所に行ってしまっている時よりも、現実世界に目を凝らし、地に足をつけ生きている時のほうが、ずっと死に近い。
彼女の表情は、まさしくそれを体現していたように思う。
「ねえ、瀬戸くん。ほんとうに今日来てくれるの?」
彼女は、うわのそらのまま、そう言った。
「いいよ。僕は、君が作った垢玉を見たいんだ。どんな姿をしているんだろうって、興味があるんだ。ほんとうに、君の垢玉は神秘的なものなんだろうね」
彼女は少し笑って、嬉しい、と言った。その目は儚くもあり、輝かしくもあった。
脈拍がやや高い。鼓動も強い。外の空気は新鮮で、こんなにも麗らかなのに、僕の胸の高鳴りだけは収まらない。藍ちゃんが隣にいるという興奮、そして彼女が作った垢玉を、これから拝見することができるかも知れない恐ろしい程の期待感。
どれも僕を高揚させるものだ。
電車に乗り、席に座る。揺れを感じながら、到着を待つ。僕が実際には一度として拝見したことのない垢玉という奇跡の代物を、見に行く。期待は興奮となって僕の胸の奥をジリジリと刺激した。
電車がだんだんと速度を落とし、彼女の家の最寄り駅に停車する。彼女は自然と早足になる。僕もそれに合わせて、足を速くする。