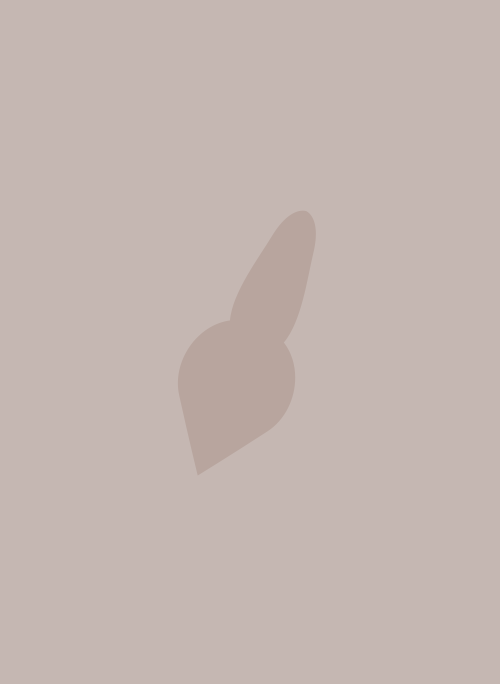さっきからコガネムシが僕の周りを飛んでいる。緑色の体には太陽の光が反射している。
しばらく僕の周囲を旋回してから、持っていた缶コーヒーのタブに止まった。
「うわー、きも」
隣にいた藍ちゃんは、僕の缶コーヒーのタブに乗っかっているコガネムシを見て、嫌悪感にあふれるような声を出した。僕は藍ちゃんが悪口を言うのを初めて聞いた。彼女はいつも、おしとやかな人だ。と僕は思っていた。
「そんなに嫌いなの? コガネムシ」と僕は彼女に聞いてみる。
「いや、いきなり来るから反射的にキモイって言っちゃったの」
と彼女は言った。藍ちゃんは、なんだか申し訳なさそうにしていた。
僕と彼女は、べつに恋人どうしではない。もっと言うと先ほど出会ったばかりである。
僕は二限の空き時間、暇つぶしに文芸部の扉を叩いた。男友達と他愛のない話をするためである。僕はそこで黒髪の美しい女性を見つけた。けれども話しかける接点がなかった。僕はもどかしい気分を感じていた。
それから男友達とある作家についての見解を述べる座談会が始まった。僕は、彼の作品の性描写について絶賛した。僕は文芸部の所属ではなかったが、これだけは語りたいと譲らなかった。彼が描く濃密な性描写は、決して世間が言うほど低俗ではないことを、僕は真剣に語った。議論がヒートアップしてきた時、
「熱いですよねぇー、あの人の性描写」
ふと輪の外側から声が聞こえたのだ。
それは、今までの暑苦しい男たちの声ではなく、もっと柔らかな、落ち着いた女性の声だった。
僕はそれが、先ほどの黒髪の美少女であることを知って衝撃を覚えた。この機会を決して逃してはならない。いま彼女とお話をしなくてはこの先、未来永劫に彼女とお喋りをする機会が無くなってしまう、と思って、僕は無我夢中で、かつ慎重に言葉を選びながら彼女とお喋りをしまくった。
そうして今、この状況である。
大学のグラウンドの横にあるベンチに二人で腰を掛け、二人で飲み物を飲みながら、僕の缶のタブに止まっているコガネムシを一緒に眺めている。
僕は戸惑っていた。正直、もう彼女と話すべき内容が底をついた。何をしゃべっていいか検討もつかない。もともと付け焼き刃のナンパみたいなものだ。これまでか。
空は快晴で、飛行機雲が一筋、流れている。柔らかな春の日差しを感じながら、清々しい風を頬に受けている。ベンチの横の花壇に咲いているビオラやサルビアや、マリーゴールドの花々が揺れている。
せめて最後は、勇気を振り絞って連絡先を交換しなくては、と考え、声を出そうとした時だった。
「……瀬戸くん。垢玉って、知ってる?」