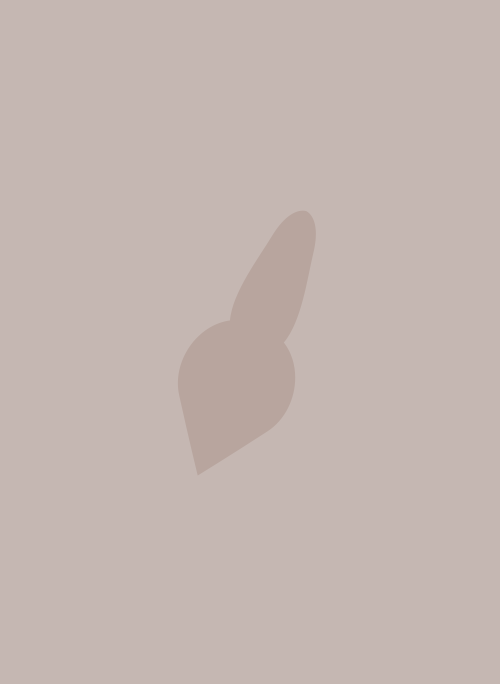階段をやっと上り終えると、そこは木の匂いでいっぱいだった。家の中に、森が広がっているかのような錯覚さえ覚えた。
階段を登り切ってすぐ目の前の扉の前で、彼女は立ち止った。ここが君の部屋なのか、と僕は思う。鼓動はより強いリズムを刻み始め、いよいよ垢玉の気配が強くなり、神秘と芸術の匂いがした。
彼女はドアを開ける、そのまま走って部屋の中まで入り、ベッドの横の棚の引き出しから、あるものを取り出した。ゆっくり、ゆっくり藍ちゃんは僕に近づいて、垢玉のペンダントを僕に差し出した。
時が止まったように感じた。外観はかなり凄かった。深い群青を基調とする色の中に、金色の装飾、金色の鎖、そして真ん中の垢玉。
その中心にある垢玉の存在だけが異様な光沢を見せていて、この世の物質ではないかのような表情をしていた。
「中が開けるようになっているの。開いて、明るい所に向けて、裏側ののぞき穴から見て。垢そのものが見えるよ」
金色の装飾の横側に、小さな突起がある。押すと、ペンダントは開いた。生々しい垢玉が見えた。
裏返し、のぞき穴に僕は目を近づける。窓の外の光を通し、僕はジッと眺める。見えたのは、垢だった。
背筋が凍り付くように、おぞましい程、美しかった。垢は、まるで何光年も離れた遠くの星の大気のように渦巻いている。垢は波打ち、うごめいている。生き物の反射のように、千切れたミミズの足掻きのように、垢はうねりを生じている。
「いいでしょう」
藍ちゃんは僕にそっと顔を近づけた。肌と肌が触れそうになる程、近かった。彼女の吐息が首筋に掛かる。呼吸が速くなる。美しさと興奮で手足が痺れるような感覚を得る。足の震えを抑えながら、垢玉の魅力に翻弄され、打ちのめされた。
光を受け淡く輝いている、どす黒い垢は、この世界の終焉のようだった。人間の垢はこんなにも醜悪で、おぞましく、そして悪魔的な魅力がある。
言葉を失った。
垢玉の表情は自然と網膜に焼き付いていた。今後、僕がいつどこにいて、何をしていようと、この垢の真っ黒いうねりのような姿は、決して忘れることができない。
垢の表情を見ている間、僕の魂は別の世界にあった。この場所が藍ちゃんの部屋の中で、目の前には藍ちゃんがいることなど忘れていたような気がした。
ふと気づいたとき、僕は確かな疲労感を覚えていた。少し汗ばんでいる。身体の力が抜け、筋肉が緩んだような感覚、そんな気がしていた。
「凄かった」と、僕は言う。彼女は、それは良かったね。見てくれてありがとうね、と言う。僕は、このように、最高に美しくグロテスクな物体を見せてくれた藍ちゃんに感謝を伝えた。彼女は喜んでいた。だんだんと日が落ちていく、夕日が濃く赤くなり、部屋の中は暗くなる。
僕もそのうち、作るよ、垢玉。と彼女に伝えた。近いうちに実際に垢玉を作りに行こうと思ったのだ。しかしその直後、彼女から思わぬ一言を告げられた。
「……私、垢玉の掘り師になりたいの」