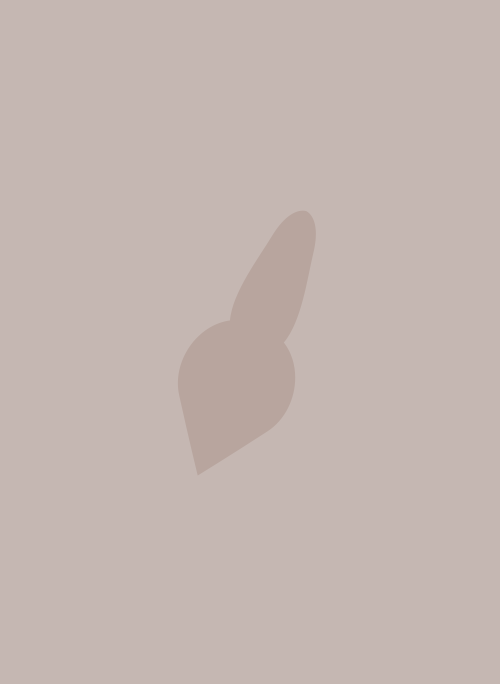当然、彼女とより親密な仲になれるに越したことはないのだが、やはりここまで来たからには垢玉を見物するしかない。電車に乗ったあたりから、僕は彼女の垢玉の存在を一度たりとも頭から離してはいない。そればかりか、より垢玉に対する期待感が膨らんでいた。
垢玉はそれくらい神秘的である。彼女の垢玉だからこそ、その神聖さにはより拍車がかかるのかも知れないし、垢玉を作った異性だからこそ、僕はより藍ちゃんを魅力的だと思うのかも知れない。
天井に浮かんだ無数の光の点々を眺めながら、僕は呟く。
「ここは、落ち着く家だね」
「広いだけよ」
と彼女はほほ笑んだ。靴を脱ぎ、廊下を渡る。砂刷りの壁を初めて見た。砂の一粒は意外と大きく、黄色い。もろく、所々に擦れて削られた跡があった。
長い廊下を僕たちは無言で渡る。洗面所の近くを通ると石鹸の匂いがしたし、和室の近くを取るとビャクダンのお香の匂いがした。深く、心地よい香り。
その香りの中に、確かに存在する垢玉の気配を僕は感じる。垢玉が近くにある。そう僕は確信したのだ。
「私の部屋は三階にあるの、階段、気を付けてね」
と彼女は言った。階段の一段一段の角に滑り止めが付いていた。
窓から差し込む日の光が雲に隠れると、辺りはちょっと薄暗くなり、足元の滑り止めが淡い緑色に光っていることに気が付いた。昼に光を吸収し、夜の暗闇の中で足元を照らすようだ。