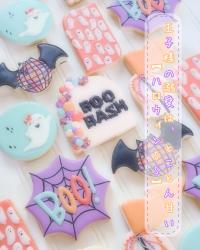私にしか聞こえないくらいの声でそう言われ、何も抵抗できないままクラスを後にした。
「…本当にごめん。やっぱり辞めさせるべきだった」
さっきはあんなにかっこよかったのに、数学準備室に着くや否や項垂れる先生。
「いいよ、もう。…助けてくれたし」
「それは、当たり前でしょ。彼氏なんだから」
「…っ!!か、彼氏…」
私が欲しかった言葉をサラッと言ってのけた先生は、不思議そうに私を見つめる。
「え。なずな、ちゃんとわかってる?」
「…わかっ、てるよ。でも…実感なかった」
つい最近までわからなかったなんて、口が裂けても言えない。
「そっか…じゃあ、こっち来て」