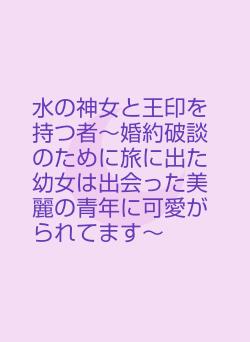謎の人物からアマーリア宛に大量の贈り物が届いてから数日後。
「お嬢様、届きましたよ」
「ありがとう」
ソマリから小さな箱を受け取り、箱を開くとそこに納まっていたのはネックレスだ。
先日の夜会で男性からもらった石をネックレスにしてもらった。
「美しいですわね。おつけしますわ」
ソマリからつけてもらい、鏡で確認する。
「よくお似合いですわ」
「ありがとう」
ハーディスは自分の胸元で輝く赤い石を見つめる。
正直、似合っているのか分からないが、胸元にあるこの石が自分を守ってくれているように感じる。
「今日はそちらでよろしいですか?」
「えぇ」
ハーディスは他の宝石箱に視線を落とす。
大きな宝石箱にはもっと沢山のアクセサリーが入っていた。
ほとんどがお母様の形見でしたのに……。
自分が買い与えられたものはほとんどなく、母が亡くなる前にハーディスに譲ってくれたものだ。
しかし、母の形見を独り占めしていると言われ、ほとんどアマーリアに持って行かれてしまった。
気付けば一つ、また一つと姿を消す宝石達は気が付けばアマーリアが身に着けている。
お父様や色んな男性から沢山宝石やドレスを贈られているというのに。
それでもハーディスが持っているものを欲しがるのだから困ったものだ。
しかし、この赤い石だけは渡したくない。
常に身に着けられるようにネックレスにしておりて正解ですね。
「いつ鼠が入るとも限らないですしね」
『噛み殺してもいいぞ』
『あぁ、それは名案だ』
『鼠なんて美味しくないわ』
口々に愛犬達は言う。
可愛い見た目とは裏腹に過激な子達だ。
「殺しては駄目ですよ」
そう言えば愛犬達は不服そうな声を漏らす。
「お嬢様、お言葉ではございますが、アマーリア様やノバン様にはもっときつく言ってやってもいいのではないですか? 私は悔しくて悔しくて」
そう言ってハンカチを噛むソマリにハーディスは苦笑する。
言ったところで無駄だということは分かっている。
アマーリアの魅了の力は強く、何を言っても周りは彼女の味方をするからだ。
「それに……旦那様に本当のことをお伝えしては如何ですか? そうすればきっと…………」
ソマリの言わんとしていることを察し、ハーディスは首を横に振る。
「良いのよ、今更でしょう。それよりソマリ」
ハーディスは引き出しから一枚の封筒を差し出す。
「貴女はもう少しで退職が決まっているけど、もしも退職前に追い出されるようなことになったり、ここを辞めたくなったらこれを持って行って」
それは貴族の屋敷で働けるように書いた紹介状である。
封筒を留めているのはファンコット家印だ。
「そんな、お嬢様!」
慌てて封筒を突き返そうとするソマリを手で制する。
「もしもの時の為にね。貴女にはとっても世話になったわ。他の使用人達は私の元を離れてしまったけど、貴女だけは残ってくれた」
ハーディスの身の回りを世話してくれていたのはほとんどが母の使用人達だった。 母が亡くなると彼女達はほとんどがアマーリエの元へ行ってしまった。
それでもソマリだけは変わらずハーディスの側にいてくれたのだ。
ソマリがいてくれたからハーディスは孤独ではなかった。
「ありがとう、ソマリ」
震えるソマリの手を包み込み、感謝の言葉を送る。
「ハーディスお嬢様っ……」
ぼろぼろと涙を零すソマリにハーディスは微笑む。
「さぁ、涙を拭いて。喉が渇いてしまったの。お茶を淹れてくれる?」
ハーディスの言葉にソマリは頷き、部屋を出た。
「今日はこちらをお召しになっては如何でしょうか?」
メイドに勧められたのは先日謎の人物から贈られたネックレスだ。
大粒の青いサファイアが一粒と細かい細工のあるもので高価なものであると一目で分かる。
正直、今着ているドレスとは合わない気もするが、高級品を身に付けるのは悪くない。
「たまにはあまり身に付けない色味のものも良いわよね」
そう思い、サファイアのネックレスを首に掛けて部屋を出る。
今日はお茶会に招かれている。
そこでみんなに自慢して、男性達を煽ってみようかしら。
財力を示すためにみんなが自分に宝石を贈るだろうと予想すると面白くて笑ってしまう。
アマーリアは廊下に出ると中庭でお茶を飲みながら本を読む姉の姿を見つけた。
いつもと同じドレスは母のお下がりで地味な色味が肌をすくませて見える。
近くで見ればあちこちが解れて生地が薄くなっていてみすぼらしい。
そんな姉を鼻で笑い、新しいドレスで目の前を通るのがアマーリアは好きだった。最高の優越感に何度やっても胸が高揚する。
挨拶の一つでもしてあげなくちゃ。
そんな風に思っていると、ハーディスの胸に輝く何かが見えた。
燃えるように赤色の宝石が姉の胸でキラキラと輝いている。
アマーリアは思わず、窓から外を食い入るように覗き込んだ。
まだあんなに素敵な宝石が残っていたの?
母の形見である宝石で目ぼしい物は全てアマーリアが奪った。
姉の宝石箱の中には時代遅れのデザインか、宝石としてはあまり価値のないようなものしか残っていない。
あれだけどこかに隠していたのかしら?
アマーリアは悔しくて無意識に爪を噛む。
あんな素敵な宝石、お姉様には似合わないわ。
私の方がきっと似合う。
どうせ、盗っても文句も言ってこない。
最初のうちは自分の物がなくなる度に怒りを顕わにした姉だが、その度に父やノバン、屋敷の者達を味方に付けて姉の物を奪ってきた。
次第に文句を言うことも諦めて何も言わなくなった。
きっと今回もいつもと同じだ。
「ちょっと」
アマーリアは側仕えのメイドに耳打ちすればメイドは快く頷く。
「お姉様には似合わなくてよ」
姉の首に掛かるネックレスを見つめてアマーリアはほくそ笑んだ。
「お嬢様、届きましたよ」
「ありがとう」
ソマリから小さな箱を受け取り、箱を開くとそこに納まっていたのはネックレスだ。
先日の夜会で男性からもらった石をネックレスにしてもらった。
「美しいですわね。おつけしますわ」
ソマリからつけてもらい、鏡で確認する。
「よくお似合いですわ」
「ありがとう」
ハーディスは自分の胸元で輝く赤い石を見つめる。
正直、似合っているのか分からないが、胸元にあるこの石が自分を守ってくれているように感じる。
「今日はそちらでよろしいですか?」
「えぇ」
ハーディスは他の宝石箱に視線を落とす。
大きな宝石箱にはもっと沢山のアクセサリーが入っていた。
ほとんどがお母様の形見でしたのに……。
自分が買い与えられたものはほとんどなく、母が亡くなる前にハーディスに譲ってくれたものだ。
しかし、母の形見を独り占めしていると言われ、ほとんどアマーリアに持って行かれてしまった。
気付けば一つ、また一つと姿を消す宝石達は気が付けばアマーリアが身に着けている。
お父様や色んな男性から沢山宝石やドレスを贈られているというのに。
それでもハーディスが持っているものを欲しがるのだから困ったものだ。
しかし、この赤い石だけは渡したくない。
常に身に着けられるようにネックレスにしておりて正解ですね。
「いつ鼠が入るとも限らないですしね」
『噛み殺してもいいぞ』
『あぁ、それは名案だ』
『鼠なんて美味しくないわ』
口々に愛犬達は言う。
可愛い見た目とは裏腹に過激な子達だ。
「殺しては駄目ですよ」
そう言えば愛犬達は不服そうな声を漏らす。
「お嬢様、お言葉ではございますが、アマーリア様やノバン様にはもっときつく言ってやってもいいのではないですか? 私は悔しくて悔しくて」
そう言ってハンカチを噛むソマリにハーディスは苦笑する。
言ったところで無駄だということは分かっている。
アマーリアの魅了の力は強く、何を言っても周りは彼女の味方をするからだ。
「それに……旦那様に本当のことをお伝えしては如何ですか? そうすればきっと…………」
ソマリの言わんとしていることを察し、ハーディスは首を横に振る。
「良いのよ、今更でしょう。それよりソマリ」
ハーディスは引き出しから一枚の封筒を差し出す。
「貴女はもう少しで退職が決まっているけど、もしも退職前に追い出されるようなことになったり、ここを辞めたくなったらこれを持って行って」
それは貴族の屋敷で働けるように書いた紹介状である。
封筒を留めているのはファンコット家印だ。
「そんな、お嬢様!」
慌てて封筒を突き返そうとするソマリを手で制する。
「もしもの時の為にね。貴女にはとっても世話になったわ。他の使用人達は私の元を離れてしまったけど、貴女だけは残ってくれた」
ハーディスの身の回りを世話してくれていたのはほとんどが母の使用人達だった。 母が亡くなると彼女達はほとんどがアマーリエの元へ行ってしまった。
それでもソマリだけは変わらずハーディスの側にいてくれたのだ。
ソマリがいてくれたからハーディスは孤独ではなかった。
「ありがとう、ソマリ」
震えるソマリの手を包み込み、感謝の言葉を送る。
「ハーディスお嬢様っ……」
ぼろぼろと涙を零すソマリにハーディスは微笑む。
「さぁ、涙を拭いて。喉が渇いてしまったの。お茶を淹れてくれる?」
ハーディスの言葉にソマリは頷き、部屋を出た。
「今日はこちらをお召しになっては如何でしょうか?」
メイドに勧められたのは先日謎の人物から贈られたネックレスだ。
大粒の青いサファイアが一粒と細かい細工のあるもので高価なものであると一目で分かる。
正直、今着ているドレスとは合わない気もするが、高級品を身に付けるのは悪くない。
「たまにはあまり身に付けない色味のものも良いわよね」
そう思い、サファイアのネックレスを首に掛けて部屋を出る。
今日はお茶会に招かれている。
そこでみんなに自慢して、男性達を煽ってみようかしら。
財力を示すためにみんなが自分に宝石を贈るだろうと予想すると面白くて笑ってしまう。
アマーリアは廊下に出ると中庭でお茶を飲みながら本を読む姉の姿を見つけた。
いつもと同じドレスは母のお下がりで地味な色味が肌をすくませて見える。
近くで見ればあちこちが解れて生地が薄くなっていてみすぼらしい。
そんな姉を鼻で笑い、新しいドレスで目の前を通るのがアマーリアは好きだった。最高の優越感に何度やっても胸が高揚する。
挨拶の一つでもしてあげなくちゃ。
そんな風に思っていると、ハーディスの胸に輝く何かが見えた。
燃えるように赤色の宝石が姉の胸でキラキラと輝いている。
アマーリアは思わず、窓から外を食い入るように覗き込んだ。
まだあんなに素敵な宝石が残っていたの?
母の形見である宝石で目ぼしい物は全てアマーリアが奪った。
姉の宝石箱の中には時代遅れのデザインか、宝石としてはあまり価値のないようなものしか残っていない。
あれだけどこかに隠していたのかしら?
アマーリアは悔しくて無意識に爪を噛む。
あんな素敵な宝石、お姉様には似合わないわ。
私の方がきっと似合う。
どうせ、盗っても文句も言ってこない。
最初のうちは自分の物がなくなる度に怒りを顕わにした姉だが、その度に父やノバン、屋敷の者達を味方に付けて姉の物を奪ってきた。
次第に文句を言うことも諦めて何も言わなくなった。
きっと今回もいつもと同じだ。
「ちょっと」
アマーリアは側仕えのメイドに耳打ちすればメイドは快く頷く。
「お姉様には似合わなくてよ」
姉の首に掛かるネックレスを見つめてアマーリアはほくそ笑んだ。