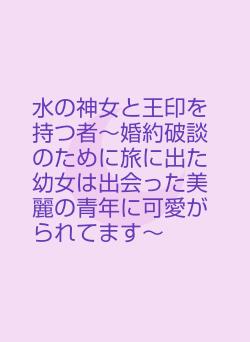仕事を一つ片付け、ようやく一息つこうかというタイミングで執務室に乗り込んできたのは母、クリスティーヌだった。
「ゼノ!」
「何ですか、騒々しい」
子供が面白いものを見つけた時のように興奮気味で王妃とは思えない荒っぽさで入室してきた。
『淑女の鏡』や『国母』などと言われているが、『永遠の十歳』と言われた方がまだしっくりくるような子供っぽい人なのだ。
「遂に見つけたわ!」
「何をですか?」
こういう時の母はろくなことを言わない。
適当に相槌を打って適当にやり過ごすのが一番だ。
「貴女の結婚相手よ!」
何を言うのかと思えば。
ゼルディノは溜息をつく。
「それよりも、怪我はないのですか? 酷い事故に遭ったと聞きましたが」
自分が王妃である自覚がどうも足りないこの人は大した護衛も付けずに年季の入った馬車に乗り、王都の人々の暮らしの眺めて回るのが好きなのだ。
そうして時々、事件や事故に巻き込まれては王やゼルディノを困らせる。
「酷い事故に遭ったのを知っておきながら見舞いにも来ないのね。薄情な息子ですこと」
ハンカチで目元を押さえるふりをする母を見れば元気そのものである。
大体、自分から事故に遭った、怪我をした、風邪を引いて具合が悪いと知らせてくる時は大抵、大したことないのだ。
何も知らせて来ない時ほど重症で、それを隠したがるのが母だ。
今回も母の付き人がいつもと同じ様子で報告に来たので大したことないと踏んでいたが案の定、ピンピンしている。
むしろいつもより元気なくらいだ。
慢性の腰痛はどうした。
「聞きなさい、ゼノ。貴方の結婚相手は彼女しかいないわ。物凄い聖力を持っているのよ! 彼女なら貴方が多少無理に抱いても壊れることはないわ!」
「言葉を選んでくれない?」
母親のストレートな言葉にゼルディノは引き気味で言う。
「昼間、馬車に乗っていたら馬鹿みたいなスピードで走る馬車がぶつかってきて護衛が大怪我をしたのよ。肋骨が折れて内臓を刺して、膝の皿が粉砕される酷い怪我だったのよ。私も、侍女も大したことはなかったけど怪我をしたわ」
護衛の騎士は正直、もう助からないかと思ったとクリスティーヌは語る。
「そこに居合わせた女性が護衛の怪我をあっと言う間に治しちゃったのよ! 勿論、私と侍女の怪我もよ!」
鼻息荒めでクリスティーヌはその時の様子を語る。
「そんな酷い怪我を? あっと言う間に?」
俄かに信じられないが、ゼルディノは思い当たる人物が一人だけいた。
「その女性の名前は?」
「分からないわ」
「は?」
聞き間違いだろうか。
名前も分からない女性を息子の結婚相手に勧める気か、この人は。
「少し目を離したらいなくなってたのよ。お礼もちゃんと言えなかったわ」
クリスティーヌは心底悔しそうに言う。
ゼルディノは母の証言からへラードの屋敷で出会った女性が逃げるように去ろうとする姿を思い出した。
「その女性はどんな人でした?」
「美人よ!」
抽象的過ぎる。
聞きたいのはもっと具体的な特徴だ。
「プラチナブロンドの美しい髪に、目の色は緑色だったわ。色白で歳も貴方と同じぐらい。それに美しいだけじゃないわ。男に立ち向かう度胸もあるのよ!」
そこまで言われてゼルディノは確信した。
きっと彼女だ。
プラチナブロンドに緑の目はそんなに多くはない。
それに骨や臓器の損傷をすぐさま修復できるほどの聖力を持つ者は国中探してもほとんどいない。
そしてお礼の言葉も受け取らずにその場から消えるという行動も、あの夜の彼女と重なる。
ゼルディノは引き出しの中に入っていた手紙を取り出す。
ファンコット家に宛てた手紙の返事だ。
娘、アマーリアからの手紙には『早く会いたい』という旨が綴られている。
正直、自分の中の彼女と手紙から受ける彼女の印象がかなり食い違っているのが気掛かりだった。
男をその気にさせるような、駆け引きを楽しむような文面にゼルディノは首を傾げる。
自分の中の彼女は素直にお礼と遠慮がちな言葉を並べた手紙を書きそうな感じがした。
まぁ、手紙だけじゃ人柄は推し量れない。
喋ったのも一度きりだ。
「その女性に心当たりがあるから、近々会いに行くよ」
「連れてきなさいな」
「そんなことをしたら騒ぎになるでしょ」
「もう騒ぎになっても良い年なのよ」
目をキラキラ、いや、血走らせて母クリスティーヌはゼルディノに迫る。
強い聖力を持って生まれたが故に、結婚相手に困っていたのも事実だ。
年が離れすぎていても困るし、かといって普通の人間や弱い天使や神の転生者でも相手が死ぬ恐れがある。
故に嫁取りに母は必死だ。
「自分の結婚相手くらい、自分でどうにかするよ」
ゼルディノはそう言ってまだまだ話足りない様子の母を執務室から追い出した。
ハーディスはあの騒ぎの中をひっそりと逃げ出し、愛犬達の待つ家に戻った。
まさか、王妃様とは思いませんでしたね……。
思わず逃げてきてしまったが、悪いことをしたわけではないので咎められることはないだろう。
『王妃に恩を売らなくて良かったのか?』
「別に恩を売るようなことではないわ。それに、御者をあんなに心配されている王妃様の人柄に感動したの」
従者達や仕える者に横柄な貴人は多い。
だが、王妃は自分が怪我をしているのにも関わらず、真っ先に御者の心配をしてハーディスに医者を呼ぶように頼んだのだ。
命令ではなく、お願いされたのだ。
「王妃様はとても素敵な方だったわ」
そんな方の助けになれたことはハーディスにとって喜ばしいことである。
『それは良いけど、仕事はどう?』
「飲食店の求人があったから、面接を受けてみようと思うの」
『飲食店? 大丈夫? 変な輩に絡まれないかしら?』
「大丈夫だと思うわ。それに、考えすぎると何もできないもの」
心配してくれるフフにハーディスは言う。
不安もあるが、考え込んでいても仕方がない。
頑張ろうと心に決め、ハーディスは愛犬達とお風呂に入り、疲れた身体を休ませた。
「ゼノ!」
「何ですか、騒々しい」
子供が面白いものを見つけた時のように興奮気味で王妃とは思えない荒っぽさで入室してきた。
『淑女の鏡』や『国母』などと言われているが、『永遠の十歳』と言われた方がまだしっくりくるような子供っぽい人なのだ。
「遂に見つけたわ!」
「何をですか?」
こういう時の母はろくなことを言わない。
適当に相槌を打って適当にやり過ごすのが一番だ。
「貴女の結婚相手よ!」
何を言うのかと思えば。
ゼルディノは溜息をつく。
「それよりも、怪我はないのですか? 酷い事故に遭ったと聞きましたが」
自分が王妃である自覚がどうも足りないこの人は大した護衛も付けずに年季の入った馬車に乗り、王都の人々の暮らしの眺めて回るのが好きなのだ。
そうして時々、事件や事故に巻き込まれては王やゼルディノを困らせる。
「酷い事故に遭ったのを知っておきながら見舞いにも来ないのね。薄情な息子ですこと」
ハンカチで目元を押さえるふりをする母を見れば元気そのものである。
大体、自分から事故に遭った、怪我をした、風邪を引いて具合が悪いと知らせてくる時は大抵、大したことないのだ。
何も知らせて来ない時ほど重症で、それを隠したがるのが母だ。
今回も母の付き人がいつもと同じ様子で報告に来たので大したことないと踏んでいたが案の定、ピンピンしている。
むしろいつもより元気なくらいだ。
慢性の腰痛はどうした。
「聞きなさい、ゼノ。貴方の結婚相手は彼女しかいないわ。物凄い聖力を持っているのよ! 彼女なら貴方が多少無理に抱いても壊れることはないわ!」
「言葉を選んでくれない?」
母親のストレートな言葉にゼルディノは引き気味で言う。
「昼間、馬車に乗っていたら馬鹿みたいなスピードで走る馬車がぶつかってきて護衛が大怪我をしたのよ。肋骨が折れて内臓を刺して、膝の皿が粉砕される酷い怪我だったのよ。私も、侍女も大したことはなかったけど怪我をしたわ」
護衛の騎士は正直、もう助からないかと思ったとクリスティーヌは語る。
「そこに居合わせた女性が護衛の怪我をあっと言う間に治しちゃったのよ! 勿論、私と侍女の怪我もよ!」
鼻息荒めでクリスティーヌはその時の様子を語る。
「そんな酷い怪我を? あっと言う間に?」
俄かに信じられないが、ゼルディノは思い当たる人物が一人だけいた。
「その女性の名前は?」
「分からないわ」
「は?」
聞き間違いだろうか。
名前も分からない女性を息子の結婚相手に勧める気か、この人は。
「少し目を離したらいなくなってたのよ。お礼もちゃんと言えなかったわ」
クリスティーヌは心底悔しそうに言う。
ゼルディノは母の証言からへラードの屋敷で出会った女性が逃げるように去ろうとする姿を思い出した。
「その女性はどんな人でした?」
「美人よ!」
抽象的過ぎる。
聞きたいのはもっと具体的な特徴だ。
「プラチナブロンドの美しい髪に、目の色は緑色だったわ。色白で歳も貴方と同じぐらい。それに美しいだけじゃないわ。男に立ち向かう度胸もあるのよ!」
そこまで言われてゼルディノは確信した。
きっと彼女だ。
プラチナブロンドに緑の目はそんなに多くはない。
それに骨や臓器の損傷をすぐさま修復できるほどの聖力を持つ者は国中探してもほとんどいない。
そしてお礼の言葉も受け取らずにその場から消えるという行動も、あの夜の彼女と重なる。
ゼルディノは引き出しの中に入っていた手紙を取り出す。
ファンコット家に宛てた手紙の返事だ。
娘、アマーリアからの手紙には『早く会いたい』という旨が綴られている。
正直、自分の中の彼女と手紙から受ける彼女の印象がかなり食い違っているのが気掛かりだった。
男をその気にさせるような、駆け引きを楽しむような文面にゼルディノは首を傾げる。
自分の中の彼女は素直にお礼と遠慮がちな言葉を並べた手紙を書きそうな感じがした。
まぁ、手紙だけじゃ人柄は推し量れない。
喋ったのも一度きりだ。
「その女性に心当たりがあるから、近々会いに行くよ」
「連れてきなさいな」
「そんなことをしたら騒ぎになるでしょ」
「もう騒ぎになっても良い年なのよ」
目をキラキラ、いや、血走らせて母クリスティーヌはゼルディノに迫る。
強い聖力を持って生まれたが故に、結婚相手に困っていたのも事実だ。
年が離れすぎていても困るし、かといって普通の人間や弱い天使や神の転生者でも相手が死ぬ恐れがある。
故に嫁取りに母は必死だ。
「自分の結婚相手くらい、自分でどうにかするよ」
ゼルディノはそう言ってまだまだ話足りない様子の母を執務室から追い出した。
ハーディスはあの騒ぎの中をひっそりと逃げ出し、愛犬達の待つ家に戻った。
まさか、王妃様とは思いませんでしたね……。
思わず逃げてきてしまったが、悪いことをしたわけではないので咎められることはないだろう。
『王妃に恩を売らなくて良かったのか?』
「別に恩を売るようなことではないわ。それに、御者をあんなに心配されている王妃様の人柄に感動したの」
従者達や仕える者に横柄な貴人は多い。
だが、王妃は自分が怪我をしているのにも関わらず、真っ先に御者の心配をしてハーディスに医者を呼ぶように頼んだのだ。
命令ではなく、お願いされたのだ。
「王妃様はとても素敵な方だったわ」
そんな方の助けになれたことはハーディスにとって喜ばしいことである。
『それは良いけど、仕事はどう?』
「飲食店の求人があったから、面接を受けてみようと思うの」
『飲食店? 大丈夫? 変な輩に絡まれないかしら?』
「大丈夫だと思うわ。それに、考えすぎると何もできないもの」
心配してくれるフフにハーディスは言う。
不安もあるが、考え込んでいても仕方がない。
頑張ろうと心に決め、ハーディスは愛犬達とお風呂に入り、疲れた身体を休ませた。