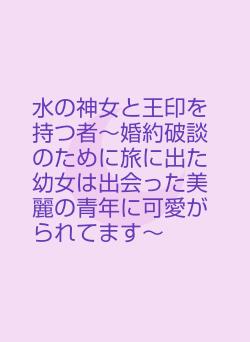ハーディスは久しぶりに清々しい気分で目を覚ました。
肩の荷が降りたというか、身体が軽い気がする。
ハーディスは洗面台で顔を洗い、身支度を整え出掛ける準備をした。
「就職案内所に行ってくるわ。ついでに買い物もしてくるわね」
愛犬達は同行を求めたがハーディスは三匹に留守番を頼み、別荘を出た。
就職案内所には多くの人が張り出された求人票を眺めている。
色んな仕事があるのね。
多いのは飲食店関係、少ないのは医療関係だ。
私の力なら医療関係でも使えそうですけど……。
特に専門的な勉強をしたわけでもなく、特別な資格もないハーディスは書類審査で落とされてしまう。
ハーディスは受付で相談し、優しそうな受付の女性に勧められた飲食店の求人を受け取る。
面接を希望するならまた後日、ここに来て欲しいと言われた。
買い物がてら、お店の前を通ってみようかしら。
条件が良い働き口はすぐになくなってしまう。
何でも初めてのことですし、問題なさそうな場所であればすぐにでも面接を申し込んだ方が良いかもしれませんね。
もらった地図を見ながら目的の飲食店を探した。
すると進行方向から大きな荷馬車がこちらに向かって走ってくる。
人通りが多い場所だとうのにかなり速度を出しており、行き交う人々が危なげな視線を向けていた。
危ないですわね。
そんなに急いでどこへ向かうというのでしょうか。
ハーディスは再び地図に視線を落とし、この辺りにあるらしい飲食店を探した。
あの、赤い看板のお店だわ。
目当てのお店を見つけたと思ったその時だ。
ドガアンとけたたましい音が街中に響いた。
あまりの音の大きさに辺りは騒然としていた。
どうやら先ほどの猛スピードで走っていた馬車が対向車と接触し、相手の馬車が転倒したらしい。
「何てことなの⁉」
ハーディスはすぐに馬車へ駆け寄る。
馬車は横転し、御者は道に放り出されていた。
道に倒れる御者を道行く人が助け、別の人が馬車の中にいる人に声を掛けていた。
「大丈夫ですか⁉」
若い御者は全身を強打し、痛みに苦しみながらもハーディスに言う。
「中の……中にいらっしゃる方はご無事ですか……?」
「今、別の方が対応していますわ。さぁ、貴方は膝をよく見せて下さい」
ハーディスは御者の足を確かめると膝の皿が割れていた。
「酷いわ」
それだけでなく、腹部から出血がある。肋骨が折れて内臓に刺さったのだ。痛みで意識が朦朧としているようで今にも目を閉じてしまいそうだ。
「おい、しっかりするんだ、兄ちゃん!」
「誰か! 手を貸してくれ!」
「待ってください! 動かしてはいけません!」
御者を動かそうとする男性達をハーディスは止める。
「しかしこのままここに寝せておくわけにもいかないだろ」
それはその通りだ。
だが下手に動かせば余計に折れた骨が臓器を傷付けて出血が多くなってしまう。
「ルマン!」
女性の声がして振り返ると馬車の中から助け出された中年女性がふらつきながらこちらに向かって歩いてくる。
「奥様、奥様もお怪我をしておりますのに」
奥様と呼ばれた女性に付き添い、もう一人女性が歩み寄る。
「私の怪我など大したことはないわ」
女性は凛とした声で言い切る。
自分の怪我よりもルマンと呼ばれた御者の男性を心配していた。
「おく……さまっ……もうし、わけ……ありませ…………ん」
「私は無事よ、それよりも自分の心配をなさいな」
奥様と呼ばれる女性は苦しそうに言葉を発するルマンの手を握り、強い口調で述べた。
大丈夫だと言いながらもその女性は左の腕を痛めたようで左腕を庇うようにしていた。
「貴女、お願い、医者を呼んできて。このままでは彼が死んでしまうわ」
品のある面立ちが涙に濡れ、ハーディスに懇願する。
あまり目立ちたくはないが、人の命が掛かっているのだ。
躊躇う必要などありませんわね。
私はもう何をしても自由なのですから。
ハーディスはルマンの身体に優しく触れた。
意識を集中させて、患部にじんわりと力を注ぎ込む。
白い光が溢れ、腹部と膝を中心に淡い光が取り込まれていく。
「これは……」
その様子を見て女性や町の人々が目を見開く。
そして光が消える頃、ルマンの出血は止まり、粉砕された膝も元通りに戻っていた。
「あ……あれ?」
「身体はどうですか?」
ハーディスの言葉にルマンは立ち上がり、飛んだり、膝を曲げたり、身体を大きく曲げ伸ばす。
「先ほどの痛みが嘘のようです」
信じられないというようにルマンは言う。
ハーディスはその言葉に頷く。
「奥様、それにそちらの貴女も」
ハーディスは自分の手を握るように二人に言う。
「お二人も怪我をしていますね」
二人の手を握り、同じように力を注げば、二人は軽やかな表情を見せる。
あれだけ強い衝撃を受けたのだから、何ともないわけがない。
「お二人共、如何ですか?」
「怪我どころか……慢性の腰痛すら感じないわ」
「私もです、奥様。ここ最近痛かった膝の痛みもなくなりました」
感嘆の声を上げる二人にハーディスは安堵する。
「おいっ! どうしてくれるんだ!」
馬車の方から怒号が聞こえてくる。
スピードを出してぶつかった方の馬車の主らしい。
「おかげで積み荷が滅茶苦茶だ! 一体どうしてくれるんだ!」
小太りの男は唾をまき散らしながら怒鳴る。
自分勝手な言い分にハーディスは眉を顰めた。
自分がスピードを出し過ぎたのが事故の大きな原因だ。
ゆっくり走行していればすれ違い際の接触など起こらなかっただろう。
もしかしたら馬車同士ではなく、人が巻き込まれたかもしれないのだ。
男の言葉に町の人達も怒りを滲ませている。
「自分勝手が過ぎるのではないですかっ⁉」
あまりの勝手な言い分にハーディスは我慢できずに声を上げる。
「ここは沢山の人達の往来がある場所です。それに配慮するのは当然のこと。それなのに、貴方達は見ている者がゾッとする速度で走っていた。このご婦人達と同じくらいの速度であればこんな事故は起きなかったのですよ。自分達が事故を引き起こして怪我人を出しておきながら彼らに対しての謝罪も救護もそれらの配慮もせず、自分の荷の心配ですか⁉ 人が死んでいたかもしれないのですよ⁉」
ハーディスは小太りの男を睨んで怒鳴った。
自分がこの場にいたから良かったものの、そうでなければルマンは死んでいたかもしれない。
それほど大きな怪我だった。
人に大怪我を負わせておきながら自分本位の発言しかしない。
縁を切ったはずの父や元婚約者、妹を思い出してムカムカしてしまいます。
「何だ、貴様は! この俺が誰だか分かって口を利いているんだろうな⁉」
生憎ですが、存じ上げません。
この王都で沢山の夜会やお茶会に形だけではあるがそれなりに数はこなしてきたハーディスだ。
失礼のないように顔と名前はそれなりに記憶している。
しかし、こんな小太りの偉そうな男に見覚えはない。
それをそのまま伝えようとした時、男とハーディスの間に誰かが割って入り込む。
「貴方こそ、この私が誰だか知っていて口を利いているのですか?」
はっきりと通る声が喧騒を裂く。
凛とした美しい立ち姿は気品と威厳を感じずにはいられない。
その圧倒的な存在感に男はたじろぐ。
「その荷馬車、ルベナスク商会のものね」
ルベナスク商会とはこの王都でも幅を利かせている商会の一つだ。
「この私、クリスティーヌ・ゴッドファクトはこの件についてルベナスク商会に強く抗議します」
その名を聞き、男は震え上がった。
町の人々も平伏する姿勢を見せる。
今に見てろよ、と言わんばかりの鋭い眼光で商会の男を威圧する女性は王妃様でした。
肩の荷が降りたというか、身体が軽い気がする。
ハーディスは洗面台で顔を洗い、身支度を整え出掛ける準備をした。
「就職案内所に行ってくるわ。ついでに買い物もしてくるわね」
愛犬達は同行を求めたがハーディスは三匹に留守番を頼み、別荘を出た。
就職案内所には多くの人が張り出された求人票を眺めている。
色んな仕事があるのね。
多いのは飲食店関係、少ないのは医療関係だ。
私の力なら医療関係でも使えそうですけど……。
特に専門的な勉強をしたわけでもなく、特別な資格もないハーディスは書類審査で落とされてしまう。
ハーディスは受付で相談し、優しそうな受付の女性に勧められた飲食店の求人を受け取る。
面接を希望するならまた後日、ここに来て欲しいと言われた。
買い物がてら、お店の前を通ってみようかしら。
条件が良い働き口はすぐになくなってしまう。
何でも初めてのことですし、問題なさそうな場所であればすぐにでも面接を申し込んだ方が良いかもしれませんね。
もらった地図を見ながら目的の飲食店を探した。
すると進行方向から大きな荷馬車がこちらに向かって走ってくる。
人通りが多い場所だとうのにかなり速度を出しており、行き交う人々が危なげな視線を向けていた。
危ないですわね。
そんなに急いでどこへ向かうというのでしょうか。
ハーディスは再び地図に視線を落とし、この辺りにあるらしい飲食店を探した。
あの、赤い看板のお店だわ。
目当てのお店を見つけたと思ったその時だ。
ドガアンとけたたましい音が街中に響いた。
あまりの音の大きさに辺りは騒然としていた。
どうやら先ほどの猛スピードで走っていた馬車が対向車と接触し、相手の馬車が転倒したらしい。
「何てことなの⁉」
ハーディスはすぐに馬車へ駆け寄る。
馬車は横転し、御者は道に放り出されていた。
道に倒れる御者を道行く人が助け、別の人が馬車の中にいる人に声を掛けていた。
「大丈夫ですか⁉」
若い御者は全身を強打し、痛みに苦しみながらもハーディスに言う。
「中の……中にいらっしゃる方はご無事ですか……?」
「今、別の方が対応していますわ。さぁ、貴方は膝をよく見せて下さい」
ハーディスは御者の足を確かめると膝の皿が割れていた。
「酷いわ」
それだけでなく、腹部から出血がある。肋骨が折れて内臓に刺さったのだ。痛みで意識が朦朧としているようで今にも目を閉じてしまいそうだ。
「おい、しっかりするんだ、兄ちゃん!」
「誰か! 手を貸してくれ!」
「待ってください! 動かしてはいけません!」
御者を動かそうとする男性達をハーディスは止める。
「しかしこのままここに寝せておくわけにもいかないだろ」
それはその通りだ。
だが下手に動かせば余計に折れた骨が臓器を傷付けて出血が多くなってしまう。
「ルマン!」
女性の声がして振り返ると馬車の中から助け出された中年女性がふらつきながらこちらに向かって歩いてくる。
「奥様、奥様もお怪我をしておりますのに」
奥様と呼ばれた女性に付き添い、もう一人女性が歩み寄る。
「私の怪我など大したことはないわ」
女性は凛とした声で言い切る。
自分の怪我よりもルマンと呼ばれた御者の男性を心配していた。
「おく……さまっ……もうし、わけ……ありませ…………ん」
「私は無事よ、それよりも自分の心配をなさいな」
奥様と呼ばれる女性は苦しそうに言葉を発するルマンの手を握り、強い口調で述べた。
大丈夫だと言いながらもその女性は左の腕を痛めたようで左腕を庇うようにしていた。
「貴女、お願い、医者を呼んできて。このままでは彼が死んでしまうわ」
品のある面立ちが涙に濡れ、ハーディスに懇願する。
あまり目立ちたくはないが、人の命が掛かっているのだ。
躊躇う必要などありませんわね。
私はもう何をしても自由なのですから。
ハーディスはルマンの身体に優しく触れた。
意識を集中させて、患部にじんわりと力を注ぎ込む。
白い光が溢れ、腹部と膝を中心に淡い光が取り込まれていく。
「これは……」
その様子を見て女性や町の人々が目を見開く。
そして光が消える頃、ルマンの出血は止まり、粉砕された膝も元通りに戻っていた。
「あ……あれ?」
「身体はどうですか?」
ハーディスの言葉にルマンは立ち上がり、飛んだり、膝を曲げたり、身体を大きく曲げ伸ばす。
「先ほどの痛みが嘘のようです」
信じられないというようにルマンは言う。
ハーディスはその言葉に頷く。
「奥様、それにそちらの貴女も」
ハーディスは自分の手を握るように二人に言う。
「お二人も怪我をしていますね」
二人の手を握り、同じように力を注げば、二人は軽やかな表情を見せる。
あれだけ強い衝撃を受けたのだから、何ともないわけがない。
「お二人共、如何ですか?」
「怪我どころか……慢性の腰痛すら感じないわ」
「私もです、奥様。ここ最近痛かった膝の痛みもなくなりました」
感嘆の声を上げる二人にハーディスは安堵する。
「おいっ! どうしてくれるんだ!」
馬車の方から怒号が聞こえてくる。
スピードを出してぶつかった方の馬車の主らしい。
「おかげで積み荷が滅茶苦茶だ! 一体どうしてくれるんだ!」
小太りの男は唾をまき散らしながら怒鳴る。
自分勝手な言い分にハーディスは眉を顰めた。
自分がスピードを出し過ぎたのが事故の大きな原因だ。
ゆっくり走行していればすれ違い際の接触など起こらなかっただろう。
もしかしたら馬車同士ではなく、人が巻き込まれたかもしれないのだ。
男の言葉に町の人達も怒りを滲ませている。
「自分勝手が過ぎるのではないですかっ⁉」
あまりの勝手な言い分にハーディスは我慢できずに声を上げる。
「ここは沢山の人達の往来がある場所です。それに配慮するのは当然のこと。それなのに、貴方達は見ている者がゾッとする速度で走っていた。このご婦人達と同じくらいの速度であればこんな事故は起きなかったのですよ。自分達が事故を引き起こして怪我人を出しておきながら彼らに対しての謝罪も救護もそれらの配慮もせず、自分の荷の心配ですか⁉ 人が死んでいたかもしれないのですよ⁉」
ハーディスは小太りの男を睨んで怒鳴った。
自分がこの場にいたから良かったものの、そうでなければルマンは死んでいたかもしれない。
それほど大きな怪我だった。
人に大怪我を負わせておきながら自分本位の発言しかしない。
縁を切ったはずの父や元婚約者、妹を思い出してムカムカしてしまいます。
「何だ、貴様は! この俺が誰だか分かって口を利いているんだろうな⁉」
生憎ですが、存じ上げません。
この王都で沢山の夜会やお茶会に形だけではあるがそれなりに数はこなしてきたハーディスだ。
失礼のないように顔と名前はそれなりに記憶している。
しかし、こんな小太りの偉そうな男に見覚えはない。
それをそのまま伝えようとした時、男とハーディスの間に誰かが割って入り込む。
「貴方こそ、この私が誰だか知っていて口を利いているのですか?」
はっきりと通る声が喧騒を裂く。
凛とした美しい立ち姿は気品と威厳を感じずにはいられない。
その圧倒的な存在感に男はたじろぐ。
「その荷馬車、ルベナスク商会のものね」
ルベナスク商会とはこの王都でも幅を利かせている商会の一つだ。
「この私、クリスティーヌ・ゴッドファクトはこの件についてルベナスク商会に強く抗議します」
その名を聞き、男は震え上がった。
町の人々も平伏する姿勢を見せる。
今に見てろよ、と言わんばかりの鋭い眼光で商会の男を威圧する女性は王妃様でした。