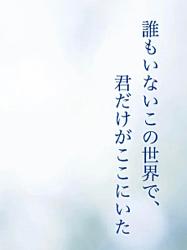「葉月ー。こっち来ないの?」
お昼休み、ぼんやりとお弁当箱を眺めているとどこからか声が聞こえてきた。
呼びかけたのは、黒板の近くの席に集まっている女の子二人組。お弁当箱を片手に、こちらに向かって手を振っている。
声をかけたのはもちろん私じゃなくて、私の前の席の井上さん。下の名前が葉月、だから。
いつもは三人グループでご飯を食べているのに、今日の井上さんは一人で自分の席に座ったままだった。
「んー、いいや。今日は一人で食べたい気分なの」
そう明るく返しながら、井上さんはまた箸を動かし始める。
井上さんは自由気ままな人で、そうしてたまに一人で行動することがあった。
普通なら、お昼休みを一人で過ごすなんて周りの目が気になるはずなのに。井上さんはなんとも感じないのだろうか。私としても、お昼休みまで彼女が目の前の席にいるとなんだか気になってしまうから、できればあっちに行ってほしかった。
でもそう思いながらも、一人ぼっちのお昼休みに一人ぼっちの仲間が増えたような気がして、少しだけ安心してしまう自分が情けない。
——いつもの教室。いつものお昼休み。
昨日で最後だと思っていたお昼休みが、またこうしてやってきている。そのことに、私はずっと戸惑っていた。
どうして私はここにいるんだろう。
もう二度と、この日常は戻ってこないはずだったのに。
今頃私は、この教室からいなくなっているはずだったのに。いや、この世界からも跡形もなくなくなっていて。……あの快速電車にぶつかって、死んでいる、はずだったのに。
昨日のことを思い出す。
荻原くんに突然告白をされたあと、私は思わず踵を返し、駅を出て逃げてしまった。
どうしたらいいのかわからなかった。あの状況で突然告白してくる荻原くんが理解できなさすぎて、脳がパンクしていたのだと思う。私はしばらくの間、すべてを振り切るように走り続けた。
そして結局、本格的に降り出してきた雨の中、傘も差さずに二駅分を歩いて家に帰った。
家の近くまで来たところでお母さんが私を見つけたのは、荻原くんがあらかじめ学校に連絡を入れておいたおかげだと思う。
『もうっ。携帯に電話しても出ないし、何かあったのかと思ったじゃない。今度学校に行ったら、荻原さんって方にちゃんとお礼言うのよ。体調不良のときは、生徒さんじゃなくて先生に連絡すること!』
おかげで私は今日、何食わぬ顔をして登校している。
学校に行かない——もしくはまたあの駅のホームに立って——という選択肢もあったのかもしれないけれど、すべての〝計画〟が崩れてしまった今、どうしたらいいのかわからなくなっていた。
「葉月ー、明日なっちゃんたちとカラオケ行く話があるんだけど、一緒に行く?」
「あ、行く行くー!」
一人でいたいからと言った井上さんに、二人の女の子が時折遠くから話しかけている。他にも、いつも一緒にいるわけじゃない女の子や、通りすがりの男子なんかも。昼休みが始まってほんの数分のうちに、入れ替わり立ち代わり誰かが井上さんに話しかけていくのを私は後ろからじっと見ていた。
それくらい、井上さんはみんなにとって特別な人だった。
彼女が輪の中にいると、もうすでに室内は明るいのに、天井に小さな太陽を吊るしたみたいにさらに明るくなる。クラスのムードメーカーで、誰とでも仲よく接して相手を楽しませる。井上さんはそんな存在だった。
スマホを眺めながらご飯を食べている彼女の背中を、ぼんやりと見つめた。
〝幼馴染の死を、自分のせいだと思ってる〟
……例えば井上さんが、修ちゃんが亡くなった原因が私のせいだと知ったらどう思うだろう。
井上さんも荻原くんと同じ、高校からこの学校へ編入してきた生徒だ。だから、修ちゃんのことは知らないかもしれないし、噂レベルで聞いたことはあるかもしれない。でも、そんなことは関係ない。まっすぐな井上さんのことだから、私が一人の生徒の死に関わっていると知ったらきっと軽蔑するに違いない。
想像するとやっぱり、怖かった。いつも明るい井上さんの、冷たい視線。
いつか、修ちゃんと私のことが誰かの耳に入ったとしても、どんな言葉も受け止めるつもりだったのに。
なのに、いざそんな状況になった今、動揺している自分がいる。誰にも言わないでほしい、と思っている自分がいる。
誰かに私の秘密を知られることを、死ぬことよりも怖いと思っている。
最低の人間だ。
「相澤さん」
気づくと、井上さんが振り返っていた。
驚いて、思わず背筋が伸びる。
「なっ、なに?」
「なんか、呼んでるみたいだよ」
井上さんがちょいと廊下の方を指し示す。
その指の先。
荻原くんが廊下から、おずおずとこちらを覗いていた。
お昼休み、ぼんやりとお弁当箱を眺めているとどこからか声が聞こえてきた。
呼びかけたのは、黒板の近くの席に集まっている女の子二人組。お弁当箱を片手に、こちらに向かって手を振っている。
声をかけたのはもちろん私じゃなくて、私の前の席の井上さん。下の名前が葉月、だから。
いつもは三人グループでご飯を食べているのに、今日の井上さんは一人で自分の席に座ったままだった。
「んー、いいや。今日は一人で食べたい気分なの」
そう明るく返しながら、井上さんはまた箸を動かし始める。
井上さんは自由気ままな人で、そうしてたまに一人で行動することがあった。
普通なら、お昼休みを一人で過ごすなんて周りの目が気になるはずなのに。井上さんはなんとも感じないのだろうか。私としても、お昼休みまで彼女が目の前の席にいるとなんだか気になってしまうから、できればあっちに行ってほしかった。
でもそう思いながらも、一人ぼっちのお昼休みに一人ぼっちの仲間が増えたような気がして、少しだけ安心してしまう自分が情けない。
——いつもの教室。いつものお昼休み。
昨日で最後だと思っていたお昼休みが、またこうしてやってきている。そのことに、私はずっと戸惑っていた。
どうして私はここにいるんだろう。
もう二度と、この日常は戻ってこないはずだったのに。
今頃私は、この教室からいなくなっているはずだったのに。いや、この世界からも跡形もなくなくなっていて。……あの快速電車にぶつかって、死んでいる、はずだったのに。
昨日のことを思い出す。
荻原くんに突然告白をされたあと、私は思わず踵を返し、駅を出て逃げてしまった。
どうしたらいいのかわからなかった。あの状況で突然告白してくる荻原くんが理解できなさすぎて、脳がパンクしていたのだと思う。私はしばらくの間、すべてを振り切るように走り続けた。
そして結局、本格的に降り出してきた雨の中、傘も差さずに二駅分を歩いて家に帰った。
家の近くまで来たところでお母さんが私を見つけたのは、荻原くんがあらかじめ学校に連絡を入れておいたおかげだと思う。
『もうっ。携帯に電話しても出ないし、何かあったのかと思ったじゃない。今度学校に行ったら、荻原さんって方にちゃんとお礼言うのよ。体調不良のときは、生徒さんじゃなくて先生に連絡すること!』
おかげで私は今日、何食わぬ顔をして登校している。
学校に行かない——もしくはまたあの駅のホームに立って——という選択肢もあったのかもしれないけれど、すべての〝計画〟が崩れてしまった今、どうしたらいいのかわからなくなっていた。
「葉月ー、明日なっちゃんたちとカラオケ行く話があるんだけど、一緒に行く?」
「あ、行く行くー!」
一人でいたいからと言った井上さんに、二人の女の子が時折遠くから話しかけている。他にも、いつも一緒にいるわけじゃない女の子や、通りすがりの男子なんかも。昼休みが始まってほんの数分のうちに、入れ替わり立ち代わり誰かが井上さんに話しかけていくのを私は後ろからじっと見ていた。
それくらい、井上さんはみんなにとって特別な人だった。
彼女が輪の中にいると、もうすでに室内は明るいのに、天井に小さな太陽を吊るしたみたいにさらに明るくなる。クラスのムードメーカーで、誰とでも仲よく接して相手を楽しませる。井上さんはそんな存在だった。
スマホを眺めながらご飯を食べている彼女の背中を、ぼんやりと見つめた。
〝幼馴染の死を、自分のせいだと思ってる〟
……例えば井上さんが、修ちゃんが亡くなった原因が私のせいだと知ったらどう思うだろう。
井上さんも荻原くんと同じ、高校からこの学校へ編入してきた生徒だ。だから、修ちゃんのことは知らないかもしれないし、噂レベルで聞いたことはあるかもしれない。でも、そんなことは関係ない。まっすぐな井上さんのことだから、私が一人の生徒の死に関わっていると知ったらきっと軽蔑するに違いない。
想像するとやっぱり、怖かった。いつも明るい井上さんの、冷たい視線。
いつか、修ちゃんと私のことが誰かの耳に入ったとしても、どんな言葉も受け止めるつもりだったのに。
なのに、いざそんな状況になった今、動揺している自分がいる。誰にも言わないでほしい、と思っている自分がいる。
誰かに私の秘密を知られることを、死ぬことよりも怖いと思っている。
最低の人間だ。
「相澤さん」
気づくと、井上さんが振り返っていた。
驚いて、思わず背筋が伸びる。
「なっ、なに?」
「なんか、呼んでるみたいだよ」
井上さんがちょいと廊下の方を指し示す。
その指の先。
荻原くんが廊下から、おずおずとこちらを覗いていた。