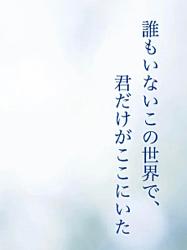「……このままここに飛び込んだら、楽になれるかなぁ」
ふと、透き通るような男性の声が聞こえた。
誰に向けられた言葉かわからず、私はつい、そっと目を開けてしまった。
手が触れてしまいそうなくらいに近い、私の右隣。いつからそこにいたのか、背の高い男の子が立っていた。
ホームには誰もいないというのに、彼はまるで友達のような距離感で私の真横に佇んでいた。
でも、その視線は私を見ているわけではなくて、ただまっすぐに正面の何もない空間へと向けられている。大きな二重の瞳が、まるで雲の向こうにある太陽の光を受け止めているかのようにキラキラと輝いていた。
——誰?
それきり何も話さない彼を、私はまじまじと見つめてしまった。
端正な顔立ち。まるでファッション雑誌に出てくるモデルみたい。初対面の人だというのに、私はその不自然な彼のことを無遠慮に観察していた。
この顔を、知っている気がする……。
けれど思い出せなかった。先ほどまで暗闇の中に沈んでいた頭は、ぼんやりとしていてうまく動かない。
彼はふと私の方を見ると、穏やかな笑みを見せた。
「……なんてさ、思ったことない?」
不意に、質問を投げかけられる。
だけれど、突然のことに言葉を返せなかった。
なんて答えたらいいのかわからない。そもそも、〝ここに飛び込んだら楽になれる、と思ったことがあるか?〟かなんて、見ず知らずの人に投げかけるような質問じゃない。
無視をするべきか、迷う。
すると、彼はまた目の前の虚空へと目を向けた。
「僕は、あるよ。時々ね、全部リセットしたら悩みとか全部なくなって、すっきりするのかなって思うんだ。本当に、たまにだけどね」
その言葉にも何も返せず黙っていると、目の前を電車が通り過ぎた。
橙色の車体が残像となって走り抜けていく。
それはほんの数秒のことで、気づくと電車ははるか線路の向こうへと姿を消していた。その余韻のような冷たい風が、真横に立つ彼の前髪をさらさらと揺らしている。
ぼうっとしていると、やがて彼が口を開いた。
「学校、サボり? 僕も付き合おうかな」
「……え?」
「お昼ご飯、もう食べた? オススメのお店があるんだ。これからどうかな」
いきなり突拍子もないことを言われる。急に現実に戻った気がして、つい一歩、後ずさった。
ナンパ?
動揺しつつ、肩に掛けていた鞄の持ち手をぎゅっと掴んだ。
「……あ、あの。私、体調悪くて、学校を早退してきただけで……。……あまり、人と話す気分になれないので」
そう言い残し、小走りでホームの逆側へと向かった。後尾車両の方へと走り、少ししてから足を止めた。
……オススメのお店、って。
ただの、ご飯の誘いだったの?
こんな、駅のホームで。たまたま周りに人がいなかったからって。理解できない。最初の質問からしてよくわからないし、ちょっと変な人なのかもしれない。
追ってこられたら嫌だな、と思いながらそっと振り返ると、彼は先ほどと変わらず同じ場所に立っていた。
ただ、その視線はいつまでも私に向けられている。気まずくてすぐに目を逸らし、さらにホームの奥へと歩き出した。
その瞬間。
響いてきた声に、足が止まってしまった。
「……君の秘密、よっつめ。本当はつらくてたまらないのに、人に頼ることができない」
はっとして、息が止まった。
——〝君の、秘密〟。
その文脈を、知っている。
今日、何度も見たフレーズ。丸一日悩まされた、短いメッセージの数々。
手のひらにじわりと汗が滲むのを感じながら、私はゆっくりと振り返った。
先ほどの穏やかな表情とは変わって、彼は真剣な顔つきになっていた。
〝本当はみんなと仲よくしたいのに、わざと嫌われるように振舞ってる〟
〝本当は聞いてほしいのに、自分の本当の気持ちを話さない〟
〝本当は笑いたいのに、笑顔の作り方がわからない〟
——本当はつらくてたまらないのに、人に頼ることができない。
あのメールの、続きだ。
「あなた……だったんですか?」
「死んじゃ、だめだよ」
独り言に近い彼の囁きは、小さい声なのに、しっかりとした輪郭を持って私の耳へと届いた。
急速に頭の中が回転し始める。よく見ると、彼のコートの襟元とマフラーの隙間からネクタイが見えていた。同じ学校の制服だ。ネクタイの色を見るに、私と同じ、一年生。
動画が巻き戻っていくように、今日一日のことを思い出していく。
あなたが、私にメールをしていたの?
あなたが、ずっと私のことを見てたっていうの?
なんで? どうして?
疑問が溢れて止まらない。
なのに、私はそれらをすべて無視して、今直前に言われた彼の一言に大声で反論していた。
「私、死のうとなんかしてないので!」
「うそ」
彼はすぐさま言い返すと、つかつかと私のそばへとやってきた。
急に距離を縮められて、思わずひるむ。頭は逃げようと思っているのに体がついてこない。あっという間に目の前までやって来た彼は、おもむろに私の手首を掴んだ。
そして、ホームから離れるように強い力で引っ張られた。
「あ、あの……! 痛い……!」
思いのほか力が強くて、声が出た。
それでも彼は私の腕を離さない。そのまま階段の前まで強引に私を連れてくると、目的を果たしたかのようにようやく力が抜けた。
その手を振り解き、一歩後ずさる。
「へ……変な言いがかりはやめてください。メールも……。……なんなんですか? これ以上つきまとうなら、駅員さん呼んできますから」
掴まれていた手首をさすりながら、彼を避けるように大回りをして階段へと走った。
怖い。やっぱり変な人だった。この人、ストーカーなんだ。
足が震えてつまずきそうになるのをこらえながら、階段を一歩、一歩と上がった。追いかけられたらかなわない。だから振り返らず、全力で走った。改札前まで行けば人はいるし、最悪、何かあったらこの場で叫べばいい。大丈夫、大丈夫と念じながら進む。
すると、後ろからまた彼の声が追いかけてきた。
「——君の、秘密。いつつめ」
まだ、言ってる。
その声を無視して進んだ。今は早く、この場から逃れたい。彼から離れたい。その一心で。
でも、その後の彼の言葉が私の足をぴたりと止めてしまった。
「幼馴染が亡くなってしまったことを、ずっと引きずってる」
階段の中腹、小さな踊り場の上で、私の体は凍りついたように動けなくなった。
その瞬間、私の周りから、彼の声、自分の走る足音、すべての音が消え去った気がした。
そして残された空間に、ぽつ、ぽつと、雨の音が響き始めた。小さく点を打っていく雨音は、やがて塊となって世界を覆う。雨音が私の体を、指先を、冷たく包んでいく。
後ろから、追い討ちをかけるように声が続いた。
「幼馴染の死を、自分のせいだと思ってる。だから、自分は幸せになんかなっちゃいけない……誰とも仲よくならないし、心を開かないし、生きる価値なんかないって、思ってる」
振り返る。
彼は微動だにせず、じっと私の目を見つめていた。
「……なんで」
それを、知ってるの?
声がかすれて、言葉は途中で消えてしまった。
誰にも言ったことはない。
誰も知らない、私の〝秘密〟。
……なのに。
どうして、あなたが、知ってるの?
「誰にも言わないよ」
そう言うと、彼は階段を上ってきた。
コツ、コツというゆっくりとした足音が辺りに響く。体が動かない。植物にでもなってしまったかのように、私の足は階段の中腹に張り付いたままだ。
喉がカラカラで、息をするのも苦しい。
呆然としたまま、私は目の前までやってきた彼の瞳を見つめることしかできなかった。
そしてその瞬間、思い出した。
彼のことを。
D組の、〝萩原蓮〟だ。
四月の初め、クラスの女子たちがしきりに話していた。うちの学校に高校から編入してきたという、噂の男の子。成績優秀で、運動神経もよくて、綺麗な顔。
そしてたしか……なにか、よくない噂があった気がする。
風が吹き、また、彼の前髪をさらりと揺らす。
それをきっかけに、彼は真剣な表情からまた穏やかな笑みを浮かべ始めたかと思うと、おどおどと口を開いた。
「言わないから、さ。……あの。そのかわり……僕と、付き合って、くれませんか」
ふと、透き通るような男性の声が聞こえた。
誰に向けられた言葉かわからず、私はつい、そっと目を開けてしまった。
手が触れてしまいそうなくらいに近い、私の右隣。いつからそこにいたのか、背の高い男の子が立っていた。
ホームには誰もいないというのに、彼はまるで友達のような距離感で私の真横に佇んでいた。
でも、その視線は私を見ているわけではなくて、ただまっすぐに正面の何もない空間へと向けられている。大きな二重の瞳が、まるで雲の向こうにある太陽の光を受け止めているかのようにキラキラと輝いていた。
——誰?
それきり何も話さない彼を、私はまじまじと見つめてしまった。
端正な顔立ち。まるでファッション雑誌に出てくるモデルみたい。初対面の人だというのに、私はその不自然な彼のことを無遠慮に観察していた。
この顔を、知っている気がする……。
けれど思い出せなかった。先ほどまで暗闇の中に沈んでいた頭は、ぼんやりとしていてうまく動かない。
彼はふと私の方を見ると、穏やかな笑みを見せた。
「……なんてさ、思ったことない?」
不意に、質問を投げかけられる。
だけれど、突然のことに言葉を返せなかった。
なんて答えたらいいのかわからない。そもそも、〝ここに飛び込んだら楽になれる、と思ったことがあるか?〟かなんて、見ず知らずの人に投げかけるような質問じゃない。
無視をするべきか、迷う。
すると、彼はまた目の前の虚空へと目を向けた。
「僕は、あるよ。時々ね、全部リセットしたら悩みとか全部なくなって、すっきりするのかなって思うんだ。本当に、たまにだけどね」
その言葉にも何も返せず黙っていると、目の前を電車が通り過ぎた。
橙色の車体が残像となって走り抜けていく。
それはほんの数秒のことで、気づくと電車ははるか線路の向こうへと姿を消していた。その余韻のような冷たい風が、真横に立つ彼の前髪をさらさらと揺らしている。
ぼうっとしていると、やがて彼が口を開いた。
「学校、サボり? 僕も付き合おうかな」
「……え?」
「お昼ご飯、もう食べた? オススメのお店があるんだ。これからどうかな」
いきなり突拍子もないことを言われる。急に現実に戻った気がして、つい一歩、後ずさった。
ナンパ?
動揺しつつ、肩に掛けていた鞄の持ち手をぎゅっと掴んだ。
「……あ、あの。私、体調悪くて、学校を早退してきただけで……。……あまり、人と話す気分になれないので」
そう言い残し、小走りでホームの逆側へと向かった。後尾車両の方へと走り、少ししてから足を止めた。
……オススメのお店、って。
ただの、ご飯の誘いだったの?
こんな、駅のホームで。たまたま周りに人がいなかったからって。理解できない。最初の質問からしてよくわからないし、ちょっと変な人なのかもしれない。
追ってこられたら嫌だな、と思いながらそっと振り返ると、彼は先ほどと変わらず同じ場所に立っていた。
ただ、その視線はいつまでも私に向けられている。気まずくてすぐに目を逸らし、さらにホームの奥へと歩き出した。
その瞬間。
響いてきた声に、足が止まってしまった。
「……君の秘密、よっつめ。本当はつらくてたまらないのに、人に頼ることができない」
はっとして、息が止まった。
——〝君の、秘密〟。
その文脈を、知っている。
今日、何度も見たフレーズ。丸一日悩まされた、短いメッセージの数々。
手のひらにじわりと汗が滲むのを感じながら、私はゆっくりと振り返った。
先ほどの穏やかな表情とは変わって、彼は真剣な顔つきになっていた。
〝本当はみんなと仲よくしたいのに、わざと嫌われるように振舞ってる〟
〝本当は聞いてほしいのに、自分の本当の気持ちを話さない〟
〝本当は笑いたいのに、笑顔の作り方がわからない〟
——本当はつらくてたまらないのに、人に頼ることができない。
あのメールの、続きだ。
「あなた……だったんですか?」
「死んじゃ、だめだよ」
独り言に近い彼の囁きは、小さい声なのに、しっかりとした輪郭を持って私の耳へと届いた。
急速に頭の中が回転し始める。よく見ると、彼のコートの襟元とマフラーの隙間からネクタイが見えていた。同じ学校の制服だ。ネクタイの色を見るに、私と同じ、一年生。
動画が巻き戻っていくように、今日一日のことを思い出していく。
あなたが、私にメールをしていたの?
あなたが、ずっと私のことを見てたっていうの?
なんで? どうして?
疑問が溢れて止まらない。
なのに、私はそれらをすべて無視して、今直前に言われた彼の一言に大声で反論していた。
「私、死のうとなんかしてないので!」
「うそ」
彼はすぐさま言い返すと、つかつかと私のそばへとやってきた。
急に距離を縮められて、思わずひるむ。頭は逃げようと思っているのに体がついてこない。あっという間に目の前までやって来た彼は、おもむろに私の手首を掴んだ。
そして、ホームから離れるように強い力で引っ張られた。
「あ、あの……! 痛い……!」
思いのほか力が強くて、声が出た。
それでも彼は私の腕を離さない。そのまま階段の前まで強引に私を連れてくると、目的を果たしたかのようにようやく力が抜けた。
その手を振り解き、一歩後ずさる。
「へ……変な言いがかりはやめてください。メールも……。……なんなんですか? これ以上つきまとうなら、駅員さん呼んできますから」
掴まれていた手首をさすりながら、彼を避けるように大回りをして階段へと走った。
怖い。やっぱり変な人だった。この人、ストーカーなんだ。
足が震えてつまずきそうになるのをこらえながら、階段を一歩、一歩と上がった。追いかけられたらかなわない。だから振り返らず、全力で走った。改札前まで行けば人はいるし、最悪、何かあったらこの場で叫べばいい。大丈夫、大丈夫と念じながら進む。
すると、後ろからまた彼の声が追いかけてきた。
「——君の、秘密。いつつめ」
まだ、言ってる。
その声を無視して進んだ。今は早く、この場から逃れたい。彼から離れたい。その一心で。
でも、その後の彼の言葉が私の足をぴたりと止めてしまった。
「幼馴染が亡くなってしまったことを、ずっと引きずってる」
階段の中腹、小さな踊り場の上で、私の体は凍りついたように動けなくなった。
その瞬間、私の周りから、彼の声、自分の走る足音、すべての音が消え去った気がした。
そして残された空間に、ぽつ、ぽつと、雨の音が響き始めた。小さく点を打っていく雨音は、やがて塊となって世界を覆う。雨音が私の体を、指先を、冷たく包んでいく。
後ろから、追い討ちをかけるように声が続いた。
「幼馴染の死を、自分のせいだと思ってる。だから、自分は幸せになんかなっちゃいけない……誰とも仲よくならないし、心を開かないし、生きる価値なんかないって、思ってる」
振り返る。
彼は微動だにせず、じっと私の目を見つめていた。
「……なんで」
それを、知ってるの?
声がかすれて、言葉は途中で消えてしまった。
誰にも言ったことはない。
誰も知らない、私の〝秘密〟。
……なのに。
どうして、あなたが、知ってるの?
「誰にも言わないよ」
そう言うと、彼は階段を上ってきた。
コツ、コツというゆっくりとした足音が辺りに響く。体が動かない。植物にでもなってしまったかのように、私の足は階段の中腹に張り付いたままだ。
喉がカラカラで、息をするのも苦しい。
呆然としたまま、私は目の前までやってきた彼の瞳を見つめることしかできなかった。
そしてその瞬間、思い出した。
彼のことを。
D組の、〝萩原蓮〟だ。
四月の初め、クラスの女子たちがしきりに話していた。うちの学校に高校から編入してきたという、噂の男の子。成績優秀で、運動神経もよくて、綺麗な顔。
そしてたしか……なにか、よくない噂があった気がする。
風が吹き、また、彼の前髪をさらりと揺らす。
それをきっかけに、彼は真剣な表情からまた穏やかな笑みを浮かべ始めたかと思うと、おどおどと口を開いた。
「言わないから、さ。……あの。そのかわり……僕と、付き合って、くれませんか」