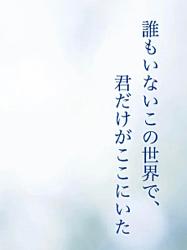「えっと……」
どうしよう。
冷や汗が出る。
違うんだ。
私は今、修ちゃんのことに向き合いたくて。
修ちゃんのことと自分のことに精いっぱいで。
蓮くんと付き合うとか付き合わないとか、とても考えられない。
修ちゃんが亡くなってからの一年間、修ちゃんのことをたくさん考えてきた。そして修ちゃんのところへ行こうと結論付けて、でも蓮くんと出会って、もう一度、今度こそ、考えようと思っているのが今なんだ。
でも……。
そんなこと、言えない。
私が事故に遭わせてしまった幼馴染のことが気になって、今は恋愛のことを考えられないから、なんて……言えない。
左隣から、蓮くんが私をじっと見つめている視線を感じる。
きっと、私が横を向いて蓮くんと目を合わせたら、助け舟を出してくれる。
すぐに蓮くんが変わって、話をしてくれる。ごまかすように、うその話を。
でも……。
それで、いいの?
私……ずっと蓮くんに助けられてばかりで。
ずっと、修ちゃんのことを隠し続けて。
長谷くんはともかく、井上さんはこんな私と仲よくなろうとしてくれてるのに。秘密に秘密を塗りたくって、全部をごまかして、蓮くんに全部頼って……。
それで、いいの……?
ぎゅっと目をつむって、とにかく何かを言葉にしようと覚悟する。
その瞬間、蓮くんが話し出した。
「芽依ちゃんは……」
「あのさ」
蓮くんの言葉が、さらに遮られる。
声を発したのは、長谷くんだった。
その声の大きさに、今度は長谷くんの方に三人の視線が集まる。
私の正面に座っている長谷くんは、背もたれに寄りかかったまま、ぽつりと呟いた。
「……相澤って、なんでそうなの」
鋭い視線が、私を捉えていた。
「煮え切らないっていうか、言いたいことを言わないっていうか。いつもびくびくしてて、なんつーか、壁があるよな」
「……ちょっと。そんなことないよー。私、相澤さんと最近お昼食べることあるけど、ちゃんと喋ってくれるもん。優馬はお昼いつも部室行ってるから知らないだろうけど!」
井上さんがフォローしてくれる。
どうしたらいいのかわからなくて、視線が井上さんと長谷くんの間をうろうろとしてしまう。
「まぁ、昼休みの様子は知らないけど。他の時間の話、だよ」
井上さんの言い分を交わすと、長谷くんは私の方に顔を戻した。
「相澤さ。中学のときはそんなんじゃなかっただろ」
——中学。
思わず、びくりと体が震えた。
「クラスメイトとも話してた。目立つタイプじゃなかったけどさ、暗いってわけでもなかった。普段話さない人ともそれなりに話せてたし。今みたいに、言葉が出てこないことはなかっただろ」
一瞬、しん、と空気が静まり返った。
どくどくと、自分の心臓の音が鳴るのが聞こえる。テーブルの下で強く握った手のひらが、じんわりと湿っていくのを感じた。
長谷くんは私と同じ、中学から高校へとエスカレーターで上がってきた生徒だ。
だから、私の中学の頃のことも多少は知っている。一方で、井上さんと蓮くんは高校から編入してきた生徒だから、中学の頃の私を知らない。
だから、口を挟む余地がない。
「よくは知らないけど、相澤が変わったのって高校に上がった頃からだろ。誰とも話さなくなって、むしろ、話しかけると嫌がるようになった。今もなんか変だよな。前も大人しい方だったけど、今はそのレベルじゃないっていうか」
——言わないで。
修ちゃんの笑顔が、頭に浮かぶ。全校生徒が体育館に集められて、修ちゃんの死を告げられた瞬間の絶望感を思い出す。
体が震えて、止まらない。
お願い。
もう言わないで。
それ以上は、もう……。
「……ずっと、思ってたんだけどさ。……もしかして、相澤って……」
その瞬間、バン、とテーブルに両手をついて、井上さんが立ち上がった。
「ゆ……!」
「長谷くん」
先に止めたのは、蓮くんだった。
蓮くんの方を見ると、たぶん真っ青な顔をしているであろう私とは対照的な、いつもの、穏やかで優しい微笑みを浮かべていた。
「誰にでも、隠しておきたいこととか、言えない気持ちはあるよ」
時が止まる。
静寂に包まれた私たちの空間を、ガヤガヤとした店内の喧騒が割り込んでくる。私たち、今お店の中にいたんだ。その賑やかさを唐突に思い出して、ふと我に返る。
でも、仕切りで隔てられている向こうとこちらでは、まるで違う世界みたいだった。
みんな楽しく食事をしているのに。私たちはいったい、何をしているんだろう。
……いや。
私、は、何をしているんだろう……。
「いや、俺は別に……」
長谷くんが、手を振って何かを言い返そうとする。
でも、私はもう限界だった。
「……ごめんなさい!」
そう言うと、立ち上がって頭を下げた。
「わ、私が優柔不断だから……。うまく喋れないだけなの。ごめんね。せっかく親睦会開いてくれたのに……。今日は、本当に楽しかった。三人の話が聞けて、うれしかった。本当に……ありがとう」
そう言い残すと、体が勝手に鞄を取って駆け出していた。
ハンバーガーを持って歩いてくる人たちをすり抜け、一目散に入り口へと向かう。もうここにいることはできないと、心が叫んでいた。
「芽依ちゃん!」
後ろから蓮くんの声が聞こえたけれど、振り返ることなく私は店を出た。
どうしよう。
冷や汗が出る。
違うんだ。
私は今、修ちゃんのことに向き合いたくて。
修ちゃんのことと自分のことに精いっぱいで。
蓮くんと付き合うとか付き合わないとか、とても考えられない。
修ちゃんが亡くなってからの一年間、修ちゃんのことをたくさん考えてきた。そして修ちゃんのところへ行こうと結論付けて、でも蓮くんと出会って、もう一度、今度こそ、考えようと思っているのが今なんだ。
でも……。
そんなこと、言えない。
私が事故に遭わせてしまった幼馴染のことが気になって、今は恋愛のことを考えられないから、なんて……言えない。
左隣から、蓮くんが私をじっと見つめている視線を感じる。
きっと、私が横を向いて蓮くんと目を合わせたら、助け舟を出してくれる。
すぐに蓮くんが変わって、話をしてくれる。ごまかすように、うその話を。
でも……。
それで、いいの?
私……ずっと蓮くんに助けられてばかりで。
ずっと、修ちゃんのことを隠し続けて。
長谷くんはともかく、井上さんはこんな私と仲よくなろうとしてくれてるのに。秘密に秘密を塗りたくって、全部をごまかして、蓮くんに全部頼って……。
それで、いいの……?
ぎゅっと目をつむって、とにかく何かを言葉にしようと覚悟する。
その瞬間、蓮くんが話し出した。
「芽依ちゃんは……」
「あのさ」
蓮くんの言葉が、さらに遮られる。
声を発したのは、長谷くんだった。
その声の大きさに、今度は長谷くんの方に三人の視線が集まる。
私の正面に座っている長谷くんは、背もたれに寄りかかったまま、ぽつりと呟いた。
「……相澤って、なんでそうなの」
鋭い視線が、私を捉えていた。
「煮え切らないっていうか、言いたいことを言わないっていうか。いつもびくびくしてて、なんつーか、壁があるよな」
「……ちょっと。そんなことないよー。私、相澤さんと最近お昼食べることあるけど、ちゃんと喋ってくれるもん。優馬はお昼いつも部室行ってるから知らないだろうけど!」
井上さんがフォローしてくれる。
どうしたらいいのかわからなくて、視線が井上さんと長谷くんの間をうろうろとしてしまう。
「まぁ、昼休みの様子は知らないけど。他の時間の話、だよ」
井上さんの言い分を交わすと、長谷くんは私の方に顔を戻した。
「相澤さ。中学のときはそんなんじゃなかっただろ」
——中学。
思わず、びくりと体が震えた。
「クラスメイトとも話してた。目立つタイプじゃなかったけどさ、暗いってわけでもなかった。普段話さない人ともそれなりに話せてたし。今みたいに、言葉が出てこないことはなかっただろ」
一瞬、しん、と空気が静まり返った。
どくどくと、自分の心臓の音が鳴るのが聞こえる。テーブルの下で強く握った手のひらが、じんわりと湿っていくのを感じた。
長谷くんは私と同じ、中学から高校へとエスカレーターで上がってきた生徒だ。
だから、私の中学の頃のことも多少は知っている。一方で、井上さんと蓮くんは高校から編入してきた生徒だから、中学の頃の私を知らない。
だから、口を挟む余地がない。
「よくは知らないけど、相澤が変わったのって高校に上がった頃からだろ。誰とも話さなくなって、むしろ、話しかけると嫌がるようになった。今もなんか変だよな。前も大人しい方だったけど、今はそのレベルじゃないっていうか」
——言わないで。
修ちゃんの笑顔が、頭に浮かぶ。全校生徒が体育館に集められて、修ちゃんの死を告げられた瞬間の絶望感を思い出す。
体が震えて、止まらない。
お願い。
もう言わないで。
それ以上は、もう……。
「……ずっと、思ってたんだけどさ。……もしかして、相澤って……」
その瞬間、バン、とテーブルに両手をついて、井上さんが立ち上がった。
「ゆ……!」
「長谷くん」
先に止めたのは、蓮くんだった。
蓮くんの方を見ると、たぶん真っ青な顔をしているであろう私とは対照的な、いつもの、穏やかで優しい微笑みを浮かべていた。
「誰にでも、隠しておきたいこととか、言えない気持ちはあるよ」
時が止まる。
静寂に包まれた私たちの空間を、ガヤガヤとした店内の喧騒が割り込んでくる。私たち、今お店の中にいたんだ。その賑やかさを唐突に思い出して、ふと我に返る。
でも、仕切りで隔てられている向こうとこちらでは、まるで違う世界みたいだった。
みんな楽しく食事をしているのに。私たちはいったい、何をしているんだろう。
……いや。
私、は、何をしているんだろう……。
「いや、俺は別に……」
長谷くんが、手を振って何かを言い返そうとする。
でも、私はもう限界だった。
「……ごめんなさい!」
そう言うと、立ち上がって頭を下げた。
「わ、私が優柔不断だから……。うまく喋れないだけなの。ごめんね。せっかく親睦会開いてくれたのに……。今日は、本当に楽しかった。三人の話が聞けて、うれしかった。本当に……ありがとう」
そう言い残すと、体が勝手に鞄を取って駆け出していた。
ハンバーガーを持って歩いてくる人たちをすり抜け、一目散に入り口へと向かう。もうここにいることはできないと、心が叫んでいた。
「芽依ちゃん!」
後ろから蓮くんの声が聞こえたけれど、振り返ることなく私は店を出た。