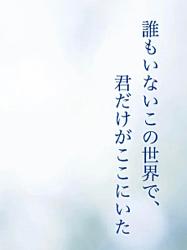*
私が通う私立高校は、いわゆる進学校と呼ばれる部類のものだった。
中高一貫校で、多くの生徒は中学から高校へとエスカレーター式に上がっていく。
偏差値は高めだけれど、進学校の中ではそれほどじゃない。そのかわりに私立ならではのボランティア活動や著名人を迎えた講義なんかがあって、他の学校にはない特別な体験ができるところが人気なのだという。
そんな中、私はこれといった理由もなくこの学校に入学していた。
それでも何か理由をひとつ挙げるとしたら、制服がかわいかったから、くらいのものだったかもしれない。小学六年生の頃の私が何を考えていたのかなんてもう朧げだけれど、今も昔も特別頭がいいわけじゃないことは確かだ。だから、まじめに授業を聞いていないとすぐみんなに置いていかれてしまう。
だけれどその日、先生の話はまったくと言っていいほど耳に入ってこなかった。
「いいかぁー、ここテストに出すからな。線引いておけよ」
聞こえてくる言葉はまるで馴染みのない言語のようで、意味を理解する前に頭の外へと逃げていってしまう。そのかわりに、あの不思議なメールの文面がずっと頭の中を駆け回っていた。
誰が送ってきたのだろう。
どうしてあんなことを書いてきたのだろう。
考えても考えてもさっぱりわからなかった。送信者はいったい何がしたくてこんなメールを送りつけてきたのだろうか。
〝君の秘密、知ってる〟
私の、秘密。
秘密……。
人の秘密とやらを、わざわざ本人に伝えてくるなんて。
やっぱり、おどし目的だろうか。そんなことをする理由といったら、相手をおどすためとしか思い浮かばなかった。
〝バラされたくなければお金を用意しろ〟——画面の向こうの人物がそう叫んでいるのを想像して背筋が凍った。相手はなんらかの方法で私の〝秘密〟を知って、それをネタに私をゆする気なのかもしれない。
でも一方で、その推測には疑問符が浮かんでいた。
〝本当はみんなと仲よくしたいのに、わざと嫌われるように振舞ってる〟
あの程度の〝秘密〟じゃ、人はおどせないと思えるから。
親のお金を盗んだとか、不正を働いてテストで高得点を取ったとかならわからなくもないけれど。わざと嫌われるように振る舞ってる、なんてたとえ人に言いふらされたとしてもたいした影響はない。人をおどす材料としては弱い、と思えた。
じゃあ、なんなんだろう。いったい何が目的で、こんなこと。
左手で、机の中のスマホにそっと触れる。もう何度も読み返したせいですっかり覚えてしまったそのメッセージを、ノートに書き出してみた。
〝わざと嫌われるように振る舞ってる〟——見れば見るほど、南極の真ん中に立っているかのように体の芯が冷たくなる。
その理由はわかっていた。
このメールは半分事実、だったから。
文章の前半、〝本当はみんなと仲よくしたいのに〟の部分は違うけれど。〝わざと嫌われるように振る舞ってる〟というのは本当のこと。
このメールは少なくとも、半分は当たっている。
——そして、その続き、も。
〝君の秘密、ふたつめ。本当は聞いてほしいのに、自分の本当の気持ちを話さない〟
〝君の秘密、みっつめ。本当は笑いたいのに、笑顔の作り方がわからない〟
ノートに、さらにふたつの文章を追加していく。今朝、井上さんから逃れようとトイレに駆け込んでから受信したメールだった。
〝秘密〟がひとつじゃなかった、ということにも驚いたけれど、加えて、それらの内容もすべて当たっていることに驚いた。〝自分の本当の気持ちを話さない〟〝笑顔の作り方がわからない〟……その通りだ。なんで知っているんだろう。まるで頭の中を見透かされているみたいで気味が悪い。
これは迷惑メールなんかじゃない。
本当に私のことを知っている人が送ってきているんだ。
その予感は、最後に送られてきたメールで確信へと変わった。
〝驚かせちゃってごめん。ずっと君のことを見てました。今日の放課後、校門前で待ってます〟
その瞬間、突然ガチャン、と派手な音がして授業が止まった。
顔を上げると、生徒たちが一斉にこちらを振り向いていた。
急に注目を浴びて、どぎまぎしてしまう。でもみんなの視線は私に向けられているわけじゃなかった。
私の右手前、床の辺りだ。私もつられて見下ろすと、床にはピンク色のポーチと、いくつもの色ペンが散らばっていた。
「井上ぇー、目ぇ覚ませ。俺の授業はそんなに退屈か?」
「……あ、スンマセーン」
先生と井上さんのやり取りに、周りがクスクスと笑い出す。どうやら、居眠りをしていた井上さんがペンケースを落としたみたいだ。周りの子たちが率先してばら撒かれたペンを拾い始める。
ふと見える、井上さんに向けられたみんなの笑顔。
その顔を一人一人、じっと見つめた。
……もしかして、メールの送信者はこの教室の中の誰かなのだろうか。
なんのつもりかわからないけれど、相手は私と会おうとしている。今日の放課後、校門前で。
ということはきっと、送信者は私がこの学校に通っていることを知っている。
そして、私の学校での振る舞いを知っている。私がクラスの子と親しくしていないことも、ほとんど笑わずに過ごしていることも。そう考えると、送信者は私と距離が近しい人——とりわけ、私と同じクラスの誰か——と考えるのが自然のように思えた。
一番後ろ、窓際の席はみんなの様子がよく見える。整然と並ぶその後頭部を、順々に見ていった。
でもどんなに見渡しても、この人が、と思える人はいなかった。
だって、私はこの中の誰にも連絡先を教えたことがないのだから。
高校に上がって十ヶ月が過ぎたけれど、このクラスの生徒たちは誰も私のアドレスを知らない。知っているのは両親と、中学の頃に親しかったごく一部の友達だけ。その顔ぶれの中から考えてみても、こんな意味深なメールを送ってくるような人に心当たりはなかった。
じゃあ、誰が。
どうして、こんなことを……。
結局上の空のまま、四時間目の終わりのチャイムが鳴った。
お昼休みが始まると、物静かだった教室は堰を切ったようにざわめき始めた。
まるで呪縛から解放されたかのように、生徒たちは自由に行動し始める。仲のいい友達の席へ移動したり、売店へ行ったり。先ほどまで真剣に授業を受けていたみんなの表情がほころび、つかの間の休息を楽しみ始める。
いつもの昼休み、いつもの教室。
——でも、これでもう、最後だ。
そっと鞄を持つと、私は教室を抜け出した。
人の行き交う廊下を進み、階段を降りていく。一階にたどり着くとそのまま下駄箱へと向かった。
玄関口には誰もいなくて、先ほどまで辺りを取り巻いていた喧騒は消えていた。
少しだけ、息がしやすい。お昼休みなのに帰り支度をして階段を降りていく不自然な私を、誰も気にかける様子がなかったことに苦笑しながらローファーに履き替える。外へ出て校門まで走ると、いとも簡単に学校を抜け出すことができた。
誰も私のことなんか見ていない——その事実にどこか安堵しながら、私は〝目的地〟へと向かって住宅街を歩き始めた。
私が通う私立高校は、いわゆる進学校と呼ばれる部類のものだった。
中高一貫校で、多くの生徒は中学から高校へとエスカレーター式に上がっていく。
偏差値は高めだけれど、進学校の中ではそれほどじゃない。そのかわりに私立ならではのボランティア活動や著名人を迎えた講義なんかがあって、他の学校にはない特別な体験ができるところが人気なのだという。
そんな中、私はこれといった理由もなくこの学校に入学していた。
それでも何か理由をひとつ挙げるとしたら、制服がかわいかったから、くらいのものだったかもしれない。小学六年生の頃の私が何を考えていたのかなんてもう朧げだけれど、今も昔も特別頭がいいわけじゃないことは確かだ。だから、まじめに授業を聞いていないとすぐみんなに置いていかれてしまう。
だけれどその日、先生の話はまったくと言っていいほど耳に入ってこなかった。
「いいかぁー、ここテストに出すからな。線引いておけよ」
聞こえてくる言葉はまるで馴染みのない言語のようで、意味を理解する前に頭の外へと逃げていってしまう。そのかわりに、あの不思議なメールの文面がずっと頭の中を駆け回っていた。
誰が送ってきたのだろう。
どうしてあんなことを書いてきたのだろう。
考えても考えてもさっぱりわからなかった。送信者はいったい何がしたくてこんなメールを送りつけてきたのだろうか。
〝君の秘密、知ってる〟
私の、秘密。
秘密……。
人の秘密とやらを、わざわざ本人に伝えてくるなんて。
やっぱり、おどし目的だろうか。そんなことをする理由といったら、相手をおどすためとしか思い浮かばなかった。
〝バラされたくなければお金を用意しろ〟——画面の向こうの人物がそう叫んでいるのを想像して背筋が凍った。相手はなんらかの方法で私の〝秘密〟を知って、それをネタに私をゆする気なのかもしれない。
でも一方で、その推測には疑問符が浮かんでいた。
〝本当はみんなと仲よくしたいのに、わざと嫌われるように振舞ってる〟
あの程度の〝秘密〟じゃ、人はおどせないと思えるから。
親のお金を盗んだとか、不正を働いてテストで高得点を取ったとかならわからなくもないけれど。わざと嫌われるように振る舞ってる、なんてたとえ人に言いふらされたとしてもたいした影響はない。人をおどす材料としては弱い、と思えた。
じゃあ、なんなんだろう。いったい何が目的で、こんなこと。
左手で、机の中のスマホにそっと触れる。もう何度も読み返したせいですっかり覚えてしまったそのメッセージを、ノートに書き出してみた。
〝わざと嫌われるように振る舞ってる〟——見れば見るほど、南極の真ん中に立っているかのように体の芯が冷たくなる。
その理由はわかっていた。
このメールは半分事実、だったから。
文章の前半、〝本当はみんなと仲よくしたいのに〟の部分は違うけれど。〝わざと嫌われるように振る舞ってる〟というのは本当のこと。
このメールは少なくとも、半分は当たっている。
——そして、その続き、も。
〝君の秘密、ふたつめ。本当は聞いてほしいのに、自分の本当の気持ちを話さない〟
〝君の秘密、みっつめ。本当は笑いたいのに、笑顔の作り方がわからない〟
ノートに、さらにふたつの文章を追加していく。今朝、井上さんから逃れようとトイレに駆け込んでから受信したメールだった。
〝秘密〟がひとつじゃなかった、ということにも驚いたけれど、加えて、それらの内容もすべて当たっていることに驚いた。〝自分の本当の気持ちを話さない〟〝笑顔の作り方がわからない〟……その通りだ。なんで知っているんだろう。まるで頭の中を見透かされているみたいで気味が悪い。
これは迷惑メールなんかじゃない。
本当に私のことを知っている人が送ってきているんだ。
その予感は、最後に送られてきたメールで確信へと変わった。
〝驚かせちゃってごめん。ずっと君のことを見てました。今日の放課後、校門前で待ってます〟
その瞬間、突然ガチャン、と派手な音がして授業が止まった。
顔を上げると、生徒たちが一斉にこちらを振り向いていた。
急に注目を浴びて、どぎまぎしてしまう。でもみんなの視線は私に向けられているわけじゃなかった。
私の右手前、床の辺りだ。私もつられて見下ろすと、床にはピンク色のポーチと、いくつもの色ペンが散らばっていた。
「井上ぇー、目ぇ覚ませ。俺の授業はそんなに退屈か?」
「……あ、スンマセーン」
先生と井上さんのやり取りに、周りがクスクスと笑い出す。どうやら、居眠りをしていた井上さんがペンケースを落としたみたいだ。周りの子たちが率先してばら撒かれたペンを拾い始める。
ふと見える、井上さんに向けられたみんなの笑顔。
その顔を一人一人、じっと見つめた。
……もしかして、メールの送信者はこの教室の中の誰かなのだろうか。
なんのつもりかわからないけれど、相手は私と会おうとしている。今日の放課後、校門前で。
ということはきっと、送信者は私がこの学校に通っていることを知っている。
そして、私の学校での振る舞いを知っている。私がクラスの子と親しくしていないことも、ほとんど笑わずに過ごしていることも。そう考えると、送信者は私と距離が近しい人——とりわけ、私と同じクラスの誰か——と考えるのが自然のように思えた。
一番後ろ、窓際の席はみんなの様子がよく見える。整然と並ぶその後頭部を、順々に見ていった。
でもどんなに見渡しても、この人が、と思える人はいなかった。
だって、私はこの中の誰にも連絡先を教えたことがないのだから。
高校に上がって十ヶ月が過ぎたけれど、このクラスの生徒たちは誰も私のアドレスを知らない。知っているのは両親と、中学の頃に親しかったごく一部の友達だけ。その顔ぶれの中から考えてみても、こんな意味深なメールを送ってくるような人に心当たりはなかった。
じゃあ、誰が。
どうして、こんなことを……。
結局上の空のまま、四時間目の終わりのチャイムが鳴った。
お昼休みが始まると、物静かだった教室は堰を切ったようにざわめき始めた。
まるで呪縛から解放されたかのように、生徒たちは自由に行動し始める。仲のいい友達の席へ移動したり、売店へ行ったり。先ほどまで真剣に授業を受けていたみんなの表情がほころび、つかの間の休息を楽しみ始める。
いつもの昼休み、いつもの教室。
——でも、これでもう、最後だ。
そっと鞄を持つと、私は教室を抜け出した。
人の行き交う廊下を進み、階段を降りていく。一階にたどり着くとそのまま下駄箱へと向かった。
玄関口には誰もいなくて、先ほどまで辺りを取り巻いていた喧騒は消えていた。
少しだけ、息がしやすい。お昼休みなのに帰り支度をして階段を降りていく不自然な私を、誰も気にかける様子がなかったことに苦笑しながらローファーに履き替える。外へ出て校門まで走ると、いとも簡単に学校を抜け出すことができた。
誰も私のことなんか見ていない——その事実にどこか安堵しながら、私は〝目的地〟へと向かって住宅街を歩き始めた。