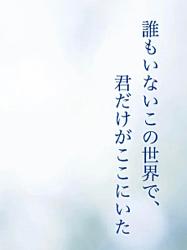なんで、荻原くんはこんなに純粋なのだろう。
薄汚れた自分が嫌になる。うそばかり……秘密ばかり。なんで私が荻原くんの横にいるのかわからなくなる。
流されるままに荻原くんと一緒にいるけれど、結局私はそれに甘えている。
修ちゃんのところへ行きたいと思いながら、結局荻原くんの優しさにしがみついている。
そして、自分を肯定しようとしてるんだ。
逃げ続けている。
目を背け続けている。
ずるい、自分……。
また一人で落ち込んでいると、荻原くんがふと起き上がって、私と同じように空を見上げた。
「ごめん、もう時間なくなっちゃったね」
言われて、思い出した。このあと、私のデートコースを巡る予定だったんだ。
でも、腕時計を見ると十六時をすぎていた。春は近いといっても日が傾くのは早いから、今から公園の入り口まで戻ってからどこかへ行くのは難しいかもしれない。
荻原くんは膝を抱えると、目を伏せた。
「……なんてね。ごめん、本当は、今日は一日ここにいるつもりだったんだ。芽依ちゃんは行きたいところ、思いつかないだろうなって思ってたから……。ただ、芽依ちゃんにも僕と行きたいところ、考えてほしかっただけで」
荻原くんは膝の中に顔を埋めると、少ししてから、ぱっと立ち上がった。
「困らせちゃってごめんね。寒くなってきたし、戻ろうか。戻るのも時間かかるし」
「……行きたいところ、あったんだ」
つい、言ってしまった。
荻原くんは、え、と私の顔を見下ろす。
「本当? ごめん……どこ?」
昨日の夜遅くまで、ずっと考えていた。
私の行きたいところ。荻原くんと一緒に行きたいところ。ひとつだけ、見つかった。でもそれは、荻原くんの望むものじゃないと思ったけれど。
胸のうちにしまって、そのまま帰ればよかったのに。
つい言葉が出てしまった。
「……三笠、駅」
ぽつりと呟くと、怖くなって、今度は私が俯いた。
自分の両手を強く握って、荻原くんの反応を待つ。口にするだけで汗が出て、背中が冷たくなるのを感じた。
荻原くんはしばらく考えてから、言葉を落とした。
「……幼馴染の子が、事故にあったところ?」
小さく、頷いた。
——修ちゃんが亡くなってから、私は一度も修ちゃんに会いに行けていなかった。
事故の遭った駅にも、お墓参りにも。お葬式にだって行けなかった。怖くて、つらくて。本当は花を手向けたいのに、修ちゃんに合わせる顔が見つからなくて、私は逃げて、逃げて、逃げ続けていた。
情けなくて、どうしようもない。
一年も経った今更、こんなことを言うなんて。
「……行こうよ。今からでも、大丈夫だから」
荻原くんが、俯く私の顔を覗き込んでくる。
私は身を引きながら、首を振った。
「……やっぱり、行けない。帰ろう」
「どうして?」
「荻原くんと二人でなんか行ったら、修ちゃん、怒るから」
私の返答に、荻原くんは意味がわからないようで眉根を寄せている。
「……怒る?」
小さく、頷いた。
「私……一人で修ちゃんに会いに行くのが怖くて。荻原くんが一緒にいてくれたら、行けるかもしれないって思った。でも、だめなの。私のせいで修ちゃんは事故に遭ったのに。そんな私が、人に付き添われて会いに行ったりしたら……修ちゃん、怒るよ」
馬鹿なことを考えていた。
よく考えれば、わかることだった。修ちゃんはそんなこと望んでないって。
自分は事故に遭ったのに、その原因を作った私が誰かに助けられながら修ちゃんに会いにいくなんて。そんなの、まるで当て付けみたいだ。
修ちゃんは、亡くなったのに。知らない男の子に支えられてやってくる私なんて、修ちゃんはきっと見たくない。ひどい発想だ。行くにしたって、一人で行くべきだ。
そんな無神経なこと、思いついただけでも傲慢だと思えた。
太陽の気配が薄まった、冷たい風が吹いてくる。
荻原くんは、その風が止むのを待ってから口を開いた。
「……その人は、そんな風に思うの?」
そっと、荻原くんの顔を見る。
まっすぐな視線は私を捉えて離さなかった。
「僕と芽依ちゃんが一緒にいたら……幼馴染の子は、怒るの?」
「……そう、だよ」
「勇気を出してやってきた、芽依ちゃんを? 今まで悩んで、苦しんで、それでもどうにかしてやってきてくれた芽依ちゃんを……怒る?」
口をつぐんだ。
「……本当に?」
〝俺、勝手に事故っただけだよ〟
〝芽依が気にすることなんかないよ、バカだな〟
ふと、あっけらかんとした修ちゃんの声が、頭の中で聞こえたような気がした。
……本当は、わかってる。
修ちゃんは怒ったりしない。
修ちゃんは私のことを否定しない。笑って、自分が悪かったんだから、って言うに決まってる。芽依のせいじゃない、俺が勝手にホームに降りたんだ、いつまでもそんなことでぐじぐじしてんなよ、って言う。そういう人だ。
でも、違う。
怒るのは、修ちゃんじゃない。
許せないのは、修ちゃんじゃない。
怒っているのは、許せないのは、他の誰でもない——私自身なんだ。
だから、私は修ちゃんに会いに行けない。
私が、私を、許さないから。
だから私は、修ちゃんが亡くなって一年が経ったあの日、駅のホームに立って……。
ぎゅっと手を握った。体が震える。心も体も冷たくて、凍ったまま動けなくなりそうになる。
その肩に、温かな手が触れた。
顔を上げると、穏やかな荻原くんの表情があった。
「……帰ろっか」
薄汚れた自分が嫌になる。うそばかり……秘密ばかり。なんで私が荻原くんの横にいるのかわからなくなる。
流されるままに荻原くんと一緒にいるけれど、結局私はそれに甘えている。
修ちゃんのところへ行きたいと思いながら、結局荻原くんの優しさにしがみついている。
そして、自分を肯定しようとしてるんだ。
逃げ続けている。
目を背け続けている。
ずるい、自分……。
また一人で落ち込んでいると、荻原くんがふと起き上がって、私と同じように空を見上げた。
「ごめん、もう時間なくなっちゃったね」
言われて、思い出した。このあと、私のデートコースを巡る予定だったんだ。
でも、腕時計を見ると十六時をすぎていた。春は近いといっても日が傾くのは早いから、今から公園の入り口まで戻ってからどこかへ行くのは難しいかもしれない。
荻原くんは膝を抱えると、目を伏せた。
「……なんてね。ごめん、本当は、今日は一日ここにいるつもりだったんだ。芽依ちゃんは行きたいところ、思いつかないだろうなって思ってたから……。ただ、芽依ちゃんにも僕と行きたいところ、考えてほしかっただけで」
荻原くんは膝の中に顔を埋めると、少ししてから、ぱっと立ち上がった。
「困らせちゃってごめんね。寒くなってきたし、戻ろうか。戻るのも時間かかるし」
「……行きたいところ、あったんだ」
つい、言ってしまった。
荻原くんは、え、と私の顔を見下ろす。
「本当? ごめん……どこ?」
昨日の夜遅くまで、ずっと考えていた。
私の行きたいところ。荻原くんと一緒に行きたいところ。ひとつだけ、見つかった。でもそれは、荻原くんの望むものじゃないと思ったけれど。
胸のうちにしまって、そのまま帰ればよかったのに。
つい言葉が出てしまった。
「……三笠、駅」
ぽつりと呟くと、怖くなって、今度は私が俯いた。
自分の両手を強く握って、荻原くんの反応を待つ。口にするだけで汗が出て、背中が冷たくなるのを感じた。
荻原くんはしばらく考えてから、言葉を落とした。
「……幼馴染の子が、事故にあったところ?」
小さく、頷いた。
——修ちゃんが亡くなってから、私は一度も修ちゃんに会いに行けていなかった。
事故の遭った駅にも、お墓参りにも。お葬式にだって行けなかった。怖くて、つらくて。本当は花を手向けたいのに、修ちゃんに合わせる顔が見つからなくて、私は逃げて、逃げて、逃げ続けていた。
情けなくて、どうしようもない。
一年も経った今更、こんなことを言うなんて。
「……行こうよ。今からでも、大丈夫だから」
荻原くんが、俯く私の顔を覗き込んでくる。
私は身を引きながら、首を振った。
「……やっぱり、行けない。帰ろう」
「どうして?」
「荻原くんと二人でなんか行ったら、修ちゃん、怒るから」
私の返答に、荻原くんは意味がわからないようで眉根を寄せている。
「……怒る?」
小さく、頷いた。
「私……一人で修ちゃんに会いに行くのが怖くて。荻原くんが一緒にいてくれたら、行けるかもしれないって思った。でも、だめなの。私のせいで修ちゃんは事故に遭ったのに。そんな私が、人に付き添われて会いに行ったりしたら……修ちゃん、怒るよ」
馬鹿なことを考えていた。
よく考えれば、わかることだった。修ちゃんはそんなこと望んでないって。
自分は事故に遭ったのに、その原因を作った私が誰かに助けられながら修ちゃんに会いにいくなんて。そんなの、まるで当て付けみたいだ。
修ちゃんは、亡くなったのに。知らない男の子に支えられてやってくる私なんて、修ちゃんはきっと見たくない。ひどい発想だ。行くにしたって、一人で行くべきだ。
そんな無神経なこと、思いついただけでも傲慢だと思えた。
太陽の気配が薄まった、冷たい風が吹いてくる。
荻原くんは、その風が止むのを待ってから口を開いた。
「……その人は、そんな風に思うの?」
そっと、荻原くんの顔を見る。
まっすぐな視線は私を捉えて離さなかった。
「僕と芽依ちゃんが一緒にいたら……幼馴染の子は、怒るの?」
「……そう、だよ」
「勇気を出してやってきた、芽依ちゃんを? 今まで悩んで、苦しんで、それでもどうにかしてやってきてくれた芽依ちゃんを……怒る?」
口をつぐんだ。
「……本当に?」
〝俺、勝手に事故っただけだよ〟
〝芽依が気にすることなんかないよ、バカだな〟
ふと、あっけらかんとした修ちゃんの声が、頭の中で聞こえたような気がした。
……本当は、わかってる。
修ちゃんは怒ったりしない。
修ちゃんは私のことを否定しない。笑って、自分が悪かったんだから、って言うに決まってる。芽依のせいじゃない、俺が勝手にホームに降りたんだ、いつまでもそんなことでぐじぐじしてんなよ、って言う。そういう人だ。
でも、違う。
怒るのは、修ちゃんじゃない。
許せないのは、修ちゃんじゃない。
怒っているのは、許せないのは、他の誰でもない——私自身なんだ。
だから、私は修ちゃんに会いに行けない。
私が、私を、許さないから。
だから私は、修ちゃんが亡くなって一年が経ったあの日、駅のホームに立って……。
ぎゅっと手を握った。体が震える。心も体も冷たくて、凍ったまま動けなくなりそうになる。
その肩に、温かな手が触れた。
顔を上げると、穏やかな荻原くんの表情があった。
「……帰ろっか」