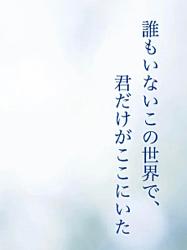どの街の駅前にもある、とあるチェーン店の喫茶店を見かけると思い出してしまう記憶がある。
あれはたしか、中学二年生の夏のことだった。日曜日のお昼どき、私は学校から五つほど離れた駅の街を歩いていた。
中学生になってからはじめて電車通学になったものの、私はそれ以外で一人で遠出をすることがなかった。だから、はじめての街を歩くのは少し心細かった。
そんな中、駅前のロータリーを抜けたところで、聞き慣れた声が聞こえてきたのだ。
「芽依!」
振り返ると、雑踏を縫うようにして走ってくる修ちゃんの姿があった。
その顔を見て、不安な気持ちは一気に消し飛び、思わず笑みが溢れてしまった。
「修ちゃん! どうしたの、こんなところで」
「この辺、うちからチャリですぐなんだよ。うわー、なんか久しぶりだな。最近廊下でもすれ違わないから、芽依のタヌキ顔見れてなくて寂しかった」
もう、と言ってむくれると、修ちゃんは私の頭をわしゃわしゃと撫でた。
その時、修ちゃんの顔を見るのは数ヶ月ぶりだったと思う。ついこの前まで同じクラスで毎日顔を合わせていたのに、二年生になってからクラスが離れてしまったから。
うちの学校は高校に上がると受験に集中するためクラス替えは行われないのだけれど、中学の間はみんなと交流を深められるよう、毎年クラス替えが行われる。でもクラスが離れたからってこんなに修ちゃんと話す機会が減ってしまうとは思わず、私は四月からずっと寂しい思いをしていた。
修ちゃんも私と同様久しぶりに会えたことがうれしかったようで、はしゃいだ様子で腕を掴んできた。
「あのさ、今そこの喫茶店でメシ食べてたんだ。芽依はもう昼食べた? 奢ってやるからさ、なんか食べよーぜ」
喫茶店。
修ちゃんの口からそんな言葉が出るなんて思わず、少し驚いた。
小学生の頃なんて、外食はおろか、コンビニでお菓子を買って二人で分け合うくらいが関の山だったのに。最近はそんなおしゃれな場所でご飯食べてるんだ。
ご両親が一軒家を建ててから、少し離れた街へと引っ越してしまった修ちゃん。
いつのまにか、私の知らない街で、私の行ったことのないようなお店で日々を過ごしている。その距離感に、どこか寂しさを感じてしまった。
小さい頃から一緒だった。修ちゃんのことならなんでも知ってると思っていた、大切な、大切な人。
でももう、そんな年齢でもなくなってしまったのかもしれない。
「……ごめん。行きたいけど、私これから友達の家で勉強するんだ。でも、喫茶店は行ってみたいな。また今度誘ってね」
努めて、なんでもないような顔をして答えた。
すると、いつも明るい修ちゃんの表情が珍しく曇った。
「え、友達? ……それってまさか、オトコ?」
「ううん、女の子。うちのクラスの小林さんと、水谷さんと……あ、修ちゃんは知らない人だよね。オトコって、まさか、私がお休みの日に男の子と会うわけないじゃん」
答えると、修ちゃんは一瞬の間を置いて、だよなぁー、と笑った。
でも、その反応もちょっと失礼だ。人見知りの私は同性の子と仲よくするので精いっぱいだけど、将来のことはわからない。私ももう少し大人になったら修ちゃん以外の男の子とも仲よくなれるかもしれないのに。
修ちゃんはひとしきり笑い終えると、すっと手を伸ばしてきて、また私の頭をわしゃわしゃと撫でた。
髪があっちこっちに絡まって、せっかくとかしてきた髪がぼさぼさになる。頭を撫でてくるのは修ちゃんの癖みたいなものだけど、そう何度もやられると困ってしまう。
「やだー、もう。なに?」
「芽依が、ちゃんと友達できてるってわかってほっとしてるだけー」
その笑顔に、私もつられて笑ってしまった。
……そうだ。
思い出した。私が、今通っている私立の中高一貫校を受験した理由。
修ちゃんが、受験するって聞いたからだ。
ずっと近所に住んでいた修ちゃんは、幼稚園、小学校と同じ環境で過ごしてきた。その中で、私は何度修ちゃんに助けられたかわからない。
引っ込み思案の私は、いつも社交的な修ちゃんに引っ張られるようにして友達を作ってきたから。
修ちゃんが私立の学校を受験することになったのは、ご両親の意向だと聞いた。だから、私が公立の中学へ進んだら修ちゃんとは会えなくなってしまう。離れたくなかった。修ちゃんのそばにいたかった。でも、その動機をお母さんに話したらきっと受験させてもらえないと思ったから、「中学生になったらもっとがんばって勉強したいから」なんて、うその理由をでっち上げた。
そして、二人してギリギリ入れた進学校。
入学後も、修ちゃんは新しい環境で友達ができるよう、私のことを気にかけてくれた。
そのおかげで私は三年間、無事楽しい中学生活を送れた。
なのに、そんな大切な修ちゃんを、私は助けられなかったんだ。
通学途中の電車の窓からあのカフェの看板が見えて、思い出してしまった。修ちゃんとの思い出。結局、あの喫茶店は行けずじまいだ。
……ごめんなさい。
その時、鞄の中のスマホが震えた。
〝芽依ちゃん、おはよう〟
荻原くんの、いつもの朝のチャット。
その変わらないメッセージが、私の心を少しだけ落ち着かせる。いつのまにか脈打っていた鼓動が、少しずつ緩やかになっていく。
それがいいことなのか、悪いことなのかはわからないけれど。
それでも、私は強く目をつむると深呼吸をして、電車が駅に到着するのを待った。