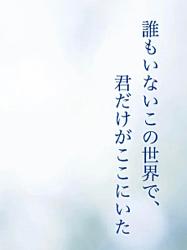〝二十四時間、私のこと見てるくらいじゃないと〟
五日前、私はたしかにそう言った。
荻原くんが、明日もお昼休みを一緒に過ごしたい、と言い出したから。私のことが心配だからと、そう、言ったから。
でも、あんなのは言葉のあやだ。
荻原くんと一緒にいたくなかった私の、諦めさせるためだけに使った言い訳。全然、本気なんかじゃなかった。
なのに。
なんで、私を掴む手のひらが、そんなに冷たいの?
なんで、そんなに唇が青ざめてるの?
どうして? いつから?
いつから、ここに、いたの……?
察したように笑う彼は、この一週間の間に何度も屋上で見た、いつもの穏やかな笑顔を浮かべていた。
「ごめん、芽依ちゃんが心配だったから」
「……私、旅行に行くって言ったじゃん!」
「でも、いつ気が変わってここに来るかわからないでしょ」
思わず、その手を振り解いた。
〝どうにかしたいって思うから、がんばるんだよ〟
どうして、なんで、という疑問が頭の中を駆け巡る。胸が痛くて、言葉すらも出てこなくなってしまう。
……この人は、今まで私のために、どんなことをしてきたのだろう。
たぶん、今日だけじゃない。
デザート作りや、英語のノート作り、だけじゃない。きっと私の知らないところで、これまでも私のために動いていたんだ。この一週間、私のことをずっと見ていたんだ。
……違う。
〝ずっと見てたんだ。芽依ちゃんのこと〟
出会ってから今日まで、だけじゃない。
きっと、もっともっと、ずっと前から……。
荻原くんがじっと私を見つめる。
その瞳は、どんなに真っ暗な闇の中でも、どこからか光を集めて輝いている。
その視線が、眩しくて純粋だから……つらい。
「……もう、やめてよ!」
思わず叫んだ。
そしてその瞳から逃れるようにしゃがみ込むと、同時に涙が溢れた。
アスファルトの上に、ぽつりと黒いシミが生まれる。それはすぐに数を増やし、いくつもの点を打っていった。
修ちゃんがいなくなって、何度流したかわからない涙だった。
「決めたの……。私、もう死ぬって決めたの。だからもう、やめてよ! こんなことしたって意味なんかないから!」
しばらくの間、私は泣き続けた。
苦しくて、悲しくて、もう何も話せなかった。一度溢れ出した涙は止まらない。恥ずかしくて止めようと思っても喉の奥が痛くなるばかりで、どうすることもできず、私は子供のように声を上げ続けた。
その間、荻原くんは私のかたわらにしゃがみ、ずっと背中をさすっていた。
大きな手のひらが、私をなだめるように揺れ続ける。その温かな温度に、癒されてしまう自分が許せなかった。
私には、優しくされる権利なんかないのに。
みんなから、寄ってたかって批判されてもいい存在なのに。
苦しい。
苦しくて、たまらない。
それでもしばらくして嗚咽が止まると、荻原くんが小さく呟いた。
「やっと、話してくれた」
言われて、思わず顔を上げた。
荻原くんは変わらず、私を静かに見つめていた。
「……え?」
「本当の、気持ち。芽依ちゃん、一番大事なことは話してくれないから」
本当の、気持ち……。
その言葉を、知っている。
〝君の秘密、ふたつめ。本当は聞いてほしいのに、自分の本当の気持ちを話さない〟
……私の〝秘密〟だ。
その視線から目を逸らし、地面を見つめると、自然と言葉が溢れてきた。
「……修ちゃんが亡くなったのは、私のせいなの。私があの夜……修ちゃんを、止めなかった、から」
荻原くんは黙って私の言葉に耳を傾けているようだった。
私は何度も言葉を詰まらせながら、それでも、続けた。
「あの夜……、修ちゃんは、私の家に来ようとしてた。その途中の駅のホームで事故に遭ったの。私がいなければ、あの駅に行くことはなかった。修ちゃんは今も、元気に生きてた……。……だから、私は幸せになっちゃいけないの。修ちゃんがいなくなってから今日まで、ずっと考えてた……でも、もう無理だってわかった。限界なの。だから、もう、私を止めようと、しないで」
はじめて出てきた、本当の言葉。
誰にも言わずにいた、私の秘密。
それが口から溢れて、私はなぜか今、ほっとしていた。
……本当は、ずっとこうしたかったのかもしれない。
言葉にすれば、醜い自分があらわになってしまうのだけれど。まだ誰にも知られていないはずの罪を、さらけ出すことになってしまうのだけれど。
でも、もう一人で抱えるのは限界だったから。
私は、弱い人間だから。
「……知ってた」
荻原くんの、穏やかな声が落ちてきた。
「そうやって、苦しんでること。幼馴染の子のことを、ずっと考えていたこと。だからメールしたんだ。あの日……幼馴染の子の、命日に。声をかけるかどうかずっと悩んでたんだけど……やっぱり、芽依ちゃんが一番つらい日に、何かが起きてしまう前に、そばにいたいって思って。悲しいことばかり考えていないで、今だけは僕のことだけを考えてもらえるようにって」
地面についていた私の右手を、荻原くんが拾い上げる。そしてぎゅっと握った。
顔を上げると、真剣な表情をした荻原くんの表情があった。
「自分を責めないで」
涙は止まらずに、頬を伝い続けていた。
「どうしようもなかったことだよ。芽依ちゃんのせいじゃない。いろいろなことが重なったんだ。誰のせいでもない」
そんなことない。
私があの日、修ちゃんが家へ来ることを断っていれば、修ちゃんは亡くなったりしなかった。
私がお土産はまた今度受け取るね、と気遣ってあげられたら、修ちゃんは高校の制服を着て、今でも学校に登校できていた。
大きく首を振って、荻原くんの言葉を否定する。
すると、私を包む荻原くんの手が、さらに強く握られた。
「芽依ちゃんが死ぬなら、僕も死ぬよ」
……え。
顔を上げる。
いつもの笑顔。お昼休みに雑談する時と同じ、当たり前みたいな表情で、荻原くんは微笑んでいる。
わからない。
なんで、この人は。
どうして、この人は。
そんなに、私のこと……。
「……なんで」
「ね。一緒に、生きよう」
全然、わからない。荻原くんのことが。
でも、私を包むその手のひらが、温かい温度を取り戻そうとしていて。
この寒空の下、凍えながらベンチにいたはずの荻原くんの手のひらが、それでも私を温めようとしていて。
——私は、その手を離すことができなかったんだ。
=========================
・本当はみんなと仲よくしたいのに、わざと嫌われるように振舞ってる
・本当は聞いてほしいのに、自分の本当の気持ちを話さない◯
・本当は笑いたいのに、笑顔の作り方がわからない
・本当はつらくてたまらないのに、人に頼ることができない
・幼馴染が亡くなってしまったことを、ずっと引きずってる
=========================
五日前、私はたしかにそう言った。
荻原くんが、明日もお昼休みを一緒に過ごしたい、と言い出したから。私のことが心配だからと、そう、言ったから。
でも、あんなのは言葉のあやだ。
荻原くんと一緒にいたくなかった私の、諦めさせるためだけに使った言い訳。全然、本気なんかじゃなかった。
なのに。
なんで、私を掴む手のひらが、そんなに冷たいの?
なんで、そんなに唇が青ざめてるの?
どうして? いつから?
いつから、ここに、いたの……?
察したように笑う彼は、この一週間の間に何度も屋上で見た、いつもの穏やかな笑顔を浮かべていた。
「ごめん、芽依ちゃんが心配だったから」
「……私、旅行に行くって言ったじゃん!」
「でも、いつ気が変わってここに来るかわからないでしょ」
思わず、その手を振り解いた。
〝どうにかしたいって思うから、がんばるんだよ〟
どうして、なんで、という疑問が頭の中を駆け巡る。胸が痛くて、言葉すらも出てこなくなってしまう。
……この人は、今まで私のために、どんなことをしてきたのだろう。
たぶん、今日だけじゃない。
デザート作りや、英語のノート作り、だけじゃない。きっと私の知らないところで、これまでも私のために動いていたんだ。この一週間、私のことをずっと見ていたんだ。
……違う。
〝ずっと見てたんだ。芽依ちゃんのこと〟
出会ってから今日まで、だけじゃない。
きっと、もっともっと、ずっと前から……。
荻原くんがじっと私を見つめる。
その瞳は、どんなに真っ暗な闇の中でも、どこからか光を集めて輝いている。
その視線が、眩しくて純粋だから……つらい。
「……もう、やめてよ!」
思わず叫んだ。
そしてその瞳から逃れるようにしゃがみ込むと、同時に涙が溢れた。
アスファルトの上に、ぽつりと黒いシミが生まれる。それはすぐに数を増やし、いくつもの点を打っていった。
修ちゃんがいなくなって、何度流したかわからない涙だった。
「決めたの……。私、もう死ぬって決めたの。だからもう、やめてよ! こんなことしたって意味なんかないから!」
しばらくの間、私は泣き続けた。
苦しくて、悲しくて、もう何も話せなかった。一度溢れ出した涙は止まらない。恥ずかしくて止めようと思っても喉の奥が痛くなるばかりで、どうすることもできず、私は子供のように声を上げ続けた。
その間、荻原くんは私のかたわらにしゃがみ、ずっと背中をさすっていた。
大きな手のひらが、私をなだめるように揺れ続ける。その温かな温度に、癒されてしまう自分が許せなかった。
私には、優しくされる権利なんかないのに。
みんなから、寄ってたかって批判されてもいい存在なのに。
苦しい。
苦しくて、たまらない。
それでもしばらくして嗚咽が止まると、荻原くんが小さく呟いた。
「やっと、話してくれた」
言われて、思わず顔を上げた。
荻原くんは変わらず、私を静かに見つめていた。
「……え?」
「本当の、気持ち。芽依ちゃん、一番大事なことは話してくれないから」
本当の、気持ち……。
その言葉を、知っている。
〝君の秘密、ふたつめ。本当は聞いてほしいのに、自分の本当の気持ちを話さない〟
……私の〝秘密〟だ。
その視線から目を逸らし、地面を見つめると、自然と言葉が溢れてきた。
「……修ちゃんが亡くなったのは、私のせいなの。私があの夜……修ちゃんを、止めなかった、から」
荻原くんは黙って私の言葉に耳を傾けているようだった。
私は何度も言葉を詰まらせながら、それでも、続けた。
「あの夜……、修ちゃんは、私の家に来ようとしてた。その途中の駅のホームで事故に遭ったの。私がいなければ、あの駅に行くことはなかった。修ちゃんは今も、元気に生きてた……。……だから、私は幸せになっちゃいけないの。修ちゃんがいなくなってから今日まで、ずっと考えてた……でも、もう無理だってわかった。限界なの。だから、もう、私を止めようと、しないで」
はじめて出てきた、本当の言葉。
誰にも言わずにいた、私の秘密。
それが口から溢れて、私はなぜか今、ほっとしていた。
……本当は、ずっとこうしたかったのかもしれない。
言葉にすれば、醜い自分があらわになってしまうのだけれど。まだ誰にも知られていないはずの罪を、さらけ出すことになってしまうのだけれど。
でも、もう一人で抱えるのは限界だったから。
私は、弱い人間だから。
「……知ってた」
荻原くんの、穏やかな声が落ちてきた。
「そうやって、苦しんでること。幼馴染の子のことを、ずっと考えていたこと。だからメールしたんだ。あの日……幼馴染の子の、命日に。声をかけるかどうかずっと悩んでたんだけど……やっぱり、芽依ちゃんが一番つらい日に、何かが起きてしまう前に、そばにいたいって思って。悲しいことばかり考えていないで、今だけは僕のことだけを考えてもらえるようにって」
地面についていた私の右手を、荻原くんが拾い上げる。そしてぎゅっと握った。
顔を上げると、真剣な表情をした荻原くんの表情があった。
「自分を責めないで」
涙は止まらずに、頬を伝い続けていた。
「どうしようもなかったことだよ。芽依ちゃんのせいじゃない。いろいろなことが重なったんだ。誰のせいでもない」
そんなことない。
私があの日、修ちゃんが家へ来ることを断っていれば、修ちゃんは亡くなったりしなかった。
私がお土産はまた今度受け取るね、と気遣ってあげられたら、修ちゃんは高校の制服を着て、今でも学校に登校できていた。
大きく首を振って、荻原くんの言葉を否定する。
すると、私を包む荻原くんの手が、さらに強く握られた。
「芽依ちゃんが死ぬなら、僕も死ぬよ」
……え。
顔を上げる。
いつもの笑顔。お昼休みに雑談する時と同じ、当たり前みたいな表情で、荻原くんは微笑んでいる。
わからない。
なんで、この人は。
どうして、この人は。
そんなに、私のこと……。
「……なんで」
「ね。一緒に、生きよう」
全然、わからない。荻原くんのことが。
でも、私を包むその手のひらが、温かい温度を取り戻そうとしていて。
この寒空の下、凍えながらベンチにいたはずの荻原くんの手のひらが、それでも私を温めようとしていて。
——私は、その手を離すことができなかったんだ。
=========================
・本当はみんなと仲よくしたいのに、わざと嫌われるように振舞ってる
・本当は聞いてほしいのに、自分の本当の気持ちを話さない◯
・本当は笑いたいのに、笑顔の作り方がわからない
・本当はつらくてたまらないのに、人に頼ることができない
・幼馴染が亡くなってしまったことを、ずっと引きずってる
=========================