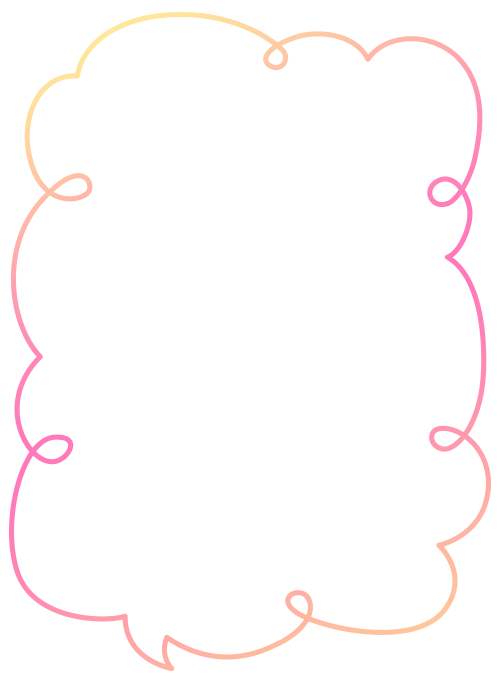セリナ=カルミアは夢だと思った。
明日婚約する相手が死んでいる。
腹を剣で一刺しされたのだろう。自ら生み出した赤い水溜まりのベッドで、その王子は眠っていた。
乾いた眼球で、最期に見たものは何だったのだろう。
薄っすら開かれた唇で、最期に何を言おうとしたのだろう。
セリナは知らない。
何度殺そうとしても、死んでくれなかった。あれだけ自分が殺したかった男のはずなのに。
――どうして?
――どうしてわたし以外の相手に殺されているの?
セリナは呆然とそれを見下ろしたまま、胸元の首飾りを握りしめる。
それは数時間前に、この男に貰ったもの。見た目も大きさも冷たい氷のような宝石が思わず目を惹く、彼が宝物だと言っていた物。自分の女の証だと、婚約の印に彼がくれた物。
笑えばいいのか。泣けばいいのか。
喜べばいいのか。悲しめばいいのか。
セリナが己の感情を持て余していた時だった。
ふと、お腹の中心が熱くなる。それが引き抜かれた瞬間、一気に全身が冷たくなる。腹部に手を当てれば、彼のベッドと同じ赤いものが彼女の手に付いていた。ヌメリとした感触を気持ち悪いと思うよりも早く。
「あなたさえいなければ」
そして、セリナの周りに虹色の靄が立ち込める。
ハッと気がつくと――セリナは、屋根の上で身を屈めていた。息を潜めなければならない。だけど途端に声が出そうになって、自分で自分の口を塞ぐ。
――あれ、わたし寝てたの?
自分の腹部を触っても、それは闇夜に紛れる黒装束。もちろん穴一つない。星も出ていない静まり返った常闇の夜。暗殺に適した夜。その中で一番明るいのは、サラリと揺れるセリナの髪だけだ。
――しっかりしなさい!
と、胸中で自身を叱咤し、セリナは自分の頬を叩いた。止まらない冷や汗を、無理やり抑え込む。
あれは夢。あれは幻。もしくは願望。
自分には成すべきことがある。何度失敗しても、成さなきゃならないことがある。
それは祖国の誇りのため。自分の尊厳のため。
こんな屋根の上で、うたた寝している場合ではない。
――今日こそ、あいつを殺さなくては!
しなやかな身体を滑らせて、セリナは窓の塀を掴んだ。そして流れるような動きで窓ガラスを蹴り抜く。静かな夜に響くには派手すぎる音。それに狼狽えることなく、彼女は灯りの付いていない部屋の中に着地しては、すぐさま絨毯を蹴る。一足飛びで向かうは寝台。天蓋の付いたベッドで眠るのは、整った顔立ちの王子。彼の喉元にナイフを突き付けようとして――その切っ先が届くよりも前に、セリナの手が掴まれた。
目をパッチリ開けた二十歳の王子がニンマリと笑う。
やっぱり、今日も殺せなかった。
「今宵もずいぶん派手な夜伽の誘いだな?」
「昨晩の窓の外から魔法をぶちこんだ時より、地味だと思うわよ?」
「あれはもう止めてくれ。さすがに部屋を直すのに骨が折れた」
肩を竦めたふりをする余裕綽々な王子、ロック=サンビタリアに対して、セリナもまた大きなため息を吐いた。
「あーもう、今日は止め止め。本当、いつになったら殺されてくれるのよ?」
「滅相もない! 俺の心はとうの昔に射抜かれているんだぜ――婚約者様?」
そこで、王子が枕元の灯りを着けた。セリナの掻き上げた髪が黄金に輝き、勝ち気な青い瞳が寝転んだままのロックを見下ろす。
「まだ正式に婚約してないわよ」
「でも婚約式は明後日だろ?」
「まだなもんはまだです!」
紅も引いていないのに艷やかの唇を尖らせたセリナに対して、ロックはクツクツと笑った。
「そんな可愛いことを言う姫様には、先に身体でわからせないとかな?」
それは一瞬だった。セリナがまばたきする間に、視界が回った。背中がポスンと心地よい弾力に包まれたかと思った時には、眼前に琥珀の瞳が迫っていた。
――あれ?
灰色の小ざっぱりとした髪も、寝台の暖かな光に当たれば雅に染まる。普段は少年のように豊かな表情も、今は色気を隠し切れていなかった。セリナも思わず、意外にも長いまつげに息を呑んでしまうほどに。
部屋に響く嚥下の音は、どちらのものだろうか。
それに、セリナはハッとする――その光景を、つい昨日見た覚えがあったから。
固まったセリナの耳元で、ロックが囁く。
「ん? どうした?」
「あんた……昨日も同じことしなかった?」
「え? 昨日は部屋がグチャグチャにされてそれどころじゃなかっただろ?」
「それも……そうよね?」
そうだ。さっきこの男と話した通り、昨晩は窓の外から攻撃魔法を仕掛けて、やつぱり防がれた。だけど部屋は丸焦げ。さすがに不味いと、二人がかりで部屋の修繕に励んだのだ。
セリナがそんなことを思い返していると、ロックが小さく笑う。
「夢に見るくらい、俺に押し倒されたかったのか?」
「ち、違うに決まっているでしょ!」
ロックの首元から垂れる鎖がシャラッと音を立てる。セリナは彼の寝間着の下に隠れたそれを、ゆっくりと引き抜いた。現れたのは、氷のように寒々しい色の宝石が目を引く首飾り。
それは、夢で自分が身につけていた首飾り。
――ほんと、なんて胸クソ悪い!
「男が寝る時までチャラチャラしたもん、着けてるんじゃないわよ」
「目障り?」
「えぇ、とっても!」
ロックごと押しのけようと肩を押すも、その手すら呆気なく掴まれてしまう。そして甲に唇が落とされた。
「悲しいこと言わないでくれ。これは俺の宝物なんだ」
「そんなのわたしの知ったことじゃ――」
そのままロックの唇が、ゆっくりと腕を伝ってくる。肩。首。耳。そして――いつの間にか目を閉じていたセリナが、そのくすぐったさに覚悟を決めた時だった。
「お戯れもその辺にしておかないと、明日に響きますよ」
いつの間に、そしてどこから現れたのか。ベッドの横に一人の若き執事あり。黒髪に黒の燕尾服の美青年。その圧力は、彼の鋭い視線のせいか。それとも有無を言わせない言葉選びのせいか。
「そういうわけで姫様。お部屋に戻りましょうか」
「……はい」
救いの船ではあるものの――その胡散臭いまでに完璧な笑顔に、セリナは|やはり(・・・)背筋が凍る思いを隠せなかった。