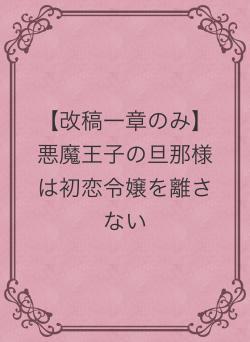「彰ー、起きてよ、彰!」
いつもの朝、砂月に揺すぶられる度に、いつもと同じ甘い香りがする。
「五分」
いつもと違うのは、俺の黒く染められた髪と、もう通い慣れた学校に行くことがない、ということ。俺達は、昨日、三年間お世話になった高校を無事に卒業した。
「嘘ばっかり!今日だけは遅刻したくないの!だって……わっ!」
俺は、そのまま砂月を、布団ごと抱きしめる。
ぽすんと体重の軽い砂月が乗っかった。
「ちょ、っと、彰!」
「ちょっとだけ」
俺は、怒られると分かってて、砂月の頬にキスを落とす。そのまま、砂月の白い首筋に顔を埋めれば、甘い香りに、もう遅刻してもいいかと真剣に思ってしまう。
「待って待って!だめっ!」
顔を真っ赤にして、バタバタと魚みたいに暴れる砂月に思わず笑った。
「笑わないで!」
「そういや、まだ、魚に憑かれた事はなかったよな」
俺は意地悪く口角を上げた。
「もうっ……意地悪」
拗ねたように怒る、なかなか砂月も可愛い。
「扉出て待ってるから」
「りょーかい」
俺が起き上がると、スウェットを脱ぎ捨てる前に、砂月がそそくさと扉を閉めた。
いつもの朝、砂月に揺すぶられる度に、いつもと同じ甘い香りがする。
「五分」
いつもと違うのは、俺の黒く染められた髪と、もう通い慣れた学校に行くことがない、ということ。俺達は、昨日、三年間お世話になった高校を無事に卒業した。
「嘘ばっかり!今日だけは遅刻したくないの!だって……わっ!」
俺は、そのまま砂月を、布団ごと抱きしめる。
ぽすんと体重の軽い砂月が乗っかった。
「ちょ、っと、彰!」
「ちょっとだけ」
俺は、怒られると分かってて、砂月の頬にキスを落とす。そのまま、砂月の白い首筋に顔を埋めれば、甘い香りに、もう遅刻してもいいかと真剣に思ってしまう。
「待って待って!だめっ!」
顔を真っ赤にして、バタバタと魚みたいに暴れる砂月に思わず笑った。
「笑わないで!」
「そういや、まだ、魚に憑かれた事はなかったよな」
俺は意地悪く口角を上げた。
「もうっ……意地悪」
拗ねたように怒る、なかなか砂月も可愛い。
「扉出て待ってるから」
「りょーかい」
俺が起き上がると、スウェットを脱ぎ捨てる前に、砂月がそそくさと扉を閉めた。