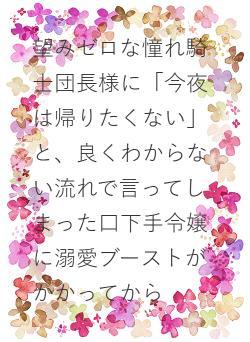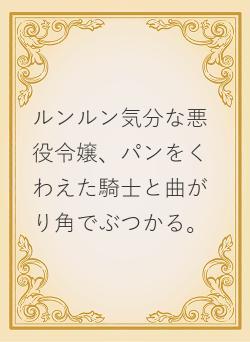◇◆◇
私がじっと息を潜めて部屋の中に閉じこもっている間に、華やかな社交期は終わりに近づき、暑い夏はすぐそこまで来ていた。
その頃になると、流石にぐちゃぐちゃな様相を呈していた心の中は大分整理が付いて片付いてはいた。
良識ある誰かに優しく話しかけられれば、きちんと会話が成立するくらいには。
「ディアーヌ」
「何処にも行きたくないし、誰にも会いたくない」
ゆったりとした寝巻き姿のままベッドに転がり、寝癖も整えていない私は憮然として言った。
いつものように私の様子を見に来てくれたラウィーニアは、仕方なさそうにふふっと笑った。部屋に入って来た彼女はいつも通りに一分の隙もない完璧な貴族令嬢で。こんな格好では何処にも行けない体たらくの無様な自分との対比を思うと、つい泣けて来る。
私がじっと息を潜めて部屋の中に閉じこもっている間に、華やかな社交期は終わりに近づき、暑い夏はすぐそこまで来ていた。
その頃になると、流石にぐちゃぐちゃな様相を呈していた心の中は大分整理が付いて片付いてはいた。
良識ある誰かに優しく話しかけられれば、きちんと会話が成立するくらいには。
「ディアーヌ」
「何処にも行きたくないし、誰にも会いたくない」
ゆったりとした寝巻き姿のままベッドに転がり、寝癖も整えていない私は憮然として言った。
いつものように私の様子を見に来てくれたラウィーニアは、仕方なさそうにふふっと笑った。部屋に入って来た彼女はいつも通りに一分の隙もない完璧な貴族令嬢で。こんな格好では何処にも行けない体たらくの無様な自分との対比を思うと、つい泣けて来る。