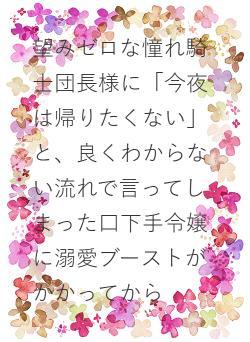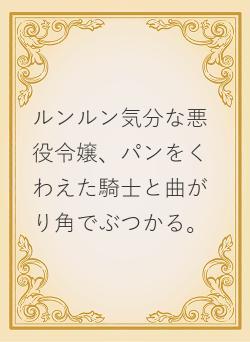「貴族が権力を持つ理由はいくつかあるけれど、良識を持ち不届き者を裁く事も含まれているわ。女性を弄び、遊び道具にするようなクズの下手な言い訳など、何ひとつ聞きたくもないわね。クレメント・ボールドウィン。これからもこの国に仕える騎士の一人で居たいなら、もう二度と、ディアーヌの前に姿を現さない事ね。もう、二度とよ。私の言葉が聞こえたかしら? もし……その何もかもが足りないお気楽な頭では、理解が不可能なら。もう一度、ゆっくり言ってあげても良いわよ」
「いいえ。申し訳ありません。ライサンダー公爵令嬢。仰せの通りに致します」
ラウィーニアは殊更優しい声で言ったのだけれど、それがプライドの高い彼には耐え難い事だったんだと思う。苦い表情で跪き一礼をして、クレメントは去って行った。
「ディアーヌ嬢……僕は……」
ランスロットは、立ち尽くす私に遠慮がちに声を掛けた。
「どうして……言ってくれなかったの!?」
「貴女を傷つけると、思った。君は、彼に恋をしていたし……ボールドウィンは、あの時まで別れる気はないと言っていた。傷つけたくはなかった」
ランスロットは、わかりにくくはあるものの。苦い顔をして、辛そうに言った。
「私。そんなに弱くないわ……それに、もっと早く言ってくれたら……」
私はそこで、言葉を止めた。そうだ。さっきの話を思い返すと、あのクレメントが私に声を掛けて来た理由はきっと、この彼。ランスロットが、私に興味を持ったからだと思う。
なんてことはない。
このところ心配していた事は、もう起こっていた。一年前の社交デビューの時に、私は既に二人の争いに巻き込まれていた。
美しいはずだった初恋はどこか遠くに奪い去られ、もう跡形もなく何も残っていない。
「いいえ。申し訳ありません。ライサンダー公爵令嬢。仰せの通りに致します」
ラウィーニアは殊更優しい声で言ったのだけれど、それがプライドの高い彼には耐え難い事だったんだと思う。苦い表情で跪き一礼をして、クレメントは去って行った。
「ディアーヌ嬢……僕は……」
ランスロットは、立ち尽くす私に遠慮がちに声を掛けた。
「どうして……言ってくれなかったの!?」
「貴女を傷つけると、思った。君は、彼に恋をしていたし……ボールドウィンは、あの時まで別れる気はないと言っていた。傷つけたくはなかった」
ランスロットは、わかりにくくはあるものの。苦い顔をして、辛そうに言った。
「私。そんなに弱くないわ……それに、もっと早く言ってくれたら……」
私はそこで、言葉を止めた。そうだ。さっきの話を思い返すと、あのクレメントが私に声を掛けて来た理由はきっと、この彼。ランスロットが、私に興味を持ったからだと思う。
なんてことはない。
このところ心配していた事は、もう起こっていた。一年前の社交デビューの時に、私は既に二人の争いに巻き込まれていた。
美しいはずだった初恋はどこか遠くに奪い去られ、もう跡形もなく何も残っていない。