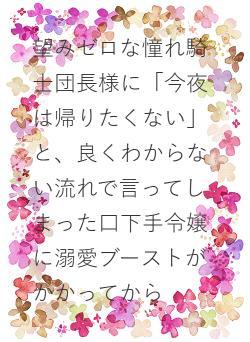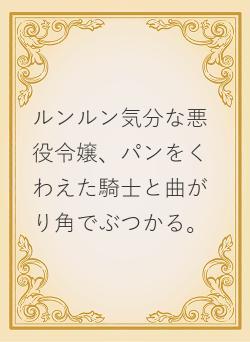姉代わりだったラウィーニアと、こうして手を繋ぐのは子どもの時以来だと思う。今思い出せるのは転んではいけないからと、庭園を手を繋いで一緒に歩いた記憶。きっとその時の他にも、彼女とは何度も何度も手を繋いでいるはずだった。
ラウィーニアだって、この状況が怖くないはずがない。というか、彼らの目的は彼女一人だ。これから、どうなってしまうのか。一番怖いのは、彼女だと思う。
巻き込まれただけの私をどうにか解放するために、知恵を絞ってくれると言ったけれど……きっと、崖のすぐ傍を歩くような危うい交渉になるだろう。
何も見えない暗闇の中で、ラウィーニアは敢えていつもと変わらないようにして私と話してくれた。
優しい温かな手のぬくもりに、忍びよる冷たい死の予感を抱かせないように。
ラウィーニアだって、この状況が怖くないはずがない。というか、彼らの目的は彼女一人だ。これから、どうなってしまうのか。一番怖いのは、彼女だと思う。
巻き込まれただけの私をどうにか解放するために、知恵を絞ってくれると言ったけれど……きっと、崖のすぐ傍を歩くような危うい交渉になるだろう。
何も見えない暗闇の中で、ラウィーニアは敢えていつもと変わらないようにして私と話してくれた。
優しい温かな手のぬくもりに、忍びよる冷たい死の予感を抱かせないように。