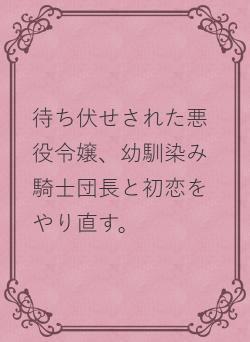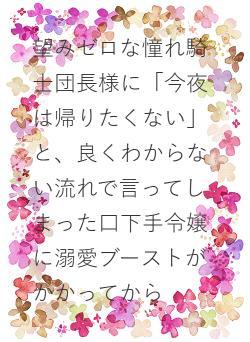人生には、キリの良い瞬間というのはたまに訪れる。振り返ると、あれこそが自分の人生の区切りだったのかと、後になってからそう思える瞬間が。
たとえば、幼い頃に両親から出された王都に残るか、それとも領地に付いていくかの二択で提示された選択肢。社交界デビューの夜会からの帰り道。
そして、初めて付き合った彼と別れ話をした、花々が咲き誇る昼下がりの庭園とか。
そろそろ三時になる事を示す鐘の音を聞いても、動き出さない自分の靴を私はじっと見つめていた。別に興味のある何かが、そこにあった訳ではない。流行の形のドレスと一緒に共布で作った、薄いピンク色のサテンで出来た靴。からからに乾いた煉瓦で出来た、赤い道。
思考は、ずっと停止したままだ。何も考えては、いられない。これからひどく傷つくだろうという事実を、簡単には受け入れたくはない。
呆気なく失恋したという重大な事実を、抱えたままではまだ動けない。心の中でせめぎ合う何かを、すべて整理しないと動き出せない気がしたし、どうにも時間の進む感覚がおかしい。
たとえば、幼い頃に両親から出された王都に残るか、それとも領地に付いていくかの二択で提示された選択肢。社交界デビューの夜会からの帰り道。
そして、初めて付き合った彼と別れ話をした、花々が咲き誇る昼下がりの庭園とか。
そろそろ三時になる事を示す鐘の音を聞いても、動き出さない自分の靴を私はじっと見つめていた。別に興味のある何かが、そこにあった訳ではない。流行の形のドレスと一緒に共布で作った、薄いピンク色のサテンで出来た靴。からからに乾いた煉瓦で出来た、赤い道。
思考は、ずっと停止したままだ。何も考えては、いられない。これからひどく傷つくだろうという事実を、簡単には受け入れたくはない。
呆気なく失恋したという重大な事実を、抱えたままではまだ動けない。心の中でせめぎ合う何かを、すべて整理しないと動き出せない気がしたし、どうにも時間の進む感覚がおかしい。