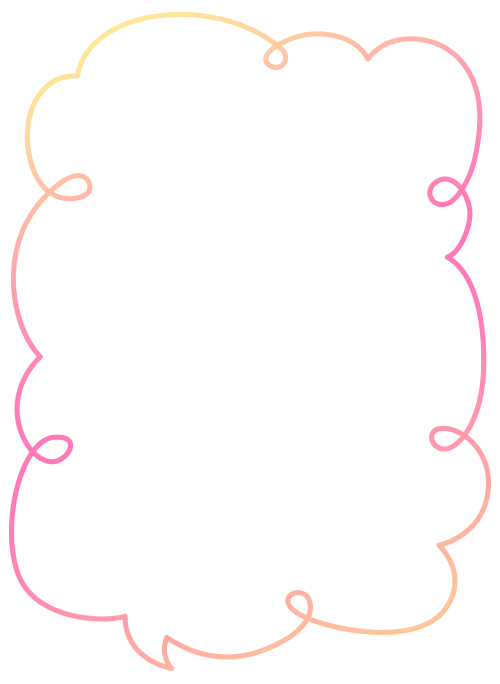翌日、目を覚ますと隣のベッドに健太郎の姿はなかった。
心のモヤモヤを吹っ切るように、いつもはしない場所の掃除や片づけをして気持ちを紛らわせた。
昼過ぎになっても健太郎は帰ってくる気配すらなく、連絡もない。
電話をしようか迷ったけどやめた。女に会って今日が休みなのもあり羽目を外したに違いない。
何度も義母に健太郎がどこにいるのか聞かれたけれど、『みーちゃんと一緒にいますよ』なんて言えるわけもない。
「少し出かけます。夕方には帰ってきますので」
なんとか平静を保とうとしたけど、私の心はもう爆発寸前だった。
義母に告げて返事を待つことなく家を出るとスマホを取り出して電話帳を開いた。
大学時代の親友の田淵薫の名前をタップしてスマホを耳に当てる。
もしも薫と連絡がつかなければ駅前のカフェでアイスコーヒーと大好きなパンケーキでも食べてゆっくり過ごして気持ちを落ち着かせよう。
カフェ代は独身時代の貯金から出す。そうすれば、健太郎にも義母にも文句を言われる筋合いはない。
3回目のコールのあと、『もしもし?』と馴染のある低い声がした。
その声を聞いただけでホッとして目頭に涙が滲む。
「もしもし、薫?あのね、聞いて欲しい話があるの」
『いいよ。どこ行けばいい?すぐ行くからもうちょっと我慢しな』
薫の心強い言葉に私はそれだけで励まされたようだった。
それぞれ住む場所の中間地点の駅で落ち合うことに決め、私は20分ほど電車に揺られて目的地を目指した。
こうやって電車に乗って出かけるのは結婚して以来だ。
この二年間、妻として嫁として生井家の家族のなれるように必死になって努力してきた。
友達と遊ぶことはおろか、一人でこうやって出かけることすらしなかった。
天国のように涼しい電車から降りて地獄のような暑さのホームに降り立ち、改札目指して歩き出す。
ICカードをタッチして改札を抜けると、そこには薫が立っていた。
自己主張の強いベリーショートの黒髪に大ぶりのピアス。
上下からし色のボタンフロントのクロップブラウスにロングスカート、それに白いサンダルというド派手ないで立ちだ。
「優花~!」
私に気付いた薫が右手を挙げてブンブンと左右と振った。
「ごめんね!待った?」
「ううん、全然。それより大丈夫?アンタ、激やせしてるけど」
歩み寄ると、薫は私を上から下まで見つめて開口一番こう言った。
心のモヤモヤを吹っ切るように、いつもはしない場所の掃除や片づけをして気持ちを紛らわせた。
昼過ぎになっても健太郎は帰ってくる気配すらなく、連絡もない。
電話をしようか迷ったけどやめた。女に会って今日が休みなのもあり羽目を外したに違いない。
何度も義母に健太郎がどこにいるのか聞かれたけれど、『みーちゃんと一緒にいますよ』なんて言えるわけもない。
「少し出かけます。夕方には帰ってきますので」
なんとか平静を保とうとしたけど、私の心はもう爆発寸前だった。
義母に告げて返事を待つことなく家を出るとスマホを取り出して電話帳を開いた。
大学時代の親友の田淵薫の名前をタップしてスマホを耳に当てる。
もしも薫と連絡がつかなければ駅前のカフェでアイスコーヒーと大好きなパンケーキでも食べてゆっくり過ごして気持ちを落ち着かせよう。
カフェ代は独身時代の貯金から出す。そうすれば、健太郎にも義母にも文句を言われる筋合いはない。
3回目のコールのあと、『もしもし?』と馴染のある低い声がした。
その声を聞いただけでホッとして目頭に涙が滲む。
「もしもし、薫?あのね、聞いて欲しい話があるの」
『いいよ。どこ行けばいい?すぐ行くからもうちょっと我慢しな』
薫の心強い言葉に私はそれだけで励まされたようだった。
それぞれ住む場所の中間地点の駅で落ち合うことに決め、私は20分ほど電車に揺られて目的地を目指した。
こうやって電車に乗って出かけるのは結婚して以来だ。
この二年間、妻として嫁として生井家の家族のなれるように必死になって努力してきた。
友達と遊ぶことはおろか、一人でこうやって出かけることすらしなかった。
天国のように涼しい電車から降りて地獄のような暑さのホームに降り立ち、改札目指して歩き出す。
ICカードをタッチして改札を抜けると、そこには薫が立っていた。
自己主張の強いベリーショートの黒髪に大ぶりのピアス。
上下からし色のボタンフロントのクロップブラウスにロングスカート、それに白いサンダルというド派手ないで立ちだ。
「優花~!」
私に気付いた薫が右手を挙げてブンブンと左右と振った。
「ごめんね!待った?」
「ううん、全然。それより大丈夫?アンタ、激やせしてるけど」
歩み寄ると、薫は私を上から下まで見つめて開口一番こう言った。