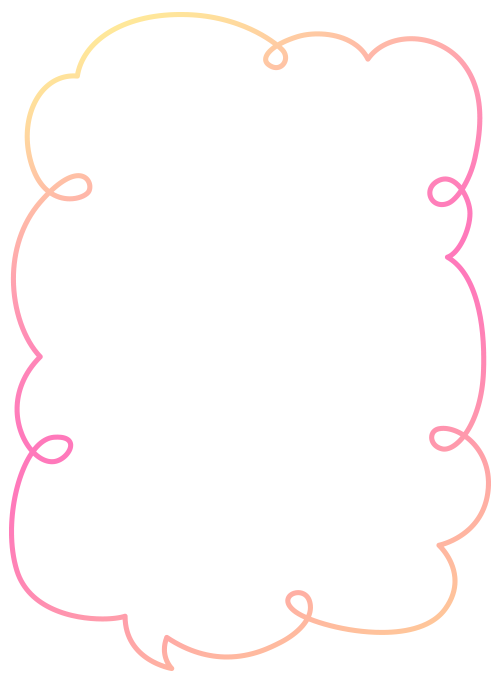「また具合悪いのかよ。最近、多いよな」
食事を終えて部屋に入ってきた健太郎の声は露骨に不機嫌そうだった。
「ごめん。少し休んだら、食器とか片付けるから」
「夏だし洗い物放置してると虫わくじゃん。早めにやれよ」
――だったら今日ぐらい洗い物を代りにやってくれてもいいじゃない。
「……わかった」
喉元まで出かかった言葉をグッと飲み込んだ瞬間、健太郎のスマホが音を立てて鳴りだした。
画面に視線を向けた健太郎がわずかに動揺した。
「あっ、友達。ちょっと出るわ」
そう言うと、慌てて部屋を出て行った。
きっと私に知られたくない人からの電話なんだろう。
健太郎に女の影を感じたのは、この前が初めてではない。
帰りの遅い日、何度か女性ものの香水の匂いを漂わせて帰ってきたことがあった。
ある日はYシャツにピンク色の口紅がついていたこともある。
付き合いでいった飲み屋の女性がつけたんだって健太郎はしれっと言ってのけたけど、きっと違う。
……私はずっとその事実から目を逸らしてきた。
気付かないようにと鈍感な振りをしていたのだ。
知ってしまえば、この結婚生活は破綻することがはっきりしていたから。
でも、このままではいけないという思いが私を突き動かす。
そろりとベッドから足を下ろし、音を立てないように部屋の扉を開ける。
なぜか急に怖くなって怖気づきそうになる気持ちを必死に奮い立たせる。
ここで目を逸らしたらまた同じことの繰り返しだ。
いつかはこの現実を直視しなくてはいけない。
廊下の奥で健太郎は声を押し殺しながらも堂々と話していた。
「えっ、そうなの?じゃあ、行こうよ。こんなチャンスないしさ」
優しく穏やかな口調だった。
私以外の人とはこんな風に話すんだね……。
「全然大丈夫だよ。今、嫁具合悪いらしいからちょうどいいよ」
疑惑が確信に変わる。私が具合が悪いからなに?
「みーちゃんの浴衣姿、楽しみすぎるんだけど。絶対可愛いから早く脱がせたくなっちゃうかもよ?」
――みーちゃん?
声が漏れそうになり、慌てて口元を覆う。
食事を終えて部屋に入ってきた健太郎の声は露骨に不機嫌そうだった。
「ごめん。少し休んだら、食器とか片付けるから」
「夏だし洗い物放置してると虫わくじゃん。早めにやれよ」
――だったら今日ぐらい洗い物を代りにやってくれてもいいじゃない。
「……わかった」
喉元まで出かかった言葉をグッと飲み込んだ瞬間、健太郎のスマホが音を立てて鳴りだした。
画面に視線を向けた健太郎がわずかに動揺した。
「あっ、友達。ちょっと出るわ」
そう言うと、慌てて部屋を出て行った。
きっと私に知られたくない人からの電話なんだろう。
健太郎に女の影を感じたのは、この前が初めてではない。
帰りの遅い日、何度か女性ものの香水の匂いを漂わせて帰ってきたことがあった。
ある日はYシャツにピンク色の口紅がついていたこともある。
付き合いでいった飲み屋の女性がつけたんだって健太郎はしれっと言ってのけたけど、きっと違う。
……私はずっとその事実から目を逸らしてきた。
気付かないようにと鈍感な振りをしていたのだ。
知ってしまえば、この結婚生活は破綻することがはっきりしていたから。
でも、このままではいけないという思いが私を突き動かす。
そろりとベッドから足を下ろし、音を立てないように部屋の扉を開ける。
なぜか急に怖くなって怖気づきそうになる気持ちを必死に奮い立たせる。
ここで目を逸らしたらまた同じことの繰り返しだ。
いつかはこの現実を直視しなくてはいけない。
廊下の奥で健太郎は声を押し殺しながらも堂々と話していた。
「えっ、そうなの?じゃあ、行こうよ。こんなチャンスないしさ」
優しく穏やかな口調だった。
私以外の人とはこんな風に話すんだね……。
「全然大丈夫だよ。今、嫁具合悪いらしいからちょうどいいよ」
疑惑が確信に変わる。私が具合が悪いからなに?
「みーちゃんの浴衣姿、楽しみすぎるんだけど。絶対可愛いから早く脱がせたくなっちゃうかもよ?」
――みーちゃん?
声が漏れそうになり、慌てて口元を覆う。