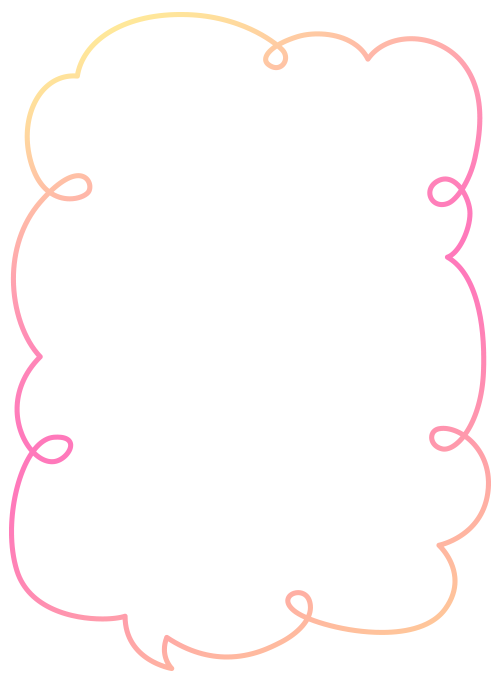「ご馳走様でした」
そう言ったタイミングでフクが瀬戸さんの膝から降りて大きく伸びをした。
「にゃ~ん」
「え、フク?」
今度は私の膝の上に座り毛づくろいを始めるフク。
「フク、生井さんだよ。ちゃんと覚えるんだよ?」
瀬戸さんの言葉なんて知らんぷりで、膝に座って私の手をぺろぺろ舐めるフク。
ざらざらとした舌の感触が痛いぐらいだ。
「フクちゃん……可愛い」
そっとフクちゃんの頭を撫でると、気持ちよさそうにうっとり目をつぶる。
そうだ……。私、子供のころからずっと猫を飼いたかったんだ。
もう何十年前のことだから、すっかり忘れていた。
「そういえばフクちゃんはいつから瀬戸さんのおうちに?」
「5年前に近くの公園で段ボールに入れられて捨てられてたんです。他の子達はもう亡くなっていて、生きていたのがフクだけだったんです」
「そんなことが……」
「だから、家に連れてかえってフクと名付けて一緒に暮らし始めました」
「瀬戸さんと家族になれてフクちゃんは幸せですね。今もこんなに嬉しそうに喉をゴロゴロ鳴らしてる」
「実はフクって案外人見知りするんです。こんな風に膝の上でゴロゴロいうのは生井さんを好きな証です」
「それは嬉しいな」
膝の上のフクは香箱座りで気持ちよさそうに目をつぶる。
――ねぇ、フク。ありがとう。
あと少しだけ、このままでいて。
そうすれば私はあなたを理由にまだこの家に……瀬戸さんとフクと一緒に穏やかな時間を過ごすことができるから――。
そう言ったタイミングでフクが瀬戸さんの膝から降りて大きく伸びをした。
「にゃ~ん」
「え、フク?」
今度は私の膝の上に座り毛づくろいを始めるフク。
「フク、生井さんだよ。ちゃんと覚えるんだよ?」
瀬戸さんの言葉なんて知らんぷりで、膝に座って私の手をぺろぺろ舐めるフク。
ざらざらとした舌の感触が痛いぐらいだ。
「フクちゃん……可愛い」
そっとフクちゃんの頭を撫でると、気持ちよさそうにうっとり目をつぶる。
そうだ……。私、子供のころからずっと猫を飼いたかったんだ。
もう何十年前のことだから、すっかり忘れていた。
「そういえばフクちゃんはいつから瀬戸さんのおうちに?」
「5年前に近くの公園で段ボールに入れられて捨てられてたんです。他の子達はもう亡くなっていて、生きていたのがフクだけだったんです」
「そんなことが……」
「だから、家に連れてかえってフクと名付けて一緒に暮らし始めました」
「瀬戸さんと家族になれてフクちゃんは幸せですね。今もこんなに嬉しそうに喉をゴロゴロ鳴らしてる」
「実はフクって案外人見知りするんです。こんな風に膝の上でゴロゴロいうのは生井さんを好きな証です」
「それは嬉しいな」
膝の上のフクは香箱座りで気持ちよさそうに目をつぶる。
――ねぇ、フク。ありがとう。
あと少しだけ、このままでいて。
そうすれば私はあなたを理由にまだこの家に……瀬戸さんとフクと一緒に穏やかな時間を過ごすことができるから――。