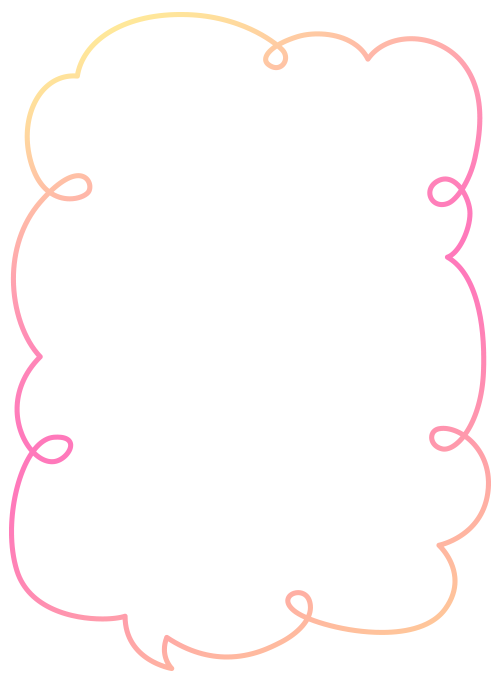「でも、お仕事の邪魔になりませんか?作家さんのことはよく分からないんですが、集中が途切れてしまったりとかしたら申し訳なくて」
「それなら大丈夫です。編集さんにもできる限り人と交流するように言われているので」
「人と交流?」
「俺の小説、感情がこもってないらしくて」
瀬戸さんは少し困ったように視線をテーブルに落とした。
「登場人物が淡々とし過ぎてるからもっと人間臭くしろって言われてるんです」
「なんだか難しいですね」
「ね。いまだに模索中です。作家とはいえ、俺はまだ売れない作家なので時間もたっぷりありますし。いつでも遊びに来てください」
その言葉を真に受けていつでも行くことなどできるはずもない。
私は主婦で、瀬戸さんは作家なのだ。
でも、きっと瀬戸さんは知らない。
私が結婚していることを。主婦だということを。
薬指にはめていた結婚指輪は、結婚してからひどく痩せてしまったせいではめてもすぐに落ちてしまう。
だから、もう付けていない。
シャインマスカットを食べ終えた頃には火照っていた体は冷え、少し休んだことで体力も回復した。
長居は無用だ。それぐらいわきまえている。
「そろそろ……。来週の月曜日に伺いますね」
「はい。待ってます」
私はにこりと笑いながら彼を欺く。
結婚していると知れば、きっと瀬戸さんは私を家へ招き入れてくれることはなくなるだろう。
近所の主婦を真昼間に家に通して二人っきりで過ごしているなどと知られれば、体裁も良くない。
『聞かれていないからわざわざ言わなかっただけ』と私は自分自身に必死になって言い訳を繰り返す。
二人っきりで過ごしているけど、私と瀬戸さんの間には何もない。
ただ一緒に美味しい物を食べて、言葉を交わしているだけ。ただ、それだけ。
「それなら大丈夫です。編集さんにもできる限り人と交流するように言われているので」
「人と交流?」
「俺の小説、感情がこもってないらしくて」
瀬戸さんは少し困ったように視線をテーブルに落とした。
「登場人物が淡々とし過ぎてるからもっと人間臭くしろって言われてるんです」
「なんだか難しいですね」
「ね。いまだに模索中です。作家とはいえ、俺はまだ売れない作家なので時間もたっぷりありますし。いつでも遊びに来てください」
その言葉を真に受けていつでも行くことなどできるはずもない。
私は主婦で、瀬戸さんは作家なのだ。
でも、きっと瀬戸さんは知らない。
私が結婚していることを。主婦だということを。
薬指にはめていた結婚指輪は、結婚してからひどく痩せてしまったせいではめてもすぐに落ちてしまう。
だから、もう付けていない。
シャインマスカットを食べ終えた頃には火照っていた体は冷え、少し休んだことで体力も回復した。
長居は無用だ。それぐらいわきまえている。
「そろそろ……。来週の月曜日に伺いますね」
「はい。待ってます」
私はにこりと笑いながら彼を欺く。
結婚していると知れば、きっと瀬戸さんは私を家へ招き入れてくれることはなくなるだろう。
近所の主婦を真昼間に家に通して二人っきりで過ごしているなどと知られれば、体裁も良くない。
『聞かれていないからわざわざ言わなかっただけ』と私は自分自身に必死になって言い訳を繰り返す。
二人っきりで過ごしているけど、私と瀬戸さんの間には何もない。
ただ一緒に美味しい物を食べて、言葉を交わしているだけ。ただ、それだけ。