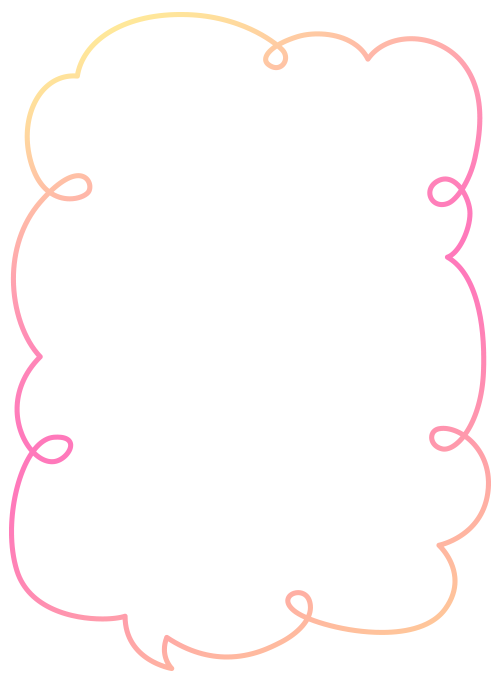「ちょっと休もう……」
フラフラッとして屋根付きのベンチで休憩しようとすると、そこにはすでに先客がいた。
「――大丈夫ですか?」
座っていたのは私と同い年ぐらいの男性だった。
「あっ、はい……」
「ここ、どうぞ」
私の異変に気付いた男性が弾かれたように立ち上がりベンチを譲ってくれた。
私は返事をすることもできずベンチに座り、だらりと体を横たえた。
「す、すみません……。少しだけこうさせてください……」
私の言葉を聞くと、男性がどこかへ駆けていく。
ザッザッザッと砂を蹴るような音が遠ざかっていく。
私はそのまま目をつぶりありがたく休ませてもらうことにした。
「ん……?」
数分後、今度は足音がどんどん近付いてくる。
ゆっくりと瞼を開くと、そこにいたのは先ほどの男性だった。
「これで首元を冷やしてください」
彼はそう言うと、私に冷えたペットボトルを握らせて首元にあてがった。
ひんやりと冷たい首元の感覚が心地よく体の熱を奪っていく。
「熱中症かもしれないですね。顔が真っ赤ですよ。今日は特に暑いから」
「ご迷惑をおかしてすみません……」
「いえ」
しばらく首元を冷やしながら横になっていると、症状が回復してきた。
その間も男性は私の顔回りを厚みのある茶色い封筒でパタパタと仰いでくれていた。
男性の献身的な看病のおかげでようやく起き上がれそうな兆しが見えた。
「すみませんでした」
起き上がって頭を下げると、男性は「もう一本買ってきたのでよかったら」と私にスポーツドリンクを差し出した。
「本当にありがとうございます」
お礼を言いながらペットボトルを受け取りキャップを空けようとしたものの、うまく力がこもらず開けることができない。
困っていると男性がスッと手を差し出して代りに開けてくれた。
「ありがとうございます」
ごくごくと喉の奥に流し込むと、カラカラに乾いていた喉が潤った。
こんなに美味しいスポーツドリンクは初めてだ。喉を鳴らしながら私は一気飲みしてしまった。
フラフラッとして屋根付きのベンチで休憩しようとすると、そこにはすでに先客がいた。
「――大丈夫ですか?」
座っていたのは私と同い年ぐらいの男性だった。
「あっ、はい……」
「ここ、どうぞ」
私の異変に気付いた男性が弾かれたように立ち上がりベンチを譲ってくれた。
私は返事をすることもできずベンチに座り、だらりと体を横たえた。
「す、すみません……。少しだけこうさせてください……」
私の言葉を聞くと、男性がどこかへ駆けていく。
ザッザッザッと砂を蹴るような音が遠ざかっていく。
私はそのまま目をつぶりありがたく休ませてもらうことにした。
「ん……?」
数分後、今度は足音がどんどん近付いてくる。
ゆっくりと瞼を開くと、そこにいたのは先ほどの男性だった。
「これで首元を冷やしてください」
彼はそう言うと、私に冷えたペットボトルを握らせて首元にあてがった。
ひんやりと冷たい首元の感覚が心地よく体の熱を奪っていく。
「熱中症かもしれないですね。顔が真っ赤ですよ。今日は特に暑いから」
「ご迷惑をおかしてすみません……」
「いえ」
しばらく首元を冷やしながら横になっていると、症状が回復してきた。
その間も男性は私の顔回りを厚みのある茶色い封筒でパタパタと仰いでくれていた。
男性の献身的な看病のおかげでようやく起き上がれそうな兆しが見えた。
「すみませんでした」
起き上がって頭を下げると、男性は「もう一本買ってきたのでよかったら」と私にスポーツドリンクを差し出した。
「本当にありがとうございます」
お礼を言いながらペットボトルを受け取りキャップを空けようとしたものの、うまく力がこもらず開けることができない。
困っていると男性がスッと手を差し出して代りに開けてくれた。
「ありがとうございます」
ごくごくと喉の奥に流し込むと、カラカラに乾いていた喉が潤った。
こんなに美味しいスポーツドリンクは初めてだ。喉を鳴らしながら私は一気飲みしてしまった。