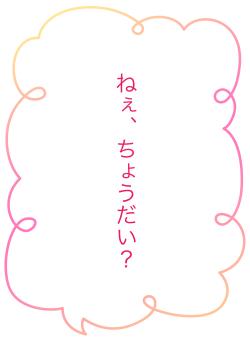その光景を見ていると、私のお腹の底から、黒い何かが溢れてきた。
…そんなに榛名先輩とベタベタしないで。
そんな風に思ったことに、私自身が驚いた。
もう2人のやり取りを見ていられなくてうつむいていると、
「あれ、小桃ちゃん?」
と言う声がして私は顔を上げた。
「桐生先輩…」
「あ、もしかして朔空?…おーい、さ…」
「あ、い、いいです!…呼ばなくて、大丈夫です」
榛名先輩を呼ぼうとした桐生先輩に、慌ててそう言った。
「えっ、いいの?」
「はい。…あ、じゃあこれ榛名先輩に渡してもらえますか?」
と、私はこの前涙を拭いてくれた先輩のハンカチを桐生先輩に渡した。
「うん、それは全然いいんだけど…」
「ありがとうございます!…では」
私は桐生先輩に笑顔を作って礼をして、その場から走って立ち去った。
…あのままあそこにいたら、私は泣いていたかもしれない。
先輩が人気者だってことは、ちゃんとわかってた。
でも、あんなにベタベタ触られてもまんざらでもない様に見えた先輩。
保健室で一緒に寝るようになって、先輩にとって私は少しでも特別な存在だろうと思った私が恥ずかしい。
…あぁ、そうか。
先輩に対して思うこの気持ち。
これって、たぶんヤキモチだ。
私ーー…、榛名先輩が好きなんだ。