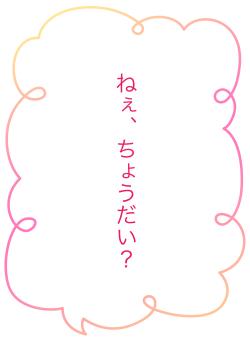すると、休憩スペースの方から声がした。
「…あ、やっと来た」
私はその言葉に、思わず立ち止まった。
もうすぐ昼休みが終わるので、私の周りには彼以外誰もいない。
ということは、彼の目には私以外誰も写っていない。
だから、さっきの言葉は私にかけられたもの。
…私のことを待ってたの?
足音がこちらに近づいてくる。
私は、彼の方に顔を向けないまま、その場に固まっていた。
私のすぐ横で、足音がピタリとやんだ。
「あのさ」
私は、動けない。
言葉も、返せない。
私は今まで、彼と話したことなんて、本当に片手で数えられるほど。
それなのに、何を言われるのだろう。
彼からの視線を感じ、私の顔は少しずつ赤く染まっていった。
少し、間が空いた。
彼の方を見れないから、彼が今、どんな表情をしているのかもわからない。
恥ずかしさと緊張で、逃げ出してしまおうかと思ったその時。
彼が私に顔を近づけてきて、
「俺…キミのことが好きなんだ」
と、私の耳にささやいた。