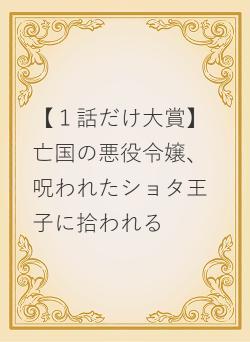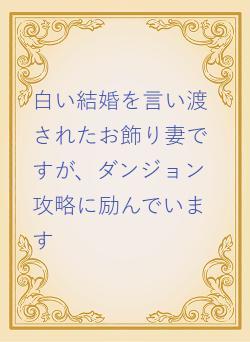帰り道の途中で命の灯が消えようとしている猫の気配を察知したシャドウが、わたしの体を突き動かしたのだ。
そしてその猫のそばまで移動すると、シャドウの意志で依り代をわたしからその猫へと移したということになる。
この猫を助けるために……?
シャドウ、あなたって何ていい子に育ったの!
そう感動していられたのはほんの一瞬で、大変なことが起きた。
シャドウが憑いた猫が苦しみ悶え始めたのだ。
早くこの怪我を治してあげないといけない。
大丈夫。
わたしは聖女隊に憧れていた白魔導士だもの。出来るわ。
手をぎゅっと握って震えを抑えると、暴れる体を持ち上げて抱きしめ、癒しの魔法で包み込む。
しかしシャドウが乗り移った猫の体からは黒いオーラのようなものが溢れ出てきて、わたしの腕をチリリと焼き始めた。
まずい。
シャドウが痛みと苦しみで我を忘れて闇に染まろうとしている。
どうしようかと焦り始めたところで、後ろからふわりと包み込まれた。
「リナリィ、落ち着け。癒しと浄化の魔法を流し続けろ。俺も手伝うから」
わたしのことをずっと「きみ」としか呼んでくれなかったのに「リナリィ」と親し気に呼んで、いつも一人称は「私」だったはずなのに「俺」と言っている。
こんなハインツ先生なんて――いや、知っている。
いつもわたしと二人っきりのときはそうだったじゃないか。
なんで忘れていたんだろう。
この人は……ハインツ・エルシードはわたしの最愛の夫だ。
そしてその猫のそばまで移動すると、シャドウの意志で依り代をわたしからその猫へと移したということになる。
この猫を助けるために……?
シャドウ、あなたって何ていい子に育ったの!
そう感動していられたのはほんの一瞬で、大変なことが起きた。
シャドウが憑いた猫が苦しみ悶え始めたのだ。
早くこの怪我を治してあげないといけない。
大丈夫。
わたしは聖女隊に憧れていた白魔導士だもの。出来るわ。
手をぎゅっと握って震えを抑えると、暴れる体を持ち上げて抱きしめ、癒しの魔法で包み込む。
しかしシャドウが乗り移った猫の体からは黒いオーラのようなものが溢れ出てきて、わたしの腕をチリリと焼き始めた。
まずい。
シャドウが痛みと苦しみで我を忘れて闇に染まろうとしている。
どうしようかと焦り始めたところで、後ろからふわりと包み込まれた。
「リナリィ、落ち着け。癒しと浄化の魔法を流し続けろ。俺も手伝うから」
わたしのことをずっと「きみ」としか呼んでくれなかったのに「リナリィ」と親し気に呼んで、いつも一人称は「私」だったはずなのに「俺」と言っている。
こんなハインツ先生なんて――いや、知っている。
いつもわたしと二人っきりのときはそうだったじゃないか。
なんで忘れていたんだろう。
この人は……ハインツ・エルシードはわたしの最愛の夫だ。