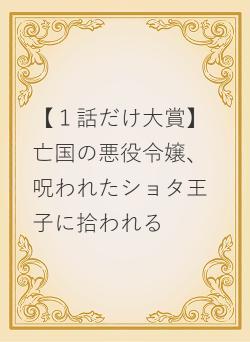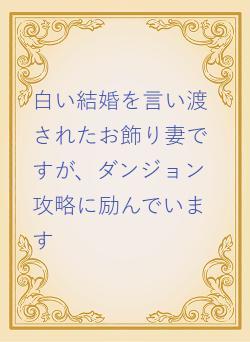シャドウがわたしの中で暴れていた。
馬車が止まると、まるで操られているかのように自分の意志に関係なく腕が扉へと伸びロックを外すと、わたしの体は飛び出すように馬車から転がり落ちた。
「どうした! 大丈夫かっ」
背後からハインツ先生の焦った声が聞こえるが、それを無視してわたしは体を起こし、馬車道の脇の草むらへと入っていく。
シャドウ待って!
あっちこっち擦り剝いてて痛いんですけど!
しかしシャドウは止まってくれない。
まっすぐにある方向へと向かっていき、ようやく足を止めたそこには――猫らしき生き物が横たわっていた。
追いついたハインツ先生が魔法で光を照らすと、茶色の猫が両後ろ足に大怪我を負っているのがわかった。
足があり得ない方向へと曲がっていて、骨が飛び出している箇所があり出血も酷い。
今夜はお祭りで夜の馬車の往来が普段よりも多かったから、きっと車輪に轢かれてしまったのだろう。
猫はぎゅっと目を瞑ったままで、もしかするともう息絶えているのかもしれない状態だった。
しゃがんで震える手をそっとその猫に伸ばした時だった。
わたしの指先から黒い影がするりと抜けるような感触がして、猫の体が大きくビクンと跳ねた。
「依り代を移したのか」
ハインツ先生の言葉で何が起きたのかようやく理解した。
馬車が止まると、まるで操られているかのように自分の意志に関係なく腕が扉へと伸びロックを外すと、わたしの体は飛び出すように馬車から転がり落ちた。
「どうした! 大丈夫かっ」
背後からハインツ先生の焦った声が聞こえるが、それを無視してわたしは体を起こし、馬車道の脇の草むらへと入っていく。
シャドウ待って!
あっちこっち擦り剝いてて痛いんですけど!
しかしシャドウは止まってくれない。
まっすぐにある方向へと向かっていき、ようやく足を止めたそこには――猫らしき生き物が横たわっていた。
追いついたハインツ先生が魔法で光を照らすと、茶色の猫が両後ろ足に大怪我を負っているのがわかった。
足があり得ない方向へと曲がっていて、骨が飛び出している箇所があり出血も酷い。
今夜はお祭りで夜の馬車の往来が普段よりも多かったから、きっと車輪に轢かれてしまったのだろう。
猫はぎゅっと目を瞑ったままで、もしかするともう息絶えているのかもしれない状態だった。
しゃがんで震える手をそっとその猫に伸ばした時だった。
わたしの指先から黒い影がするりと抜けるような感触がして、猫の体が大きくビクンと跳ねた。
「依り代を移したのか」
ハインツ先生の言葉で何が起きたのかようやく理解した。