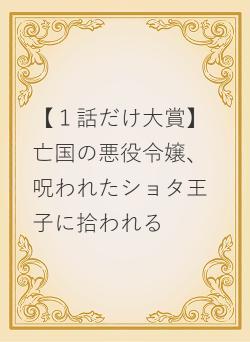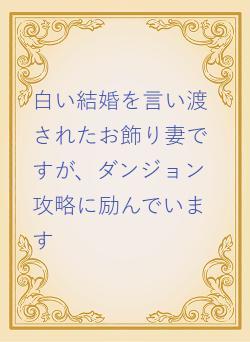「先生は感動が薄すぎます。それではシャドウの情操教育上よろしくないですわ」
「急に熱心な教師のようになったな、どうした」
「どうしたもこうしたも、わたしはシャドウを綺麗な心の子に育てたいんです。綺麗なものを見て感動したり、可愛い物を愛でたり豊かな心をですねえ…って、聞いてます?」
ハインツ先生は無言でサンドイッチを次から次へと食べている。
ランチは毎朝わたしと母がハインツ先生の分も作って持参していて、今日のローストチキンとレタスのサンドイッチももちろん手作りだ。
どうやら気に入ってくれたらしい。
わたしとシャドウが感動を共有できたのならもうそれでいいかと諦めて、虹が徐々に消えゆくのを名残惜しく眺めながらサンドイッチを頬張った。
粗方食べ終えたところでガサガサという音が聞こえて、ベンチの脇の丸く刈られた植栽から灰色の猫が顔を出した。
養成学校に居ついて学生たちからおこぼれをもらって暮らしている猫がいるという話を耳にしたことがあったが、それがこの猫だろうか。
あと一口となったサンドイッチの端にマスタードがついていないことを確認する。
「食べる?」
上半身を折り曲げて差し出すと、その猫がタタっと小走りでやって来てパクリと食べた。
「可愛いっ!」
「餌付け禁止だと掲示板に書いてあった気がするんだが」
まったくこの人は、堅物なんだから。
集団生活のルールは厳守しなければならない。
それでも猫が可愛いからみんなついつい餌をあげてしまうのだろう。
そのジレンマをどう解決しようか、むうっと唇を尖らせながら考えていると、猫がわたしの足元で前足をクイクイ動かしていることに気づいた。
そこにはわたしの影のほかに、わたしの肩に乗るシャドウの影もあって、どうやらこの猫はシャドウの存在がわかっているようだった。
「急に熱心な教師のようになったな、どうした」
「どうしたもこうしたも、わたしはシャドウを綺麗な心の子に育てたいんです。綺麗なものを見て感動したり、可愛い物を愛でたり豊かな心をですねえ…って、聞いてます?」
ハインツ先生は無言でサンドイッチを次から次へと食べている。
ランチは毎朝わたしと母がハインツ先生の分も作って持参していて、今日のローストチキンとレタスのサンドイッチももちろん手作りだ。
どうやら気に入ってくれたらしい。
わたしとシャドウが感動を共有できたのならもうそれでいいかと諦めて、虹が徐々に消えゆくのを名残惜しく眺めながらサンドイッチを頬張った。
粗方食べ終えたところでガサガサという音が聞こえて、ベンチの脇の丸く刈られた植栽から灰色の猫が顔を出した。
養成学校に居ついて学生たちからおこぼれをもらって暮らしている猫がいるという話を耳にしたことがあったが、それがこの猫だろうか。
あと一口となったサンドイッチの端にマスタードがついていないことを確認する。
「食べる?」
上半身を折り曲げて差し出すと、その猫がタタっと小走りでやって来てパクリと食べた。
「可愛いっ!」
「餌付け禁止だと掲示板に書いてあった気がするんだが」
まったくこの人は、堅物なんだから。
集団生活のルールは厳守しなければならない。
それでも猫が可愛いからみんなついつい餌をあげてしまうのだろう。
そのジレンマをどう解決しようか、むうっと唇を尖らせながら考えていると、猫がわたしの足元で前足をクイクイ動かしていることに気づいた。
そこにはわたしの影のほかに、わたしの肩に乗るシャドウの影もあって、どうやらこの猫はシャドウの存在がわかっているようだった。