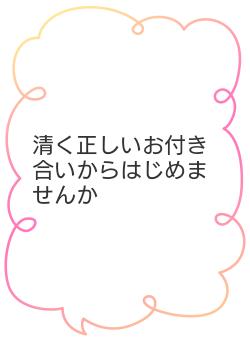「雷の時は車内が一番安全だっていうし、大丈夫だよ」
誠一に促されるまま彼の車の助手席に乗り理香は戸惑う。
「理香は雷嫌いだったもんな」
そんなこと覚えていてくれたのか。
理香の胸の奥がぎゅうと軋んで痛みを伝える。
子供みたいにくしゃりと笑う誠一の髪はすっかり雨にぬれて、雫がぽたりと頬を伝って流れ落ちた。
額に貼り付く前髪を掻き上げるその横顔に思わず見惚れてしまう自分がいて、理香はその邪な気持ちを振り払うように目を背ける。
ドキドキと理香の心臓が早鐘を打っていた。
誠一への気持ちは徐々に思い出のようになって薄れていっていると思ったのに、まだこんなにも自分は未練がましく彼のことが好きなのかと、いやでも自覚してしまう。
「……あ、あの、私、歩いて帰れます。大丈夫です」
「雷鳴ってるのに?」
「だ、大丈夫です」
本当は怖かったけれど、このままここにいるのとどちらが怖いかはわからなかった。
自分の心がぐらぐらと揺れて、どうしようもないものに呑み込まれてしまいそうで、そちらのほうが恐ろしく思える。
また遠くで響く雷鳴にわかりやすくビクッと身を震わせる理香に、誠一は微苦笑を浮かべながら優しくぽんぽんと頭を撫でた。
「通り道だから。可愛い後輩に何かあったら俺が心配だし。送られてって」
相変わらずズルい人だと理香は思った。
「……ありがとう、……ございます……」
そういう言い方をされたら断りずらい。
誠一に促されるまま彼の車の助手席に乗り理香は戸惑う。
「理香は雷嫌いだったもんな」
そんなこと覚えていてくれたのか。
理香の胸の奥がぎゅうと軋んで痛みを伝える。
子供みたいにくしゃりと笑う誠一の髪はすっかり雨にぬれて、雫がぽたりと頬を伝って流れ落ちた。
額に貼り付く前髪を掻き上げるその横顔に思わず見惚れてしまう自分がいて、理香はその邪な気持ちを振り払うように目を背ける。
ドキドキと理香の心臓が早鐘を打っていた。
誠一への気持ちは徐々に思い出のようになって薄れていっていると思ったのに、まだこんなにも自分は未練がましく彼のことが好きなのかと、いやでも自覚してしまう。
「……あ、あの、私、歩いて帰れます。大丈夫です」
「雷鳴ってるのに?」
「だ、大丈夫です」
本当は怖かったけれど、このままここにいるのとどちらが怖いかはわからなかった。
自分の心がぐらぐらと揺れて、どうしようもないものに呑み込まれてしまいそうで、そちらのほうが恐ろしく思える。
また遠くで響く雷鳴にわかりやすくビクッと身を震わせる理香に、誠一は微苦笑を浮かべながら優しくぽんぽんと頭を撫でた。
「通り道だから。可愛い後輩に何かあったら俺が心配だし。送られてって」
相変わらずズルい人だと理香は思った。
「……ありがとう、……ございます……」
そういう言い方をされたら断りずらい。