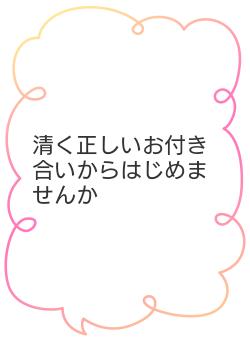「理香さん」
ノックの音が聞こえて、小さく返事をすればすぐにドアが開いた。
「ごはんできましたよ」
やってきたのは、後輩の悠太だ。社会人になりたての彼はまだ笑うと少し幼く見える。
「ありがと……」
悠太とは大学のサークル仲間でずっと友達だった。彼には自然と甘えることができる。
悠太は理香のこの拗れた恋愛の全部を知っているのに、理香を好きだと言ってくれた。
その悠太の気持ちに応えられないと理香が言ってもそれでもいいと言って、ただ優しく無条件に理香を甘やかす。
そうしたいのだと、言ってそうするのだ。
今日のように時々家にきては理香に尽くしてくれる。
「ほら、いきましょ?ごはん、冷めちゃいますよ」
理香の手を引いて笑いかける彼に罪悪感もあるのに、どこか嬉しい自分が嫌だった。
悠太を利用している。
気持ちに応えられないくせに、こうやって甘えるのがいかに残酷なことなのか。
悠太に手を握られると、彼の手を思い出した。大きくと骨張った彼の手。
悠太よりも彼は大きくて、手を繋がれた時は少し視線が上に上がった。
こんな時に悠太に彼を重ねるなんて。救い難い馬鹿だ。
「今日は理香さんの好きなハンバーグ作ったんです。結構上手くできたと思うんですよ」
無邪気に笑いかけてくれる悠太を見ると、鼻の奥がツンとした。
ノックの音が聞こえて、小さく返事をすればすぐにドアが開いた。
「ごはんできましたよ」
やってきたのは、後輩の悠太だ。社会人になりたての彼はまだ笑うと少し幼く見える。
「ありがと……」
悠太とは大学のサークル仲間でずっと友達だった。彼には自然と甘えることができる。
悠太は理香のこの拗れた恋愛の全部を知っているのに、理香を好きだと言ってくれた。
その悠太の気持ちに応えられないと理香が言ってもそれでもいいと言って、ただ優しく無条件に理香を甘やかす。
そうしたいのだと、言ってそうするのだ。
今日のように時々家にきては理香に尽くしてくれる。
「ほら、いきましょ?ごはん、冷めちゃいますよ」
理香の手を引いて笑いかける彼に罪悪感もあるのに、どこか嬉しい自分が嫌だった。
悠太を利用している。
気持ちに応えられないくせに、こうやって甘えるのがいかに残酷なことなのか。
悠太に手を握られると、彼の手を思い出した。大きくと骨張った彼の手。
悠太よりも彼は大きくて、手を繋がれた時は少し視線が上に上がった。
こんな時に悠太に彼を重ねるなんて。救い難い馬鹿だ。
「今日は理香さんの好きなハンバーグ作ったんです。結構上手くできたと思うんですよ」
無邪気に笑いかけてくれる悠太を見ると、鼻の奥がツンとした。