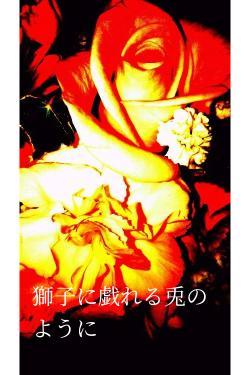―出産から三ヶ月―
夜、美梨はソファーに座ったまま携帯電話で何やら遊んでいるようだった。修は昂幸と風呂上がりの髪を拭きながら美梨に近付く。
「お母ちゃん、何してるの? あーー、お母ちゃんがゲームしてる」
「昂幸、修にバラさないで。優が寝てるからちょっと休憩していただけだよ」
修は缶ビールを持ち美梨に近付き、昂幸と一緒に携帯電話の画面を覗き込む。
「ほら、昂幸はもう歯磨きすんだの? 修に仕上げしてもらった? お風呂で遊びすぎだってば。もう寝る時間だよ。明日の時間割、ちゃんとわかってるよね?」
「もうランドセルに入れたよ。オレはお母ちゃんとは違うんだから。忘れ物なんてしないよ」
「はいはい。ほら、ベッドに行くよ。修に『おやすみ』は」
「お父ちゃんおやすみなさい」
「おやすみ。えっ? お父ちゃん? 昂幸、今『お父ちゃん』って言ったのか?」
「えへへ、そろそろサンタのおじちゃんはおしまい。お父ちゃんおやすみなさい」
「タカ……。おやすみ」
初めて昂幸が修を『お父ちゃん』と呼んだ。それを聞いた修の目には涙が浮かんでいた。美梨はそれを見て目頭が熱くなった。
美梨はニコニコ笑っている昂幸を子供部屋に連れて行き、ベッドに寝かせた。
「おやすみなさい、昂幸」
「お母ちゃんおやすみ。お父ちゃん泣いてたね。どうして?」
「昂幸にお父ちゃんって呼ばれて嬉しかったのよ」
「そっか。お父様も三田のお家を出た時に泣いてたね。大人って泣き虫なんだね」
「そうね。大人は泣き虫だね。涙ってね、悲しくても寂しくても嬉しくてもでるのよ。大人は涙脆いから、昂幸が一番強いのかも。いい夢をみなさい。おやすみ」
美梨は昂幸の額にキスを落として照明を消した。
リビングに戻ると、修はソファーに座り缶ビールを飲みながらテーブルの上に置かれたままになっている携帯電話のアプリに見入っていた。
「美梨がまさか乙女ゲームにハマッてるとはな。イケメンが育児の気晴らしになるのならしてもいいよ。本当に浮気されたら困るけどな」
「やだ、これは違うの。この乙女ゲームの原作者は元OLなのよ。ペンネームは『マリリン』なんだけどね」
「マリリン!?」
「やだどうしたの? 修、この乙女ゲーム知ってるの? 登場するメイドの名前もマリリンなのよ」
「メイドも!? 乙女ゲームなんて知らないよ」
「それがね、この乙女ゲームの登場人物が私や私の友達や、姫香の恋人の公平くんにキャラが似てるのよ。執事はみんなイケメンだし、我が儘な公爵令嬢は私にそっくりなのよ。執事の一人は異世界から来た青年でね。そう言えばレイモンドって修に似てるわね」
「レイモンドだって!?」
驚いた修は思わず口に含んだビールを吹き出す。
「やだな。修、何を慌ててるの」
美梨は修が吹き出したビールを布巾で綺麗に拭き取る。
「そのレイモンドはどうなったんだ?」
「この乙女ゲームはノベル式だから、本を読み進めていくみたいに、次の展開はプレイヤーの意思で選択できるの。だからプレイヤーによってエンディングは異なるのよ」
「美梨はどうプレイしたんだよ」
「私? 公爵令嬢は執事のレイモンドを愛しながらも、隣国の王太子殿下に見初められて結婚するんだけど、王子の誘拐事件がきっかけでレイモンドは妃殿下に『一緒に元の世界に戻らないか』と誘うの。私はそれを選択せず、妃殿下は王太子殿下と幸せに暮らす結末にしたわ。そうすればレイモンドは元の世界に戻れるから。私はレイモンドと修を重ねて見てたから、レイモンドには元の世界に戻って欲しかったんだ」
「……そ、そうなんだ」
修は奇妙な偶然に驚いていた。
「私は三田と別れたけど、誘拐事件とかよく似てるの。この原作者のマリリンって、私達の知り合いだったりして」
修はそれを聞いて、脳裏に一人の女性の顔が浮かんだ。
(まさか……美波が乙女ゲームの原作者? 確かに美波は乙女ゲームが好きだったけど。俺は事故で美波の書いた乙女ゲームの世界に飛ばされていたのか!?)
(いや、辻褄が合わない。美梨が俺の初体験が『三十点』だと言ったのは、タクシー運転手と俺しか知らないはずだ。乙女ゲームのメイサがそのセリフを話すなんてあり得ない。)
(まさか、あのタクシー運転手がこの世界に戻ったあと、客である美波に面白可笑しく話したのか? いや、それでは時期的に辻褄が合わない。美波は俺のことをそのレベルだと勝手に妄想して書いたのか? そんなバカな。)
顔面蒼白な修に、美梨が顔を近付ける。
夜、美梨はソファーに座ったまま携帯電話で何やら遊んでいるようだった。修は昂幸と風呂上がりの髪を拭きながら美梨に近付く。
「お母ちゃん、何してるの? あーー、お母ちゃんがゲームしてる」
「昂幸、修にバラさないで。優が寝てるからちょっと休憩していただけだよ」
修は缶ビールを持ち美梨に近付き、昂幸と一緒に携帯電話の画面を覗き込む。
「ほら、昂幸はもう歯磨きすんだの? 修に仕上げしてもらった? お風呂で遊びすぎだってば。もう寝る時間だよ。明日の時間割、ちゃんとわかってるよね?」
「もうランドセルに入れたよ。オレはお母ちゃんとは違うんだから。忘れ物なんてしないよ」
「はいはい。ほら、ベッドに行くよ。修に『おやすみ』は」
「お父ちゃんおやすみなさい」
「おやすみ。えっ? お父ちゃん? 昂幸、今『お父ちゃん』って言ったのか?」
「えへへ、そろそろサンタのおじちゃんはおしまい。お父ちゃんおやすみなさい」
「タカ……。おやすみ」
初めて昂幸が修を『お父ちゃん』と呼んだ。それを聞いた修の目には涙が浮かんでいた。美梨はそれを見て目頭が熱くなった。
美梨はニコニコ笑っている昂幸を子供部屋に連れて行き、ベッドに寝かせた。
「おやすみなさい、昂幸」
「お母ちゃんおやすみ。お父ちゃん泣いてたね。どうして?」
「昂幸にお父ちゃんって呼ばれて嬉しかったのよ」
「そっか。お父様も三田のお家を出た時に泣いてたね。大人って泣き虫なんだね」
「そうね。大人は泣き虫だね。涙ってね、悲しくても寂しくても嬉しくてもでるのよ。大人は涙脆いから、昂幸が一番強いのかも。いい夢をみなさい。おやすみ」
美梨は昂幸の額にキスを落として照明を消した。
リビングに戻ると、修はソファーに座り缶ビールを飲みながらテーブルの上に置かれたままになっている携帯電話のアプリに見入っていた。
「美梨がまさか乙女ゲームにハマッてるとはな。イケメンが育児の気晴らしになるのならしてもいいよ。本当に浮気されたら困るけどな」
「やだ、これは違うの。この乙女ゲームの原作者は元OLなのよ。ペンネームは『マリリン』なんだけどね」
「マリリン!?」
「やだどうしたの? 修、この乙女ゲーム知ってるの? 登場するメイドの名前もマリリンなのよ」
「メイドも!? 乙女ゲームなんて知らないよ」
「それがね、この乙女ゲームの登場人物が私や私の友達や、姫香の恋人の公平くんにキャラが似てるのよ。執事はみんなイケメンだし、我が儘な公爵令嬢は私にそっくりなのよ。執事の一人は異世界から来た青年でね。そう言えばレイモンドって修に似てるわね」
「レイモンドだって!?」
驚いた修は思わず口に含んだビールを吹き出す。
「やだな。修、何を慌ててるの」
美梨は修が吹き出したビールを布巾で綺麗に拭き取る。
「そのレイモンドはどうなったんだ?」
「この乙女ゲームはノベル式だから、本を読み進めていくみたいに、次の展開はプレイヤーの意思で選択できるの。だからプレイヤーによってエンディングは異なるのよ」
「美梨はどうプレイしたんだよ」
「私? 公爵令嬢は執事のレイモンドを愛しながらも、隣国の王太子殿下に見初められて結婚するんだけど、王子の誘拐事件がきっかけでレイモンドは妃殿下に『一緒に元の世界に戻らないか』と誘うの。私はそれを選択せず、妃殿下は王太子殿下と幸せに暮らす結末にしたわ。そうすればレイモンドは元の世界に戻れるから。私はレイモンドと修を重ねて見てたから、レイモンドには元の世界に戻って欲しかったんだ」
「……そ、そうなんだ」
修は奇妙な偶然に驚いていた。
「私は三田と別れたけど、誘拐事件とかよく似てるの。この原作者のマリリンって、私達の知り合いだったりして」
修はそれを聞いて、脳裏に一人の女性の顔が浮かんだ。
(まさか……美波が乙女ゲームの原作者? 確かに美波は乙女ゲームが好きだったけど。俺は事故で美波の書いた乙女ゲームの世界に飛ばされていたのか!?)
(いや、辻褄が合わない。美梨が俺の初体験が『三十点』だと言ったのは、タクシー運転手と俺しか知らないはずだ。乙女ゲームのメイサがそのセリフを話すなんてあり得ない。)
(まさか、あのタクシー運転手がこの世界に戻ったあと、客である美波に面白可笑しく話したのか? いや、それでは時期的に辻褄が合わない。美波は俺のことをそのレベルだと勝手に妄想して書いたのか? そんなバカな。)
顔面蒼白な修に、美梨が顔を近付ける。