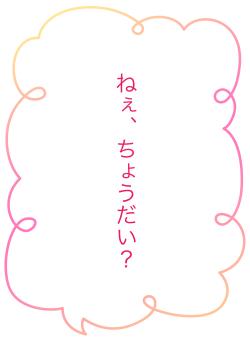観覧車の中は、非日常だった夜の遊園地とは切り離されたような空間だった。
それでもまだ気まずさは消えなくて。
私は下を向いて黙ったままだった。
でも、その沈黙を翔くんが破った。
「…あのさ、ここにくるみを連れてきた理由、本当はなんとなくなんかじゃないんだ」
えっ…?
私は少し驚いて、下を向いていた顔を上げた。
「くるみに、伝えたいことがあって。…家じゃたぶん聞いてくれない気がしたから」
確かに、家だと私は逃げてしまうかも。
ここだったら逃げられない。
翔くんに真剣に向き合うしかないんだ。
…伝えたいことってなんだろう。
「…なに?」
聞くのはとても怖かった。
でも、今ここで聞かなければ後悔すると思った。
「実はさ、俺たち昔1回会ってるんだ」
えっ、会ってる…?
「いつ…どこで?」
私に思い当たる節はなかった。
「幼稚園ぐらいの頃に、ショッピングモールで」
「ショッピングモールって…湊くんと行った?」
私がそう聞くと、翔くんは少しムスッとしながらうなずいた。
ショッピングモール…幼稚園…。
私は記憶の中を探る。
「覚えてないのか?…"泣かないで。僕が必ず、君を笑顔にするから"」
翔くんのその言葉を聞いて、私の記憶が今と結びついた。
幼稚園の頃、私はお母さんと一緒にショッピングモールにお買い物に行った。
その時、私は初めてショッピングモールに行ったから、好奇心からか走り回ってたんだよね。
そしたらいつの間にかお母さんとはぐれちゃって。
半泣き状態でお母さん、お母さんって言って歩き続けてたんだ。
で、なんか歩くのも疲れちゃって。
そのまま床に座り込んだんだ。
そしてお母さんに会えない寂しさで、周りの目も気にせずに泣いてしまった。
すると1人の子ども…私と同じくらいの男の子が、私に声をかけてくれたんだ。
『泣かないで。僕が必ず、君を笑顔にするから』
さっきの翔くんが言ったのは、あの時の男の子が昔の私に行った言葉。
「翔くんが…あの時、迷子の私に声をかけてくれた男の子…!?」
あの時男の子が私に声をかけてくれたから、一緒にいてくれたから。
私は泣かないでいられたし、お母さんにも笑顔で会えたんだ。
私の言葉に、翔くんがうなずく。
…まさかあの男の子が、翔くんだなんて。
そして、今こうして一緒に暮らしてるなんて。
本当に世界は狭い。
「…それで、お前あの時言った言葉、覚えてるか?」
言った言葉?
私あの時何か言ったっけ。
もう何年も昔のことだから、細かいことまで覚えてない。
私が首を横に振ると、
「覚えてないのかよ。…お前、あの時人気だった男のアイドルのポスター見て、笑顔になったんだよ」
アイドル…もしかして、私が一時期好きだったあのアイドルのかな?
「そしてお前言ったんだ。"すごい…!カッコいい!"ってな。それも満面の笑みで」
そうなんだ。
それが私があのアイドルを好きになった理由だったんだ。
「だから、俺。あの時決めたんだ。この子を笑顔にできるアイドルになろうって」
…え?
「お前を、笑顔にするために」
私の、ために…!?
呆気に取られて、翔くんから目が離せない。
観覧車から見える、たくさんの星やイルミネーションも、今は私の目にはひとつも映らない。
「そしたらお前、俺がアイドルだって知って距離取るし。話さなくなるし。…もう本当どういうことだよ」
そう言って、下を向く翔くん。
「だ、だってアイドルだったら私とも話さない方がいいかなって思って…」
私がそう言うと、翔くんはゆっくりと顔を上げ、私の目を真っ直ぐに見つめた。
「…お前が嫌なら、アイドルもやめる。テレビにも出ない」
その視線から真剣さが伝わってきて、さらに翔くんから目が離せなくなる。
「俺はお前が好きだ」
翔くんが、私を…好き?
「あの時のお前の笑顔がずっと忘れられなくて。また会えるかもわかんない相手が好きだなんて、らしくないとも思ってて。…でも、また会えた」
翔くんの真っ直ぐな言葉が、私の心に突き刺さる。
「…初めて一緒に買い物に行った帰りに見たお前の笑顔が、昔のお前の笑顔と重なったんだ」
翔くんが私から視線を外さずに、私の両手を自分のそれで包み込む。
「絶対にお前を笑顔にする。…俺と、付き合ってください」
私は息を呑んだ。
こんなに直球で言ってくれるなんて。
そして、私のこの想いも、無くさなくていいなんて。
恥ずかしさで顔を逸らしてしまいたかったけど。
私は視線を外さずに、
「…私も、翔くんのことが好きです。よろしくお願いします」
と言った。
私のその言葉を聞くと、翔くんは安心したのか、ホッと息をついた。
「え、どうしたの?」
「いや…だってお前、俺のこと嫌いなんだと思ってたから」
「は、話さなかったのは翔くんがアイドルだからで…。翔くんのこと好きだったんだけど、忘れなきゃって思ってて…」
翔くんがアイドルだってことを知って、私は全てが終わったような気がした。
もうあんな風には喋れない、笑い合えないんだと。
でも、そんなことはなかった。
「あ、もしかして、ここに誘ってくれたのって…」
「うん、お前に告白するためだよ。…もし断られたらキッパリ諦めるつもりだった」
私も、このお出かけが終わったら、翔くんのことをキッパリ諦めるつもりだった。
翔くんも、私も同じだったんだ。
そのことに気がついて、私は思わずクスッと笑ってしまった。
「おい、なんで笑ってるんだよ」
「いや、私たち似てるなーって思って」
「なんだそれ」
こんな風に、いつも通り話せるのがとても嬉しい。
心からそう思った。