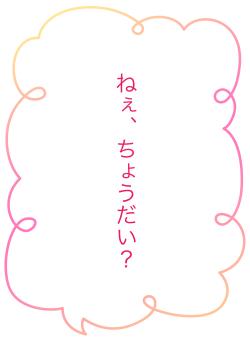少しすると、足音が階段を上がってくるのが聞こえた。
…もしかして、翔くん?
そしてその足音は、私の部屋の前で鳴り止んだ。
コンコンコンッとドアを叩く。
「くるみ、起きてるか?」
その声で、翔くんだってことがわかった。
今の私は目が真っ赤に腫れていて、とても見せられるような顔じゃない。
何も答えなければ入ってこないかなと思い、私は無言で息をのんだ。
「…入るぞ」
うそ、入ってくるの!?
焦る私にお構いなしに、私の部屋のドアはガチャリと開いた。
…あぁ、こんなことなら鍵閉めていればよかった。
「くるみ、お前なんで泣いて…?」
赤くなった目を、見られてしまった。
「…なんでもない」
私はそう言って翔くんから目を逸らした。
なんでもないわけ、ない。
それは私が1番よくわかってる。
でも、その理由は翔くんには言えない。
好きだってことがバレてしまう。
すると翔くんは私が顔を背けた方向に回り込んで来て、
「なんでもないわけないじゃん」
と言って、ギュッと私のことを抱きしめた。
「えっ、ちょっと!」
私はすぐに翔くんから離れた。
顔が真っ赤に染まるのがわかって、思わず下を向く。
「なんで…」
と私が聞くと、
「…だって、ハグって疲れに効くんだろ?」
と翔くんが答えた。
確かに、あの時私はそう言った。
でも…。
「それでも、ダメだよ」
「なんで?」
「だって、翔くんってアイドルじゃん」
気づいたら、その言葉が私の口から発せられていた。
「…やっと気づいたか」
…え?
翔くんは想像以上に落ち着いていた。
やっと気づいた?
じゃあなんで黙ってたの。
翔くんに対する疑問が、次から次に溢れ出す。
でも、私はそれを聞くことができなかった。
そしてなぜか目頭が熱くなって。
「…部屋から出て」
と、毛布にくるまって言った。
翔くんは少し間を開けて、
「…わかった」
と言って私の部屋をあとにした。
翔くんはアイドルだからって思うあまり、私は言いたくないことまで言ってしまう。
翔くんとの溝がどんどん深まっていくように感じるけど。
仲良くなりすぎて、自分の気持ちを抑えられなくなるよりかはマシだ。
目を閉じると、私の頬に再びひとすじの雫が流れた。