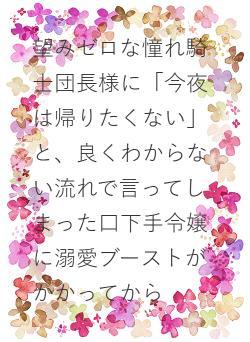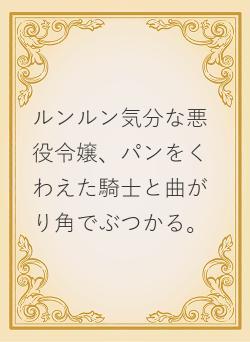彼は愛する息子のユーウェインを甥のリチャードのために取られ、影として育てることには納得はしていなかったようなので、奪還するきっかけとなった私に感謝してくれている。
そして、従兄弟にあたる王太子の代打としてユーウェインが婚約者となることを認められた私の部屋に居て寛ぐことも、公爵令息として立派に仕事をしている彼にとっては当然の事で。
「セシル。本当に美しい」
「もう……何度目? 誉め言葉の価値が下がってしまうから、止めてくれないかしら」
いつもいつも同じように言われているけど、彼のような美形に甘い言葉を囁かれていると思うと、落ち着かないし恥ずかしい。
育ちが良い正統派のリチャードとは違って、彼の影であったユーウェインは例えようもない色気があった。
「今日は、もう言いましたっけ? セシルを褒めるのは、これが初回だと思うんですけど」
「いつもいつも……そうして褒められていると、それが当たり前になってしまうわ。私に飽きてしまったら、どうするの?」
そして、従兄弟にあたる王太子の代打としてユーウェインが婚約者となることを認められた私の部屋に居て寛ぐことも、公爵令息として立派に仕事をしている彼にとっては当然の事で。
「セシル。本当に美しい」
「もう……何度目? 誉め言葉の価値が下がってしまうから、止めてくれないかしら」
いつもいつも同じように言われているけど、彼のような美形に甘い言葉を囁かれていると思うと、落ち着かないし恥ずかしい。
育ちが良い正統派のリチャードとは違って、彼の影であったユーウェインは例えようもない色気があった。
「今日は、もう言いましたっけ? セシルを褒めるのは、これが初回だと思うんですけど」
「いつもいつも……そうして褒められていると、それが当たり前になってしまうわ。私に飽きてしまったら、どうするの?」