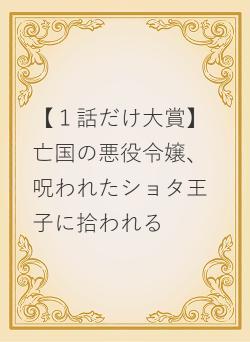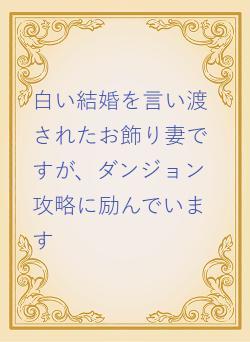「レイナードには教えてあげる、わたしは…」
ナディアはレイナード様のことを敬称をつけずに呼ぶ。
無礼講である学院内では当然それも許されているが、彼女が転入してくるまではレイナード様を呼び捨てにするのはカインだけだった。
レイナード様は、わたしによく不満げに漏らしていた。
「シアはどうして俺のことを昔みたいに『レイ』と呼んでくれなくなったんだ?」
どうしても何も、あなたと婚約してお妃教育で厳しく躾けられたせいよっ!
結婚するまでは、たとえ婚約者といえど王太子殿下のことを親しげに呼ぶのはやめなさいと言われたからよっ!
レイと呼んでほしいと言われる度に、そう叫びたいのをこらえて、少し困った顔を作って「恥ずかしくて…」と答えていたのだ。
ナディアには何の足枷もなく、わたしがいちいち引っかかっているハードルを難なく飛び越えてゆく。
おもしろくないわね…。
思わず本音を心の中でつぶやいてドアを開けると、レイナード様の肩に手をかけ顔を寄せて耳打ちしているナディアの姿と、それを聞いて「よかったじゃないか」と微笑むレイナード様の姿が目に飛び込んできた。
レイナード様は長い脚を投げ出すように組んでナディアのほうに体を傾け、なんともくつろいでらっしゃるご様子だ。
わたしの姿を認めても二人が悪びれる様子はない。
「シア、いまナディアに鑑定結果を聞いていたんだ、シアも教えてもらうといいよ」
どうしてこの人は、笑顔でそんなことをわたしに言えるのだろうか。
「お気遣いありがとうございます。でも、勉強の時間が少なくなってしまいますので、まずは勉強会にいたしましょう」
口角を上げて微笑むと、レイナード様もわたしの提案に納得して、勉強会が始まった。
ナディアはレイナード様のことを敬称をつけずに呼ぶ。
無礼講である学院内では当然それも許されているが、彼女が転入してくるまではレイナード様を呼び捨てにするのはカインだけだった。
レイナード様は、わたしによく不満げに漏らしていた。
「シアはどうして俺のことを昔みたいに『レイ』と呼んでくれなくなったんだ?」
どうしても何も、あなたと婚約してお妃教育で厳しく躾けられたせいよっ!
結婚するまでは、たとえ婚約者といえど王太子殿下のことを親しげに呼ぶのはやめなさいと言われたからよっ!
レイと呼んでほしいと言われる度に、そう叫びたいのをこらえて、少し困った顔を作って「恥ずかしくて…」と答えていたのだ。
ナディアには何の足枷もなく、わたしがいちいち引っかかっているハードルを難なく飛び越えてゆく。
おもしろくないわね…。
思わず本音を心の中でつぶやいてドアを開けると、レイナード様の肩に手をかけ顔を寄せて耳打ちしているナディアの姿と、それを聞いて「よかったじゃないか」と微笑むレイナード様の姿が目に飛び込んできた。
レイナード様は長い脚を投げ出すように組んでナディアのほうに体を傾け、なんともくつろいでらっしゃるご様子だ。
わたしの姿を認めても二人が悪びれる様子はない。
「シア、いまナディアに鑑定結果を聞いていたんだ、シアも教えてもらうといいよ」
どうしてこの人は、笑顔でそんなことをわたしに言えるのだろうか。
「お気遣いありがとうございます。でも、勉強の時間が少なくなってしまいますので、まずは勉強会にいたしましょう」
口角を上げて微笑むと、レイナード様もわたしの提案に納得して、勉強会が始まった。