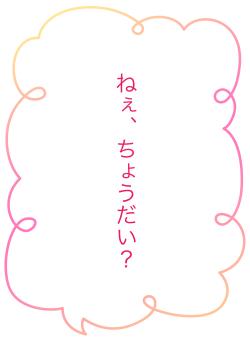次の日、僕は木下さんに言われた通り、中央病院にやってきた。
ドアを数回ノックしてから105号室のドアを開けると、昨日よりもさらにやつれた木下さんがいた。
「来てくれたんだね。嬉しい」
そう話す木下さんの声も、やけにか細く聞こえた。
「約束したからね」
「ふふっ、そうだね。私があんなに念押ししたからね」
そう言って、微かに笑う。
「…あのさ」
木下さんがこちらを見る。
「木下さんが僕と話したり、ゲームセンターに行ったりしたのは、星に帰る前の思い出作り?」
僕の言葉に、木下さんは少し驚いた様子を見せた。
そして、ゆっくりと口を開き、
「そうだよ」
と言った。たった4文字の言葉なのに、僕にはやけに重く感じた。
「私が君の高校に転校した時、あと1ヶ月くらいで帰らなきゃってことはわかってたし。最後の思い出作りだったんだよ」
「じゃあなんで僕なの」
「それは、席が隣だったからね」
もしかして僕に一目惚れしたのかも、という淡い期待は、すぐに壊された。
「転校して、隣の席の子と仲良くなるってのが、私の夢みたいな感じだったから」
ということは、木下さんの隣が僕でなかったら、僕以外の人と話してたし、僕以外の人とゲームセンターに行ってたかもしれないのか。
「木下さん、退院したらさ、遊園地行こうよ」
「え?」
「1週間後までには退院するでしょ。…そしたらさ、遊園地行こうよ」
こう言っている今でも、僕は僕が何を言っているのかが自分でもよくわからなかった。
木下さんも困っているのがわかった。でも木下さんは笑って、
「うん、行こう」
と、言ってくれた。
「あ、そうだ。木下さんには言ってなかったんだけどさ」
「うん」
「僕も宇宙人なんだよね」
「え?…どこの星?」
「スターチス星っていうんだ」
「へぇ」
その言葉を最後に、病室は沈黙に包まれた。
そして、その沈黙が破られることはなかった。
ドアを数回ノックしてから105号室のドアを開けると、昨日よりもさらにやつれた木下さんがいた。
「来てくれたんだね。嬉しい」
そう話す木下さんの声も、やけにか細く聞こえた。
「約束したからね」
「ふふっ、そうだね。私があんなに念押ししたからね」
そう言って、微かに笑う。
「…あのさ」
木下さんがこちらを見る。
「木下さんが僕と話したり、ゲームセンターに行ったりしたのは、星に帰る前の思い出作り?」
僕の言葉に、木下さんは少し驚いた様子を見せた。
そして、ゆっくりと口を開き、
「そうだよ」
と言った。たった4文字の言葉なのに、僕にはやけに重く感じた。
「私が君の高校に転校した時、あと1ヶ月くらいで帰らなきゃってことはわかってたし。最後の思い出作りだったんだよ」
「じゃあなんで僕なの」
「それは、席が隣だったからね」
もしかして僕に一目惚れしたのかも、という淡い期待は、すぐに壊された。
「転校して、隣の席の子と仲良くなるってのが、私の夢みたいな感じだったから」
ということは、木下さんの隣が僕でなかったら、僕以外の人と話してたし、僕以外の人とゲームセンターに行ってたかもしれないのか。
「木下さん、退院したらさ、遊園地行こうよ」
「え?」
「1週間後までには退院するでしょ。…そしたらさ、遊園地行こうよ」
こう言っている今でも、僕は僕が何を言っているのかが自分でもよくわからなかった。
木下さんも困っているのがわかった。でも木下さんは笑って、
「うん、行こう」
と、言ってくれた。
「あ、そうだ。木下さんには言ってなかったんだけどさ」
「うん」
「僕も宇宙人なんだよね」
「え?…どこの星?」
「スターチス星っていうんだ」
「へぇ」
その言葉を最後に、病室は沈黙に包まれた。
そして、その沈黙が破られることはなかった。