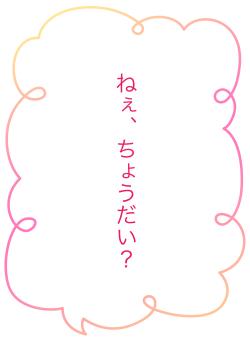公園に着くと、先輩はベンチに座った。私もそれに続いて座る。
お互いがお互いの顔色を伺い、なかなか沈黙から抜け出せない。
でも、それを破ったのは先輩だった。
「俺さ、お前に一目惚れしてたんだよね」
「えっ!?…いつ、ですか」
先輩の急な告白に、頭が追いつかない。
「お前んとこの喫茶店に行った時、…2回目だったかな。お前俺がミルク多めって言ったのに、ブラックを出してくれただろ」
「…はい」
「あの時、俺の素顔が初めて家族以外にバレたんだよな。…カズにもバレてなかったのにさ」
コーヒーのことは、ホントに賭けだったんだよね。もしかしたら違ったのかも知れなかったし。
「お前なら、この時の俺もしっかりと受け止めてくれる。そばにいてくれるって、思ったんだ」
先輩の目は、いつになく真剣だった。
「でもお前は俺のことを知らない。だからどうにかして特別な関係になりたくて、ニセカノをお願いしたんだ」
だから、私に…。
「お前が見てるの知っててハリナと話したのは、お前にヤキモチを焼いて欲しかったから。…ニセモノなのに、変だよなぁ…。でも、俺そんだけお前が好きだったんだよ」
先輩はハハッと笑う。でもその目はとても悲しそうだった。
「変じゃ、ないです…。先輩が変なら、私の方がもっと変です…」
「…え?」
「先輩のことが好きなのに、わざと離れようとしました…。自分が傷つくのがいやで…」
あの時の感情も、先輩に言った言葉も、今ならわかる。完全にヤキモチだった。
「私の先輩なのに、なんでって。…私も一目惚れだったんです」
「う、そ…」
「本当です。…私は、道宮アサヒ先輩のことが、好きです」
すると先輩は一瞬驚いた顔をして、私を両手で抱きしめた。
「…俺も、ずっと立花チハルが好きだ。…誰にも、渡したくない」
私も先輩の大きな背中に手をまわす。
少し暑さが残る夏の夜。すれ違い続けた私たちの心の矢印が、今同じ方向を向いた。
この恋は、苦くて、甘い、青春だ。
お互いがお互いの顔色を伺い、なかなか沈黙から抜け出せない。
でも、それを破ったのは先輩だった。
「俺さ、お前に一目惚れしてたんだよね」
「えっ!?…いつ、ですか」
先輩の急な告白に、頭が追いつかない。
「お前んとこの喫茶店に行った時、…2回目だったかな。お前俺がミルク多めって言ったのに、ブラックを出してくれただろ」
「…はい」
「あの時、俺の素顔が初めて家族以外にバレたんだよな。…カズにもバレてなかったのにさ」
コーヒーのことは、ホントに賭けだったんだよね。もしかしたら違ったのかも知れなかったし。
「お前なら、この時の俺もしっかりと受け止めてくれる。そばにいてくれるって、思ったんだ」
先輩の目は、いつになく真剣だった。
「でもお前は俺のことを知らない。だからどうにかして特別な関係になりたくて、ニセカノをお願いしたんだ」
だから、私に…。
「お前が見てるの知っててハリナと話したのは、お前にヤキモチを焼いて欲しかったから。…ニセモノなのに、変だよなぁ…。でも、俺そんだけお前が好きだったんだよ」
先輩はハハッと笑う。でもその目はとても悲しそうだった。
「変じゃ、ないです…。先輩が変なら、私の方がもっと変です…」
「…え?」
「先輩のことが好きなのに、わざと離れようとしました…。自分が傷つくのがいやで…」
あの時の感情も、先輩に言った言葉も、今ならわかる。完全にヤキモチだった。
「私の先輩なのに、なんでって。…私も一目惚れだったんです」
「う、そ…」
「本当です。…私は、道宮アサヒ先輩のことが、好きです」
すると先輩は一瞬驚いた顔をして、私を両手で抱きしめた。
「…俺も、ずっと立花チハルが好きだ。…誰にも、渡したくない」
私も先輩の大きな背中に手をまわす。
少し暑さが残る夏の夜。すれ違い続けた私たちの心の矢印が、今同じ方向を向いた。
この恋は、苦くて、甘い、青春だ。