「ユーシィ」
そんなあたし達を厳しい声色が止めていた──ラヴェルのあたしを呼ぶ声。
「悪いけどこれ以上、君と遊んでいる暇はない」
「遊んでなんかっ──」
「レイピアを返してくれ。それと……しばらく辛抱してて」
ラヴェルは自分の肩に掛けていたタオルの端を手にし、それを揺らしながら何かを唱えた。やがてタオルは長く細く変化して、あたしの胴に巻き付き、エントランスへ引っ張って、真ん中に聳える柱にあたしを括りつけてしまった!
「君の魂胆は分かってる……自分達が危うくなった時、捨て身の盾になるつもりなんでしょ? 昔のタラのように……でもスティだってバカじゃない。もうその手は通用しないよ」
「だけどっ!」
あたしはロープと化したタオルに拘束されながら、柱を背に反論の言葉で食い下がった。だけど……だって……花嫁はあたし独りなのだもの。きっと『その時』に役に立てる筈!
「ピータン、アイガー、君達もじっとしてて」
ラヴェルは次に金網状の傘立てを手に取り、それを数回さすって再び何かを唱えた。徐々に大きくなっていく傘立てはやがてドーム状となり、ピータンとアイガーを覆うケージとなって二匹を囲ってしまった。
「嫌よっ、ほどいて! お願いだから連れていって!!」
自室へロングソードを取りに戻り、エントランスを出ようとするラヴェルの背に、最後の嘆願の叫びを放つ。けれど振り向いたその顔には、もう微笑みなんて形容は有り得なかった。
「君は足手まといなんだよ」
「あ……」
こちらを見詰める揺るがない瞳は、もうあたしを映していない。
「ラウル……」
さすがのタラも、その冷たい言葉に閉口したみたいだった。
「行こう、タラ」
「ウ、ウン~」
「ラっ──」
名前を呼ぶ前に扉は閉じられ、二人の姿は隠されてしまった。
「ラヴェル……ラ、ヴェル……──」
あたしの呼び声は小さく淋しくエントランスに反響した──。
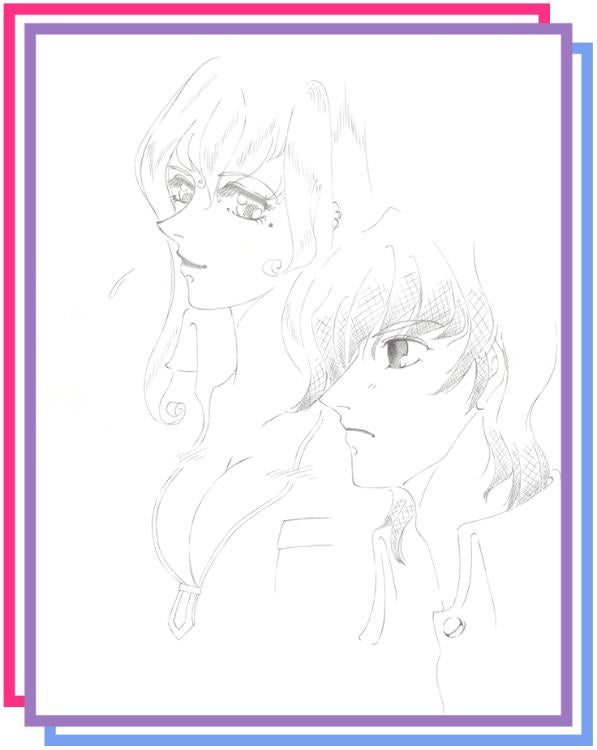
そんなあたし達を厳しい声色が止めていた──ラヴェルのあたしを呼ぶ声。
「悪いけどこれ以上、君と遊んでいる暇はない」
「遊んでなんかっ──」
「レイピアを返してくれ。それと……しばらく辛抱してて」
ラヴェルは自分の肩に掛けていたタオルの端を手にし、それを揺らしながら何かを唱えた。やがてタオルは長く細く変化して、あたしの胴に巻き付き、エントランスへ引っ張って、真ん中に聳える柱にあたしを括りつけてしまった!
「君の魂胆は分かってる……自分達が危うくなった時、捨て身の盾になるつもりなんでしょ? 昔のタラのように……でもスティだってバカじゃない。もうその手は通用しないよ」
「だけどっ!」
あたしはロープと化したタオルに拘束されながら、柱を背に反論の言葉で食い下がった。だけど……だって……花嫁はあたし独りなのだもの。きっと『その時』に役に立てる筈!
「ピータン、アイガー、君達もじっとしてて」
ラヴェルは次に金網状の傘立てを手に取り、それを数回さすって再び何かを唱えた。徐々に大きくなっていく傘立てはやがてドーム状となり、ピータンとアイガーを覆うケージとなって二匹を囲ってしまった。
「嫌よっ、ほどいて! お願いだから連れていって!!」
自室へロングソードを取りに戻り、エントランスを出ようとするラヴェルの背に、最後の嘆願の叫びを放つ。けれど振り向いたその顔には、もう微笑みなんて形容は有り得なかった。
「君は足手まといなんだよ」
「あ……」
こちらを見詰める揺るがない瞳は、もうあたしを映していない。
「ラウル……」
さすがのタラも、その冷たい言葉に閉口したみたいだった。
「行こう、タラ」
「ウ、ウン~」
「ラっ──」
名前を呼ぶ前に扉は閉じられ、二人の姿は隠されてしまった。
「ラヴェル……ラ、ヴェル……──」
あたしの呼び声は小さく淋しくエントランスに反響した──。
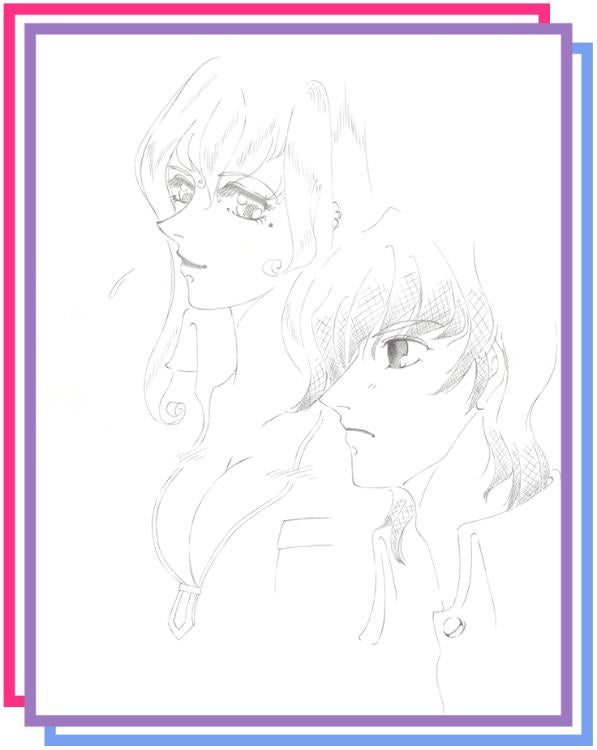




![月とガーネット[下]](https://www.no-ichigo.jp/img/member/1247997/zcrelg1uqj-thumb.jpg)
![月とガーネット[上]](https://www.no-ichigo.jp/img/member/1247997/qwurwj3tz2-thumb.jpg)