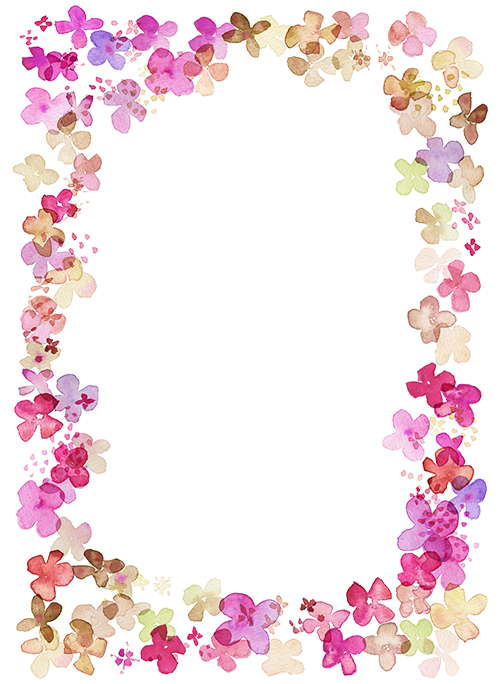「キミがみんなと距離を置く理由は?」
「私の両親は最低なんです」
「?」
「私は両親との思い出がありません。仕事が忙しいし、仕方ないって思ってたんです」
小さい頃はよく駄々こねて困らせてたよね。
「それに私は産まれて来なきゃよかったって思ったことさえあるんです。父も母もお金はくれます。欲しいと願えば大抵の物は手に入る。けど、"愛情"だけは手に入らなかった。
父からも母からも愛情は貰えなかった。
もちろんこれがどれだけ贅沢なことかわかってます」
私がそう言うと弁慶さんは優しく微笑みながら言ってきた。
「キミに愛情をくれた人はいなかったんですか?」
「それはっいなくはないです。天后がいましたし、祖母もいました」
私にはわかっていた。
この想いが贅沢だってことくらい。
けれど、私は母さんたちに愛されたかった。
他の子のように。
「天后とは?」
「私のことよ」
弁慶さんがそう聞いた途端。
いつも、私のそばにいる猫に化けている天后が人間の姿へと変えた。
「私が天后よ!明里様の家族のようなものよ」
「ちょっ!天后」
「いいじゃないですか。未来から来たってわかってるなら」
「ね、明里さん。俺に教えてくれませんか?」
「う゛っ、わかりました。ただし他言無用でお願いします」
「キミと俺との秘密ですね」
悪戯っぽく笑う弁慶さんに対して頷く。
私は全て話した。
未来の水城家の当主だということ。
そして、当主就任の儀式の日にトラブルがあったこと。
そして何故か、『平清盛』が友達に憑依されていたということを。
そして、気がつけばこの世界にいて、愁一郎に拾われたこと。
話し終わると弁慶さんは、私の頭を撫でてくる。
「弁慶さん?」
「明里さん。さみしくないんですか?怖くはないんですか?」
「それはっ」
私は言葉に詰まった。
だって考えないようにしていたから。
私1人じゃないし、天后もいるのだからと言い聞かせていたから。
「私の両親は最低なんです」
「?」
「私は両親との思い出がありません。仕事が忙しいし、仕方ないって思ってたんです」
小さい頃はよく駄々こねて困らせてたよね。
「それに私は産まれて来なきゃよかったって思ったことさえあるんです。父も母もお金はくれます。欲しいと願えば大抵の物は手に入る。けど、"愛情"だけは手に入らなかった。
父からも母からも愛情は貰えなかった。
もちろんこれがどれだけ贅沢なことかわかってます」
私がそう言うと弁慶さんは優しく微笑みながら言ってきた。
「キミに愛情をくれた人はいなかったんですか?」
「それはっいなくはないです。天后がいましたし、祖母もいました」
私にはわかっていた。
この想いが贅沢だってことくらい。
けれど、私は母さんたちに愛されたかった。
他の子のように。
「天后とは?」
「私のことよ」
弁慶さんがそう聞いた途端。
いつも、私のそばにいる猫に化けている天后が人間の姿へと変えた。
「私が天后よ!明里様の家族のようなものよ」
「ちょっ!天后」
「いいじゃないですか。未来から来たってわかってるなら」
「ね、明里さん。俺に教えてくれませんか?」
「う゛っ、わかりました。ただし他言無用でお願いします」
「キミと俺との秘密ですね」
悪戯っぽく笑う弁慶さんに対して頷く。
私は全て話した。
未来の水城家の当主だということ。
そして、当主就任の儀式の日にトラブルがあったこと。
そして何故か、『平清盛』が友達に憑依されていたということを。
そして、気がつけばこの世界にいて、愁一郎に拾われたこと。
話し終わると弁慶さんは、私の頭を撫でてくる。
「弁慶さん?」
「明里さん。さみしくないんですか?怖くはないんですか?」
「それはっ」
私は言葉に詰まった。
だって考えないようにしていたから。
私1人じゃないし、天后もいるのだからと言い聞かせていたから。