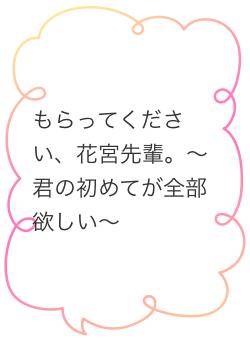イタリアンのお店に向け、隣を歩く新田さんを盗み見ると、柔らかなブラウンの髪が風に揺れてキラキラと輝いている。
背の高さだけでも目立つのに、顔までかっこいいから通る人通る人、みんながちらりと新田さんを見ていた。
こんな人が、なんで私なんかを。
私はそんなに鈍感ではない。
だから、新田さんが私に好意を抱いてくれてるのをなんとなく分かってる。
遊び人だったこの人が、セフレ全て切って私の隣にいる。それが全てだ。
元カレと付き合っている頃は、意識がそちらにばかりいっていたから気付かなかったけど、ここまであからさまに私の時間のほぼ全てを独占しようとしてくる姿や、ジッと向けられる熱の篭った視線に、これが自惚れでないことが嫌でも分かってしまう。
そして、失恋したばかりの私の心に、その恋情はじわじわと浸透してきていた。
「……あーあ、想像もしてなかったなぁ」
「ん? 何がだよ」
「別に、なんでもないです」
傷付いて、あれだけ苦しんだ恋を終えたばかりなのに、まだ私の心は恋をしたいと叫んでいる。
恋を馬鹿にしていた、この男に。
***