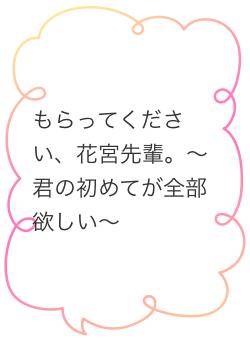「洸、私はもう死のうなんて思わないから」
「ああ」
「だから、洸も──」
次の瞬間、手首を引かれ、洸の胸に抱き寄せられる。洸の香水とタバコの匂いに包まれ、私は固まった。ドキンドキンと心臓の音が身体中に響く。
そして、耳元で優しい声が聞こえた。
「都、元気でな。お前に出会えて良かった。……この夏をお前と過ごせて、幸せだった」
トンと、身体が離される。
私は洸の顔を見上げる。洸は優しくこちらを見下ろし、私に白い封筒を差し出した。
「それ、約束のやつ。車の中で見ろよ」
「え? 約束のやつ……?」
「忘れてんのかよ! ったく……」
「待って、今思い出すからっ」
「そんなこと言ってたら日が暮れちまうよ。ほら、親が呼んでるぞ」
肩を掴まれ、くるりと方向転換させられる。そして背中を押され、両親の乗り込んだ車に押し込まれた。文句を言おうとすると、バタンとドアが閉められる。洸は窓の外から、笑顔でこちらを見つめていた。
──また冬に来れる。なのに何故か、この別れがとても名残惜しかった。