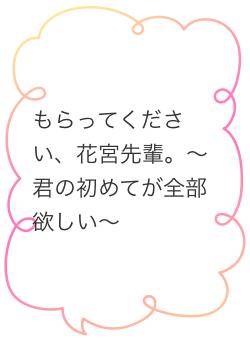自転車の荷台に乗っていて日差しがキツかったから。
カキ氷を一口含むと、干からびていた喉が潤っていく。向かいに座った理玖も同じなのか、額には汗が滲んでいた。大きな口でカキ氷を頬張り、その冷たさに目を細めていた。
「美味い」
「……うん。美味しい」
「俺、瀬名理玖。苗字で呼ばれ慣れてないから名前でいい。因みに高二。都はいくつ」
今更過ぎる自己紹介と質問に面食らう。返事をすべく、口の中に入れたばかりのカキ氷を急いで飲み込んだ。
「私も高二」
「ふーん。それで、なんで洸のとこにいんの」
「なんで……私夏休み中おばあちゃん達のところにいる予定で、おばあちゃん達が洸と知り合いだったから……えっと、流れで」
「流れね……まぁ、洸ならそうなるのも分かる。アイツ顔に似合わず妙にお人好しだから」
「えっと……理玖は洸と知り合って長いの?」
「物心つく頃にはもう知ってた。洸はこの街の有名人だから」
「有名人?」
「昔からどんなに素行が悪くても、年寄りや女子供にはすげー優しい。困ってる人間に迷いなく手を差し伸べる。だからこの街の人間はみんな洸が好き」
理玖はバクバクとカキ氷を食べ進めるが、私は自分の知らない洸の話が聞けるのが楽しくて、食べる手を止めてしまいカップに水滴が滲んでカキ氷が溶け始める。